人体の機能
| 臓器名 | 主な機能 | 主な構成器官 | 疾患 |
|---|---|---|---|
| 循環器系 | 酸素と栄養の供給 | 心臓、動脈 静脈、リンパ管 | 心筋梗塞 |
| 呼吸器系 | 酸素の摂取と 二酸化炭素の排出 | 気道、肺 | 肺気腫、肺炎、気管支炎 |
| 消化器系 | 栄養と水の摂取、再合成と排泄 | 食道。肝臓、胃 十二指腸、肛門 小腸、大腸等 | 肝炎、腸炎 胃炎、胃潰瘍 |
| 腎臓、泌尿器系 | 血液中の老廃物の排泄 | 腎臓、尿管 膀胱、尿道 | 腎不全 |
| 感覚器系 | 外部刺激の神経系への伝達 感覚器系は神経系と密接な関係を持っている。 | 聴覚器、視覚器 味覚器、嗅覚 | 左記器官の疾患 |
| 筋骨格系 | 身体の構成と運動 | 骨、筋肉 | 骨折 |
| 生殖器系 | 子孫形成と種の保存 | 生殖器 | 生殖器疾患 |
| 皮膚系 | 発汗 | 外皮 | 皮膚疾患 |
| 神経系 | 刺激の中枢への伝達、 中枢からの命令の伝達 | 脳、知覚神経 運動神経、自律神経 | パ―キンソン病 脳出血、脳梗塞 |
| 造血器系 | 赤血球、白血球、血小板の生成 | 骨髄、脾臓 | 血友病、白血病 |
| 内分泌系 | 成長、代謝等の活性のコントロ―ル | 視床下部、下垂体 副腎、甲状腺、性腺 | 甲状腺疾患 |
- 知覚神経:感覚器からの刺激を中枢に伝達
- 運動神経:中枢からの命令を筋骨格系に伝達
- 自律神経:消火、呼吸、循環の諸機能の調整
- 物理的要因
- 温度、湿度、気流、熱、光、音,気圧、放射線、超音波、振動など
- 化学的要因
- 空気、酸素、二酸化炭素、オゾン、一酸化炭素、硫黄酸化物、粉じん、水、し尿、廃棄物など
- 生物学的要因
- 植物、ウイルス、細菌、寄生虫、昆虫、ねずみ、動物、リケッチアなど
- 社会的要因
- 文化、教育、産業、経済、情報、交通、医療、福祉、行政、宗教など
体熱平衡と熱産生・熱放射
人体の熱産生と熱放射のバランス(体熱平衡)によって決まる。
したがって、熱産生量と熱放散量が等しければ体温は一定(約37℃)に保たれる。
- 熱産生量が熱放散量より大きくなれば体温は上昇する。
- 熱放散量が熱産生量より大きくなれば体温は低下する。
- 対流・・・流体の流れに伴う熱エネルギーの移動現象です。
- 放射・・・物体から熱エネルギーが電磁波として放射される現象のことです。
- 伝導・・・身体と直接接触する物体との間の熱移動現象のこと。
- 蒸発・・・水分が皮膚より気化するときに熱を奪う現象のことです。
- 放射・・・・・・・・45%
- 伝導・対流・・・・・30%
- 蒸発・・・・・・・・25%
- 自律性体温調節
- 暑さに対する反応
- 発汗、皮膚血管の増大(皮膚血管の拡張)、呼吸数の増加
- 寒さに対する反応
- 皮膚血管の減少(皮膚血管の収縮)、震え、立毛、筋緊張
- 暑さに対する反応
- 行動性体温調節
- 空調設備を付ける。衣服を着る。日射を避ける。冷たい飲み物を飲む等
- 足の皮膚温が25℃
- 手が30℃
- 顔が34℃
- 直腸温が36℃
| 熱産生機能 | 熱放散機能 |
|---|---|
| 摂取した食べ物の代謝 運動 筋緊張・ふるえ | 発汗による蒸発 皮膚血管の拡張 呼吸数の増加 |
体温
人の体温は平均して36℃~37℃程度で維持されている。1日のうちで早朝は低く夕方は高い。
気温が23℃のとき
- 足の皮膚温が25℃
- 手が30℃
- 顔が34℃
- 直腸温が36℃
ポイント・・・・つまり温度の高い順から
直腸温 > 顔 > 手 > 足
他は核心温で外気温の影響を受けにくく、その中でも直腸温が最も受けにくい。
- 長時間体が冷えると発生
- 冷気に当たると抹消血管の縮小、血流が減少し「体が冷える」「体がだるい」「喉が痛い」等の症状を訴える。
- 冷房時は室温と外気温の差を7℃以上にしない。
- 温度差を大きくすると体温調整がうまく働かなくなり暑い時に汗をかき、寒い時にふるえが起きる等、体に余分な負担がかかる調整が必要になる。
- 足が冷える、体が冷えるという症状は男性よりも女性に多い。
- 座業が長く続く場合は軽い運動、女性はストッキングをはくなど対策が必要。
- 冷房時には温度だけでなく湿度・風速にも注意
- 直接冷房の冷気があたらないようにする。
- 低体温症とは、体の深部体温が35℃以下に低下した状態を指します。
- 5℃以下の水に突然に漬かると、5分~15分間でで生命にかかわる低体温症を生じる。
- 天候にもよるが、気温が13~16℃程度でも低体温症になることがある。
- 低体温症の診断には、直腸温を測定する。(一般の体温計では正確に測定できない。)
- 低湿度になった場合の影響及び害
- 冬期は低湿度になりやすい。
- 静電気が発生(冬に静電気が発生するのは湿度が低いため)。
- ウイルスに感染しやすい(冬にインフルエンザにかかりやすいのも湿度が低いためである)。
- 鼻やのどの粘膜に乾燥しやすい。
- アトピ―性皮膚炎や気管支喘息の患者では、低湿度が悪化因子となりうる。
- 電気ショック。
- 塗装の剥離。
- 乾燥し過ぎ(火災の危険)。
- 高湿度になった場合の影響及び害
- 蒸し暑い不快感を感じる。
- 建築物の結露の発生。
- かびやダニが発生。
- 建材の腐朽。
- アレルギ―疾患の発生。
- 汗ばみ・汗によるものの汚れ。
- 建築物・建具等の狂い。
- 結露(表面・内部)
- 結露水による汚れ
- 壁体内部に断熱材を入れる。
- 窓には二重ガラスや断熱戸を用いる。
- 適当な量の換気を行う。
- 家具と壁に隙間等を作り、気流を通す。
- 水蒸気の発生を極力抑える。
- 温度の分布を極力抑える。
- その他、露点温度以下にならないよう努める。
- 壁体内部に断熱材をいれ、防湿層を高湿側に入れる。
- 外断熱にする。
- その他、内部結露と同様の注意をする。
快適温度
多くの実験から平均皮膚温と温冷感申告には、皮膚温が低いと寒い、皮膚温が高いと暑いと感じる一次相関が見られることが多い。 平均皮膚温は通常は33℃~34℃程度で、35℃を超えると暑さを感じ、31℃を下回ると寒さによる不快感を感じる。
局所温冷感に関しては、手の皮膚温が20℃以下となると不快な冷たさを感じ、15℃以下では極限の冷たさを感じ、10℃以下まで下がると痛みを感じるとされている。
ちなみに足では手より約3℃高い皮膚温で同じ症状が出る。ポイント・・・・
- 平均皮膚温・・・・33℃~34℃
- 暑さを感じる・・・35℃
- 寒さを感じる・・・31℃
- 不快な冷たさ・・・21℃
- 極限・・・・・・・15℃
- 痛み・・・・・・・10℃
快適性に影響する因子
環境因子
- 気温
- 湿度
- 風速
- 熱放射
人間側の因子
- 着衣量
- 作業強度
性による快適温度
多くの調査により、女性の快適温度は男性よりも1~2℃高いと報告されている。
原因としてはオフィス内では女性は男性より薄着であること。
女性の低い基礎代謝や低い皮膚温等が考えられている。
高齢者の快適温度
高齢者の快適温度の問題も良く出題されます。高齢者は身体活動量が少なく、また代謝量も少ないため、一般に若年者より暖かい室温を好むとされている。一方、冬期の住宅内の温度測定してみると、 高齢者の室温は若年者と比較して低い場合が多い。
この原因として、高齢者の寒さに対する感受性の低下が考えられ、そして感受性の低下の原因としては、皮膚からの温度情報の減少が一因であると考えられている。
建築物の環境衛生②
快適温度
多くの実験から平均皮膚温と温冷感申告には、皮膚温が低いと寒い、皮膚温が高いと暑いと感じる一次相関が見られることが多い。 平均皮膚温は通常は33℃~34℃程度で、35℃を超えると暑さを感じ、31℃を下回ると寒さによる不快感を感じる。
局所温冷感に関しては、手の皮膚温が20℃以下となると不快な冷たさを感じ、15℃以下では極限の冷たさを感じ、10℃以下まで下がると痛みを感じるとされている。
ちなみに足では手より約3℃高い皮膚温で同じ症状が出る。ポイント・・・・
- 平均皮膚温・・・・33℃~34℃
- 暑さを感じる・・・35℃
- 寒さを感じる・・・31℃
- 不快な冷たさ・・・21℃
- 極限・・・・・・・15℃
- 痛み・・・・・・・10℃
快適性に影響する因子
環境因子
- 気温
- 湿度
- 風速
- 熱放射
人間側の因子
- 着衣量
- 作業強度
性による快適温度
多くの調査により、女性の快適温度は男性よりも1~2℃高いと報告されている。
原因としてはオフィス内では女性は男性より薄着であること。
女性の低い基礎代謝や低い皮膚温等が考えられている。
高齢者の快適温度
高齢者の快適温度の問題も良く出題されます。高齢者は身体活動量が少なく、また代謝量も少ないため、一般に若年者より暖かい室温を好むとされている。一方、冬期の住宅内の温度測定してみると、 高齢者の室温は若年者と比較して低い場合が多い。
この原因として、高齢者の寒さに対する感受性の低下が考えられ、そして感受性の低下の原因としては、皮膚からの温度情報の減少が一因であると考えられている。
同時に測定した深部体温は、高齢者の方が低くなっている。特に、深部体温が35℃未満を低体温症と呼ぶが、高齢者はこの低体温症に陥りやすい。
- 夏の快適温度は、冬に比べ2~3℃高い。
- 女性の方が男性よりも1~2℃高い。
- 高齢者は若者に比べ寒さを感じにくい。
上記項目は覚えましょう。
温熱環境指数
温熱環境指数は、人間が感じる温熱環境の感覚に対応するように作られた、物理量に基づく体感温度を表す指標である。
その基礎となるものは、人間の暑さ寒さに影響を与える温熱環境要素である。
エネルギー代謝量、着衣量、気流、湿度、空気温度、放射温度の6つを人体の熱的快適感に影響する主要な温熱環境要素という。
人間はこれらの温熱環境要素を個々に区別して暑い寒いと感じているわけではなく、それらを複合した結果を感じている。
| 温度環境指数 | 乾球温度・湿球温度・気流 |
| 有効温度 | 乾球温度・湿球温度・気流 |
| 修正有効温度 | 黒球温度・湿球温度・気流 |
| 作用温度 | 乾球温度、気流平均ふく射温度(MRT) |
| 不快指数 | 乾球温度・湿球温度もしくは相対湿度 |
| 新有効温度 | 乾球温度・湿球温度・黒球温度・気流エネルギー代謝量・着衣量 |
| WBGT指数 | 乾球温度・湿球温度・黒球温度 |
建築物の環境衛生2
建築物の環境衛生②
快適温度
多くの実験から平均皮膚温と温冷感申告には、皮膚温が低いと寒い、皮膚温が高いと暑いと感じる一次相関が見られることが多い。 平均皮膚温は通常は33℃~34℃程度で、35℃を超えると暑さを感じ、31℃を下回ると寒さによる不快感を感じる。
局所温冷感に関しては、手の皮膚温が20℃以下となると不快な冷たさを感じ、15℃以下では極限の冷たさを感じ、10℃以下まで下がると痛みを感じるとされている。
ちなみに足では手より約3℃高い皮膚温で同じ症状が出る。ポイント・・・・
- 平均皮膚温・・・・33℃~34℃
- 暑さを感じる・・・35℃
- 寒さを感じる・・・31℃
- 不快な冷たさ・・・21℃
- 極限・・・・・・・15℃
- 痛み・・・・・・・10℃
快適性に影響する因子
環境因子
- 気温
- 湿度
- 風速
- 熱放射
人間側の因子
- 着衣量
- 作業強度
性による快適温度
多くの調査により、女性の快適温度は男性よりも1~2℃高いと報告されている。
原因としてはオフィス内では女性は男性より薄着であること。
女性の低い基礎代謝や低い皮膚温等が考えられている。
高齢者の快適温度
高齢者の快適温度の問題も良く出題されます。高齢者は身体活動量が少なく、また代謝量も少ないため、一般に若年者より暖かい室温を好むとされている。一方、冬期の住宅内の温度測定してみると、 高齢者の室温は若年者と比較して低い場合が多い。
この原因として、高齢者の寒さに対する感受性の低下が考えられ、そして感受性の低下の原因としては、皮膚からの温度情報の減少が一因であると考えられている。
同時に測定した深部体温は、高齢者の方が低くなっている。特に、深部体温が35℃未満を低体温症と呼ぶが、高齢者はこの低体温症に陥りやすい。
- 夏の快適温度は、冬に比べ2~3℃高い。
- 女性の方が男性よりも1~2℃高い。
- 高齢者は若者に比べ寒さを感じにくい。
温熱環境指数
温熱環境指数は、人間が感じる温熱環境の感覚に対応するように作られた、物理量に基づく体感温度を表す指標である。
その基礎となるものは、人間の暑さ寒さに影響を与える温熱環境要素である。
エネルギー代謝量、着衣量、気流、湿度、空気温度、放射温度の6つを人体の熱的快適感に影響する主要な温熱環境要素という。
| 温度環境指数 | 乾球温度・湿球温度・気流 |
| 有効温度 | 乾球温度・湿球温度・気流 |
| 修正有効温度 | 黒球温度・湿球温度・気流 |
| 作用温度 | 乾球温度、気流平均ふく射温度(MRT) |
| 不快指数 | 乾球温度・湿球温度もしくは相対湿度 |
| 新有効温度 | 乾球温度・湿球温度・黒球温度・気流エネルギー代謝量・着衣量 |
| WBGT指数 | 乾球温度・湿球温度・黒球温度 |
体感温度を示すおもな温熱環境指数
| 測定器を用いて計測した示度を指標とする指数 | 湿球温度、カタ冷却力、黒球温度 |
| 実験・経験に基づく指数 | 有効温度、修正有効温度、不快指数、湿球黒球温度(WBGT) |
| 熱平衡式に基づく指数 | 作用温度、予測平均温冷感申告(PMV)、新有効温度 |
- Tw:Wet-bulb temperature(湿球温度)
- Tg:globe temperature(黒球温度)
- Ta:atmosphere temperature(乾球温度、気温)
ということになる。
グロ―ブ温度計によって測定される温度を黒球温度という。
↑
このことは覚えておきましょう。
このことを覚えておけば、Tgは黒球温度となんとなくわかると思う。
Tgのgがglobe(グロ―ブのこと)WBGT指数とは屋内外での暑熱作業時の暑熱ストレスの評価に用いられる。
乾球温度、湿球温度、黒球温度の値を使って算定される。
WBGTの算出方法
- 屋外で太陽放射がある場合(WBGT)=0.7 x 湿球温度 + 0.2 x 黒球温度 + 0.1 x 乾球温度
- 屋内や屋外で太陽y放射がない場合(WBGT)=0.7 x 湿球温度 + 0.3 x 黒球温度
発汗
汗をかくことを発汗という。
汗腺には実際に汗を出す能動汗腺と汗を出さない不能汗腺がある。汗腺には
- アポクリ線
- エクリン線
があり、暑い時にかく汗はエクリン線から分泌される。汗をかくことで体温の上昇を防ぐ。
熱中症
人は恒温動物であり、体温は調節機構により通常は37℃付近に維持されるが、何らかの原因により調節不全または調節不能の状態を来し、異常な体温上昇や 循環不全、電解質異常を来すことにより生じる障害を総称して熱中症という。重症例では、脳内温度の上昇で体温中枢の機能低下、更に体温上昇の悪循環の結果、急激な体温上昇で死に至る。深部温度は41~43℃に達する。頭重、あくび、めまい、視力障碍、四肢運動困難、 体温上昇、嗜眠、けいれん、精神錯乱等の症状が起こる。
従って予防が第一である。発症してしまった場合には迅速・適確な対応が肝要である。
熱中症の種類は下記表に示す通りです。
| (軽症) | 熱失神 | 皮膚血管の拡張によりて血圧が低下し、脳血流が減少して起こる一過性の意識消失 |
| 熱けいれん | 低ナトリウム血症による筋肉のけいれんが起こった状態 | |
| (中等症) | 熱疲労 | 大量の汗により脱水状態となり、全身倦怠感、脱力、めまい、頭痛、吐気、下痢などの症状が出現する状態 |
| (重症) | 熱射病 | 体温上昇のため中枢神経機能が異常をきたした状態 |
| 日射病 | 上記の中で太陽光が原因で起こるもの |
熱失神
長時間、頭頚部が直射日光に曝されることにより抹消血管の拡張を生じ、相対的な体循環血液の減少を来して、めまいや失神が起こることがある。
また、、高温多湿時に急に激しい運動を始めたり、逆に激しい運動をしていたのを急に休止したりした場合、めまいや失神を来すことがある。
熱けいれん
熱の放射時の過剰な発汗により身体から水分と塩分(主にナトリウム)が失われる。その際、水分を大量に摂取すると、塩分が薄まり、有痛性の 筋収縮が生じることがある。これを熱けいれんという。
熱疲労
高温高湿の環境下に長時間居ることにより大量の発汗を来し、体内の水分や塩分が不足することに加え、全身的な循環不全にによる重要諸臓器の機能低下 によるものと考えられる。異常なほど汗をかきながらも、皮膚は青白くてじっとりし、強い疲労感や頭痛、めまい、吐き気、強い口の渇きなどの兆候が特徴である。熱疲労は細胞外液の浸透圧が上昇し、細胞内から水分が細胞外に移動することにより細胞内脱水の状態となっている。このことが熱疲労での症状の原因となっていると考えられる。
暑さに慣れない中での急激な運動や肉体労働、また、乳幼児や衰弱した高齢者などに起こりやすい。熱疲労に気付いたら、すぐに涼しいところへ移動させ、服をゆるめて安静とし、水分補給を開始する。
熱射病
熱射病は、大脳の体温調節中枢が熱によって障害された状態で引き起こされる最も重い温熱障害である。体温が40℃以上であることと脳障害の症状があることが特徴である。
体温調節中枢の機能に障害を来しているため、自力での体温調節ができず、体温が急激に上昇し、危険なレベルまで達する。
熱射病の治療は、全身の冷却が第一であるが冷やし過ぎには十分に注意する。
日射病
熱射病の病態にあって、太陽光が原因で起こったものが日射病とされている。
空気の組成
清浄空気の組成
- 窒素・・・・・・78.08%
- 酸素・・・・・・20.95%
- アルゴン・・・・0.93%
- 二酸化炭素・・・0.04%
- ネオン・・・・・0.0018%
- ヘリウム・・・・0.00052%
酸素濃度の影響
酸素欠乏とは、酸素濃度が18%未満である状態。
| 濃度[%] | 症状 |
|---|---|
| 17~ | 呼吸・脈拍増加、めまい |
| 15~14 | 労働困難・注意力・判断力低下 |
| 11~10 | 呼吸困難、眠気、動作が鈍くなる |
| 7~6 | 顔色が悪い・口唇が青紫色・感覚鈍重・知覚を失う |
| 4以下 | 40秒以内に知覚を失い、卒倒 |
酸素濃度が16~17%となると呼吸や脈拍が増加し、それ以下になると注意力、判断力が低下する。7%以下になると意識がなくなる。
二酸化炭素
二酸化炭素濃度は空気の汚れの一般的な指標とされている。
二酸化炭素は、物質の燃焼や、人間や動物の体内での代謝により発生する。近年、化学燃料の燃焼などによる大気中二酸化炭素濃度の上昇が指摘されており、実際の測定値として 大気中の濃度は0.04%、都市部では、0.05%である。
二酸化炭素は人の呼気に4%含まれている。
二酸化炭素の影響
| 濃度[%] | 症状 |
|---|---|
| 0.55 | 6時間曝露で症状なし |
| 1~2 | 不快感を起こす。 |
| 3~4 | 呼吸中枢を刺激されて呼吸の増加・脈拍・血圧の上昇・頭痛・めまい等起こす。 |
| 6 | 呼吸困難 |
| 7~10 | 数分間で意識不明となり、チアノ―ゼが起こり死亡 |
良好な室内環境を維持するために必要な換気量は1人当たり約30m3/h以上確保されている必要がある。
室内の二酸化炭素濃度が0.1%(1000ppm)以下であれば、必要換気量(1人当たり約30m3/h以上)が確保されていると見なすことができる。
二酸化炭素は水に溶ける。
一酸化炭素
一酸化炭素は無味無臭の窒息性のガスで、ヘモグロビンとの親和力は酸素の200倍以上
| 濃度[%] | 症状 |
|---|---|
| 0~5 | 無症状 |
| 10~20 | 前頭部が締め付けられる感じ、時には動作により軽度の呼吸困難を示すことがある |
| 20~30 | 側頭部に軽度ないし中等度の拍動性の頭痛をきたす |
| 30~40 | 激しい頭痛、回転性のめまい、悪心、嘔吐、脱力が出現し易刺激性や判断力の低下、動作時失神をきたす |
| 50~60 | 時にけいれんや無呼吸期を伴うチェ―ンスト―クス型呼吸とともに昏睡を示すことがある |
| 60~70 | 昏睡とともにけいれん、呼吸抑制をきたす、時に死亡することがある |
| 70~80 | 呼吸中枢の抑制により死亡する |
- 一酸化炭素は空気より若干軽いので床近くに滞留することはない。
- 不完全燃焼より発生する。
- 一酸化炭素は火を着けてやれば空気中で青い炎を上げて二酸化炭素になるが、火源がなければ常温で酸素と反応して二酸化炭素になることはない。
- 高い濃度の一酸化炭素は急性中毒を起こすが、低濃度であっても、長期曝露によって慢性中毒を起こす。
- 一酸化炭素の人体への影響は、一般に一酸化炭素濃度と曝露時間の積に関係する。
- 血液中の酸素の運搬を阻害する。
- 一酸化炭素のビル管理法の環境衛生基準は、100万分の10以下、すなわち10ppm以下である。
ただし、特別の事情がある場合20ppm以下である。
ちなみに事務所衛生基準規則では50ppm以下である(空調設備を設けている場合はビル管理法と同じ基準値)。
浮遊粉じん
空気中の粉じんのうち、相対沈降径が10μm以上のものは発じんしても直ぐに沈降するので、人の呼吸器官に吸込まれることは少ない。
従って、ビル管理法でも測定対象となるのは粒径がおおむね10μm以下の粉じんである。
5μm程度の粉じんは気道の粘液と有毛細胞運動によって排出される。したがって肺に沈着して、人体に有害な影響を及ぼす粉じんは、通常1μm以下の大きさである。
空気中に浮遊している粒子状物質を総称してエアロゾルと呼ぶ。
エアロゾルの種類には以下のようなものがあります。
| エアロゾルの種類 | 相 | 生成様式 |
|---|---|---|
| 粉じん | 固体 | 固体の粉砕、粉体の飛散 |
| ヒューム | 固体 | 固体の加熱により発生した蒸気の冷却凝縮 |
| 煙 | 固体・液体混合 | 有機物の燃焼 |
| ミスト | 液体 | 液体の分散、液体の蒸発凝縮 |
ホルムアルデヒド
- ホルムアルデヒドは、常温では可燃性の無色の気体である。水やアルコ―ル等に溶けやすい。
- 35~38%水溶液はホルマリンと呼ばれている。
- ホルムアルデヒドは還元性が強く、人間にとって毒性、刺激性が強い。発がん性が確認されている。
- 建材、洗剤、化粧品、消毒剤、防腐剤に利用されている。
- 燃焼排気ガス、たばこ煙中にも存在
- シックハウス症候群及び肺気腫の原因物質である。
- 建築基準法によって居室の種類によるホルムアルデヒド発散建築材料の面積制限と換気設備の設置が義務付けられている。
ホルムアルデヒドは新築の住宅や家具類の接着剤から発散します。
それにより、シックハウス症候群が多発しました。(1990年代)従って、ビル管理法では空気環境測定の測定項目に
新築、増築、大規模の修繕又は大規模の模様替えを完了し、その使用を開始した時点から直近の6月1日から9月30日までの間に1回実施することと定義されています。
上記ことがら丸暗記すること。
濃度の影響
| 濃度[ppm] | 影響 |
|---|---|
| 0.01 | 結膜の刺激 |
| 0.03~0.05 | 中程度の眼の刺激 |
| 0.08 | WHOの基準値 |
| 0.16~0.45 | 眼・鼻・のどの灼熱感、角膜刺激症状 |
| 0.8 | 臭気を感じる |
| 1~3 | 眼・鼻・のどの刺激、不快感 |
| 5~10 | 眼・鼻・のどの強い刺激、軽い流涙 |
| 15~20 | 咳・深呼吸困難 |
| 50以上 | 深部気道障害、肺水腫 |
窒素酸化物
窒素酸化物はNO、とNO2がある。
物質が高温で燃焼する際に、空気や物質中に含まれる窒素が空気中の酸素と反応して生成されるものが窒素酸化物であり、工場・事業場の燃焼施設やディーゼルエンジンが主な発生源である。
発生源から排出される際には大部分が一酸化窒素(NO)であり、排出後に空気中の酸素と結合して二酸化窒素(NO2となる。
従って一酸化窒素は直ぐ酸素と結合して二酸化窒素になるので大気汚染等で問題になるのは二酸化窒素の方です。 NO2の大気汚染にかかる環境規準は0.04~0.06ppm以下である。
窒素酸化物は刺激性が強く、非水溶性のため吸入すると肺の奥まで達する。
毒性が強く高濃度の場合は、目や鼻、のどを強く刺激する
窒素酸化物は独特の臭いがする。
一酸化窒素のヘモグロビン親和力は、一酸化炭素の1400倍ともいわれ、一酸化窒素ヘモグロビンを形成する。
二酸化硫黄
無色の気体。重油、軽油、石炭等で発生
硫黄を含む重油や軽油、石炭等が燃焼する際に、空気中の酸素と反応して生成される二酸化硫黄、三酸化硫黄等を総称して硫黄酸化物という。硫黄酸化物の中で、健康影響上、最も問題となるのが二酸化硫黄である。 濃度の影響
| 濃度[ppm] | 症状 |
|---|---|
| 0.1~1 | 臭気を感じる。 |
| 2~3 | 特有の刺激臭(刺激臭となり不快臭を覚える。) |
| 5~10 | 粘膜刺激作用で咳、咽頭痛、喘息(鼻やのどに刺激があり咳がでる。) |
| 20 | 目への刺激症状(目に刺激を感じ、咳がひどくなる。) |
| 400~500 | 呼吸困難、死亡 |
大気汚染に係る環境基準は1時間値の1日平均が0.04ppm以下、1時間値が0.1ppm以下であること。
二酸化硫黄は吸着性が強いので、室内濃度は外気濃度の数分の1以下である。一般に、外気の方が濃度が高いが、室内で開放型の石油スト―ブ等を使用すると、 室内の方が濃度が高くなることがある。
オゾン
オゾンは光化学オキシダントの主成分であり、独特の刺激臭を持った青い気体で 水に溶けにくく肺の奥まで侵入する。
落雷や放電でもオゾンは発生するが、人間の環境に影響する大部分のオゾンは自動車やその他燃焼過程の排気ガス中に含まれている炭化水素と窒素酸化物の光化学 反応の結果として生成される。
室内のオゾン量に重要な影響を与えそうな発生源が、高電圧を利用したコピ―機、レ―ザ―プリンタ―、コロナ放電を伴う静電式空気清浄機である。
オゾンは酸化力の強い物質で、オゾン濃度が0.3~0.5ppm程度となると肺や気道粘膜に刺激し始める。
アスベスト
アスベストは、自然界に存在する水和化したケイ酸塩鉱物の総称である。
発がん性があり、かつては使われていたが、現在は製造が禁止されている。
アスベストの繊維は極めて細く、飛散すると呼吸器系に入り、肺線維症、悪性中皮腫の原因となる。肺癌を起こす恐れがある。
クリソタイル、アモサイト、クロシドライト等の種類がある。
揮発性有機化合物(VOC)
揮発する有機化合物の総称。種類が極めて多い。
| 種類 |
|---|
| ベンゼン、パラジクロロベンゼン、トルエン、キシレン、トリクロロエチレン、エチルベンゼン 酢酸エチル、アセドアルデヒド、フタル酸ジブジル、スチレン、ジエチルアミンなど |
シックビル症候群(定義)
- そのビルの居住者の20%以上が不快感にもとづく症状の訴えを申し出る。
- それらの症状の原因は必ずしも明確ではない。
- それらの症状のほとんどは該当ビルを離れたら解除する。
定義には該当ビルを離れたら解除するとなっています。(これ覚えておこう。)
慢性的なシックビル症候群の起きやすい建築物の発生要因
- 室内の空気が循環されている。
- 屋外空気の換気量の低減。
- 気密性が高すぎる。
- 室内がテクスタイルやカ―ペット仕上げになってている。
シックビル症候群につながる危険因子
| 個人の医学的背景 | アトピ―体質、アレルギ―疾患、皮膚炎、女性の更年期 |
| 仕事の要因 | 複写機、改築、改装、職場のストレス、不安 |
| 建築物の要因 | 室外空気の供給不足、清掃の回数不足など |
化学物質過敏症
化学物質過敏症は、非常に微量の薬物や化学物質の摂取によって引き起こされる健康被害。
原因物質と考えられるのは、建築材料、家具材から発散されるホルムアルデヒド、VOCs、有機溶剤、殺虫剤が多い。
シックハウス症候群も化学物質過敏症の1つとする考え方もある。
化学物質過敏症の病状は精神神経症状が主体で多様であり、自律神経失調症と一般には診断されうる。
1996年にWHOは、環境中化学物質との因果関係は証明されておらず、臨床的に定義された疾患ではなく、認められた病態を基盤としていないという理由で、化学物質過敏症は病名として不適切であるとしている。
家で発生することをシックハウス症候群という。
音
音には、自然の音と人工的な音がある。同じ音でも、聞く人によっては、快適な音、楽音にもなり、不快な音、騒音にもなる。音の聞こえ方は、音の物理的特性である音圧レベル(dB)周波数特性(Hz)、時間的変動特性等によって異なり、これら音の大きさ、音の高さ、音色を音の感覚の3要素という。
聴力と騒音
- ヒトの聴器で聞き取ることのできる周波数帯は、約20Hzから約20kHzの約10オクターブの範囲である。
- ヒトが音として聞こえる最小の音圧レベルを、最小可聴値という。
- 聴力の正常な人では、、4000Hz付近の最小可聴値が、他の周波数の音と比べて鋭敏であり、最小の音圧レベルを示す。
- 最大可聴値とは、これ以上の音圧レベルでは、不快感や痛み等の他の感覚が生ずる閾値である。
- ヒトが音として聴こえない、約20Hz以下の音を超低周波空気振動という。
- コウモリなどが聴き分ける約20Hz以下を超える周波数の音を超音波という。
- ある騒音環境下で、対象とする特定の音以外の音を暗騒音という。
- 等ラウドネス曲線
- 音の周波数を変化させたときに等しいラウドネス(人間の聴覚による音の大きさ、騒音のうるささ)になる音圧レベルを測定し、等高線として結んだものである。
人の聴覚は周波数によって感度が異なるため、物理的に同じ音圧であっても、周波数によって感じる音の大きさが異なる。この聴感上の音の大きさをラウドネスと呼ぶ。
- 音の周波数を変化させたときに等しいラウドネス(人間の聴覚による音の大きさ、騒音のうるささ)になる音圧レベルを測定し、等高線として結んだものである。
- マスキング
- 一つの音により、他の音が遮へい(マスク)されて聞こえなくなる現象。
つまり、テレビを観ているときに、近くで掃除機などを使用されると、テレビの音が聴こえなくなることがあると思います。
このようなことをマスキングと言います。
- 一つの音により、他の音が遮へい(マスク)されて聞こえなくなる現象。
騒音とその影響
ヒトの聴力は、一般的に20前後で最も良く、加齢によって、高い周波数から次第に低い周波数域に聴力の低下が見られる。これを加齢性難聴(老人性難聴)という。
こうした聴力低下には、周辺の騒音、テレビ等の音声や音、自分の活動による騒音も含めた全ての音が関係する。
- 騒音職場に長時間にわたり働いていると難聴が起こりやすく、これを騒音性難聴(職業性難聴)という。
騒音性難聴(職業性難聴)の初期の特徴は、通常、約4kHz付近での聴力低下(C5dip)と呼ばれる。)と耳鳴り等である。 - 騒音により自律神経系が刺激され、抹消血管の収縮、血圧の上昇、胃の働きの抑制等が起こる。
- 副腎ホルモンの分泌の増加、性ホルモン分泌の変化等が起き、騒音レベルが高くなると、生理的・身体的な影響が大きくなる。
- 騒音による健康影響は、年齢や生活習慣、生活・活動環境などによる複合的な要因で変化する。
- 55dB超の夜間騒音で心臓血管系への影響を示す科学的根拠があるとしている。
- 超音波は、医療機器、工作機械、洗浄機等から発生し、強いレベルの場合には、耳鳴り、頭痛、吐き気、疲労等の身体的影響が見られる。
- 聴力低下や難聴といった聴力障害の程度は、聴力レベルにより評価される。
中度・重度の難聴になると、言語聴取に支障が起こる。 - 大きく、高い音に一時的にばく露されていると、聴力は一時的に低下する。これを一過性聴力閾値上昇(TTS)という。
一時的な聴力低下は、通常、その後の静かな環境により回復する。しかしこの状態が繰り返され、長時間にわたると聴力低下は進行・慢性化し、永久性の聴力低下となる。これを永久性聴力閾値上昇(PTS)または永久性難聴という。 - 永久性難聴の程度は、周波数や音圧レベル、一日のばく露時間、ばく露年数等により異なり、障害の程度や進行具合には個人差が大きい。
- 聴力検査では、500、1000、2000Hzの聴力レベルの平均値(3分法平均聴力レベル)と4,000Hzの聴力レベルとが、ともに30dB未満の人を聴覚正常者としている。
- 音が大き過ぎる、「やかみしい」、「うるさい」、「不快だ」、「迷惑だ」、「邪魔だ」等の心理的影響は、聴取妨害とともに住民の騒音苦情の大半をなしている。
振動に関すること
- 環境要因として問題になる振動は全身振動と局所振動に分けられる。
- 全身振動の振動源には、建設機械、道路交通、工場、鉄道等であり、地面を伝搬してきた振動が、建築物内にいる人間によって全身振動として知覚される。この場合、建築物の窓や家具等の振動に夜音として知覚され、また揺れとして視覚的に知覚される。
- 全身振動の大きさの感覚は、建築物の振動物体上にいる人の姿勢、すなわち、立位、座位、横臥位、仰臥位等によって異なる。このために全身振動は、鉛直振動と水平振動に分けて測定・評価する。
- 人は鉛直振動のほうが 水平振動より敏感に感じる
- 振動による人の感覚は、周波数によって異なる。
- 鉛直振動では4~8Hzの振動に最も感じやすい。水平振動では1~2Hzである。
- 振動の知覚は、皮膚、内臓、間接等、人の全身に散らばる知覚神経末端受容器によりなされる。全身振動の場合には、内耳の前庭器官、三半規管が加速度の知覚に関係している。
- 人間の周波数による振動感覚の違いを補正して計測した振動加速度レベルを周波数補正加速度レベルまたは振動レベルという。
- 振動レベル55dBは地震の震度段階0(無感) に相当し、振動感覚閾値という。
- 局所振動ではレイノ―症候群(白ろう病)が生ずる場合がある。
- 振動レベルの単位はdBである。
- 振動の基本的物理量とは、変化、速度、加速度、周波数などであり、振動加速度レベルには基準加速度と加速度実効値が関係する。
- 周波数は振動数ともいう。1秒間に繰り返す振動回数のことで単位はヘルツ[Hz]。
- 全身振動の大きさの感覚は、振動継続時間によっても異なる。2~60Hzでは2秒以下で、また100~200Hzでは0.8秒以下の場合に、継続時間が短くなるにつれて振動の大きさの感覚も減少し、これより長い継続時間の場合には振動の大きさの感覚は一定となる。
- 地面の振動は建築物により増幅されてから、建築物内部の柱や床を減衰して伝搬していくことが多く、屋外地面上により建築物内床面の振動レベルの方が高くなることがある。
- ヒトへの振動としては、通常、周波数範囲1~90Hzの振動が対象となる。
- 低い振動数で新幅の大きい場合には、乗り物酔い、動揺病が発生しやすい。
- 手持ち工具などの使用による振動が手腕などから伝達し、身体局所に問題となる振動が局所振動である。
光に関すること
光に関する用語と単位
| 照度(ルクス:lx) | 被照射面の明るさの度合い、単位面積当たりに入射する光束 |
| 光束(ル―メン:lm) | 人の視覚で光と感じる量のこと。 |
| 光度(カンデラ:cd) | 光の明るさの度合いのこと。光の強さ、単位立体角当たりの光束 |
| 輝度(cd/m2) | ある面の輝きの度合い。単位面積当たりの光の明るさの度合い(光度を単位面積で割る) |
水と健康
- 血液成分の多くは水分である。
- 身体の中の水分である体液は体重の50~70%(体重50kgの人の水分はおよそ30kg前後)
- 幼若であるほど体内の水分の割合は高く、一般に女性の方が体内の水分量は少ない。加齢とともに、体内の水分量は少なくなる。
- 人が必要とする水分の量は普通1日約1.5Lで、体重当たりに換算すると小児は成人の3~4倍の水分量が必要
- 通常の食事及び水分摂取の状態で、成人が1日に排泄する尿の量は1~2Lである。
- 体内で生成された老廃物の排泄のため、成人では1日に最低0.4~0.5Lの尿が必要である。
- 体内における食物の代謝過程で生成される水は通常成人で1日約0.3Lである。
体液は細胞の内部に含まれる細胞内液と、細胞の外に存在する細胞外液とに分けられる。
細胞内液は全体液の約3分の2(約40%)を占め、細胞外液は約3分の1(約20%)を占める。細胞外液の代表的なものは血液(血漿(けっしょう))であるが、そのほかに間質液、リンパ液などがある。細胞内液の組成はカリウムイオンが多く、細胞外液にはナトリウムイオンおよび塩素イオンが多い。
血液成分の多くは水分である。血液は体内に摂取・吸収された栄養素や酸素、そしてタンパク質、ホルモン、酵素、抗体、血液凝固因子等を含み、血液循環によってそれらを身体の各部位に運搬する。
水分の欠乏率と脱水症状
| 水分欠乏率「%」 | 脱水症状 |
|---|---|
| 1 | のどの渇き |
| 2 | 強い渇き、ぼんやりする、重苦しい、食欲減退、血液濃縮 |
| 4 | 動きのにぶり、皮膚の紅潮化、いらいらする、疲労及び嗜眠、感情鈍麻、吐気、感情の不安定 |
| 6 | 手、足の震え、熱性抑うつ症昏迷、頭痛、熱性こんぱい、体温上昇、脈拍、呼吸数の増加 |
| 8 | 呼吸困難、めまい、チアノ―ゼ、言語不明瞭、疲労増加、精神錯乱 |
| 10~12 | 筋けいれん、平衡機能失調、失神、舌の腫張、講妄および興奮状態、循環不全、血液濃縮及び血液の減少、腎機能不全 |
| 15~17 | 皮膚がしなびれてくる。飲込み困難、目の前が暗くなる、目がくぼむ、排尿痛、聴力損失、皮膚の感覚鈍化舌がしびれる、 |
| 18 | 皮膚のひび割れ、尿生成停止 |
| 20%以上 | 死亡 |
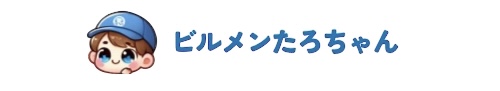

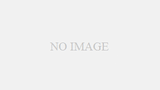
コメント