生体機能と深部体温の特徴
・外気温の影響を受けにくい身体内部の温度=移心温(核心温)
・深部体温に最も近い温度は皮膚温ではない(皮膚温は外気の影響を受けやすい)
・外気温の変動に影響されにくいのは深部体温(=核心温)であり、皮膚温は受けやすい
・深部体温の最低値:早朝の睡眠中
・深部体温の最高値:夕方~夜
・深部体温の変動幅:0.7~1.2℃
・女性では性周期により0.5℃程度の変動あり
・顔の皮膚温>手足の皮膚温
・平均皮膚温:各部位の皮膚温を面積で重みづけして算出
深部体温と皮膚温の温度関係(高い順)
| 部位 | 温度の高さ(高→低) |
| 直腸温 | 最も高い |
| 顔の皮膚温 | やや高い |
| 手の皮膚温 | 中程度 |
| 足の皮膚温 | 最も低い |
体温調節の種類
| 種類 | 内容・例 |
| 行動性体温調節 | 意識的に行う:・服を着る/脱ぐ・冷暖房・扇風機を使う |
| 自律性体温調節 | 無意識に起こる:・発汗・ふるえ |
放熱・産熱・代謝
・常温で安静時の人体からの放熱:対流が最多
・気温が35℃以上 → 伝導・対流・放射による放熱はほぼ不可能
・産熱機能:基礎代謝の増進など
・放熱機能:呼吸、血流、皮下組織による断熱など
基礎代謝と安静・睡眠時の代謝
| 種類 | 説明 |
| 基礎代謝 | 早朝・空腹・安静・起床時の代謝 |
| 安静時代謝量 | 基礎代謝の約20%増し |
| 睡眠時代謝量 | 基礎代謝の約95%程度 |
| 季節変化 | 冬は高く、夏は低い |
| 性差 | 男性>女性例:30代 男性1500kcal/女性1150kcal程度 |
恒常性(ホメオスタシス)と体温調節
・恒常性(ホメオスタシス)=内部環境を一定に保とうとする性質
・体温調節は恒常性機能の代表例
・ストレスの原因となる刺激→ストレッサー
・フィードバック機構により体温・代謝等を調節
・外部刺激→受容器→中枢→効果器→反応の流れ
Hardy-DuBoisの7点法(平均皮膚温)
・平均皮膚温 = 各部位を面積で重み付け
・最も重みが大きい部位:腹部
汗腺の種類と機能の違い
| 汗腺の種類 | 特徴・分泌内容 |
| エクリン腺 | 全身に分布、主に体温調節のための発汗(さらっとした汗) |
| アポクリン腺 | 脇・陰部などに分布、緊張・刺激で発汗、においを伴う(体臭の原因) |
・暑いときの体温調節の汗はエクリン腺から
・「暑い時にアポクリン腺が働く」という記述は誤り!(ひっかけ注意)
民族差
・南方民族は能動汗腺数が少ない(乾燥・高温環境に適応)
・発汗反応の強さや皮膚温の変化には民族差がある
・北方民族のほうが皮下脂肪が厚く寒冷に強い傾向
加齢とエネルギー・体温調節
・加齢とともに以下が低下
- 摂取エネルギー量
- 代謝予備力(=エネルギーを蓄える能力)
- 発汗量・血流反応などの体温調節能
・高齢者は寒冷・熱中症に対する耐性が低い(要注意)
正誤対策
| 問題文 | 正誤 |
| 暑いときの汗はアポクリン腺から分泌される | ×誤りは(エクリン腺) |
| 南方の民族は能動汗腺数が多い | ×誤り(少ない) |
| 加齢により代謝予備力は向上する | ×誤り(低下する) |
| エクリン腺は体温調節に関与する | ○ |
呼吸・血流による放熱機構(自律性体温調節)
・呼吸:呼気で熱を放出(特に寒冷時に重要)
・皮膚血流:血管拡張により体表へ熱を運び、放出
・皮下脂肪:熱の断熱材(=放熱を防ぐ)として働く
・汗の蒸発:エクリン腺からの汗が蒸発することで気化熱による放熱
・寒冷時:血管収縮→熱を体内に保持(放熱抑制)
・暑熱時:血管拡張→熱を体外に放出(放熱促進)
寒冷順化と暑熱順化の違い
| 項目 | 寒冷順化 | 暑熱順化 |
| 発汗量 | 変化なし or 減少傾向 | 増加(大量発汗に慣れる) |
| 発汗開始温度 | 高くなる(遅れる) | 低くなる(早めに発汗開始) |
| 皮膚血流反応 | 強化される | やや変化 |
| 末梢血流 | 減少(熱保持) | 増加(放熱促進) |
| エクリン腺の機能 | ほぼ影響なし | 機能向上(塩分再吸収能UP) |
| 順化期間 | 数週間~1ヶ月 | 1週間程度(早い) |
| その他 | しもやけ・凍傷の予防効果あり | 熱中症リスクの軽減 |
正誤対策
| 問題文 | 正誤 |
| 暑熱順化では発汗量が減少する | ✕ 誤り(発汗量は増加) |
| 寒冷順化では発汗量が増加する | ✕ 誤り(ほぼ変化しない) |
| 暑熱順化により、発汗開始温度は低下する | ○ 正しい |
| 寒冷順化では末梢血流が増加する | ✕ 誤り(減少し、熱を体内に保持) |
補足:順化と適応の違い
・順化(acclimatization):生理的な環境への慣れ(数日~数週間)
・適応(adaptation):進化レベルでの長期的変化(世代を超える)
温熱環境要素(6要素)
| 区分 | 要素 |
| 環境側の4要素 | 気温・湿度・風速・熱放射 |
| 人体側の2要素 | 代謝量・着衣量 |
・快適性に影響するその他の要因:季節・性別・年齢・活動強度など
・着衣の保温性は**clo値(クロ)**で表される
・平均皮膚温が33~34°Cのとき温熱的中性感を得やすい
温熱環境に関する主な指標
| 指標名 | 特徴・構成要素 |
| WBGT(暑さ指数) | 湿球温度・黒球温度・気温(Ta)から算出→屋内外での暑熱ストレス評価に使用 |
| 黒球温度(グローブ温度) | 鋼製黒球の中心温度を測定→放射・対流の影響評価 |
| 有効温度 | 気温+湿度+風速の3要素 |
| 新有効温度(ET) | 有効温度に放射熱を加えた4要素 |
| 標準新有効温度(SET) | ETに代謝量・着衣量を加えた6要素 |
| 不快指数(DI) | 気温と湿度から算出。暑さを数値化 |
| PMV(予測平均温冷感申告) | 温冷感を**−3~+3**で数値化する主観的評価指標 |
快適温度と温熱的快適感
・快適温度は季節・性別・年齢によって変化
・夏の快適温度は冬より2~3°C低い
・女性の快適温度は男性より1~2°C高い
・快適感は核心温に影響される、温冷感は主観による
熱中症の分類と症状
| 重症度 | 名称 | 主な症状・特徴 |
| 軽症 | 熱失神 | 血圧低下、めまい、失神(末梢血管の拡張) |
| 中等症 | 熱けいれん | 低ナトリウム血症による筋けいれん |
| 中等症 | 熱疲労 | 脱水・塩分不足 → 倦怠感・頭痛・脱力感 |
| 重症 | 熱射病 | 中枢神経障害、意識障害、体温上昇(40℃以上) ※日射病=太陽光由来の熱射病 |
低体温症と冷房障害
・低体温症:体温(直腸温)が35℃以下になる状態
・診断は直腸温測定で行う
・気温13~16℃でも天候等で発症リスクあり
・冷房障害:短時間の急激な温度差で自律神経失調を起こす
→ 女性に多い/複数症状からなる症候群
冷房障害対策
・室温と外気温の差は10°C以内
・室温を20°C以下にしない
・風速を下げる、風に直接当たらないようにする
・軽い運動、入浴、マッサージなどが効果的
高齢者の温熱特性
| 特性 | 内容 |
| 体温調節 | 若年者より低体温症になりやすい |
| 血圧反応 | 寒冷による血圧上昇が顕著 |
| 感覚 | 冷点・痛点は少なくなる(※多くなるは誤り) |
| 聴力 | 会話域より低音域の聴力が低下しやすい |
| 照明 | 間接照明・局所照明が有効/全体照度は抑えめに |
| 視認性 | 白×黄、黒×青の標識は見にくい |
| 老眼 | 一般に50歳代から始まる |
熱産生(産熱)
・熱産生は、食物の代謝によるエネルギーに由来する
・低温環境でのふるえは、筋収縮により熱産生を増加させる
・高温環境下では、熱産生量は低下する(※誤答に注意!)
→血流量が増えて体温が上昇するが、熱産生は抑制傾向
熱放散の4つのメカニズムと特徴
| 種類 | 内容・特徴 |
| 対流 | 空気や水など流体の流れによる熱移動(風や動きで促進) |
| 放射 | 電磁波として熱が放出される(物体間に接触不要) |
| 伝導 | 体が冷たい物体に直接触れることで熱が移動 |
| 蒸発 | 汗などが気化する際に潜熱を奪う(主に発汗) |
・熱放散が熱産生を上回ると、体温は低下する
・皮膚からの不感蒸泄(無意識の蒸発)でも熱が放散されている
・発汗 → 蒸発 → 放熱
正誤対策
| 記述 | 正誤 |
| 放射は流体の流れによる熱移動である | ✕ 誤り(→電磁波) |
| 蒸発による放熱は、蒸発面から凝縮熱を奪う | ✕ 誤り(→気化熱を奪う) |
| 呼吸による放熱は、呼吸量に反比例する | ✕ 誤り(→比例) |
| 熱放散>熱産生 → 体温が上昇する | ✕ 誤り(→低下する) |
| 皮膚が冷たい床面に接触 → 放射により放熱 | ✕ 誤り(→伝導) |
代謝
・基礎代謝:早朝、空腹、安静時、横になっている状態の代謝量
・安静時代謝量は、基礎代謝の約10~20%増し
・小児>大人(体表面積当たりの代謝量)
・男性>女性(平均代謝量:男1500kcal、女1150kcal程度)
・低温環境では代謝量は増加する(※「減少」は誤り)
■ 温熱環境指標
| 指標名 | 内容・特徴 |
| 黒球温度(グローブ温度) | 黒く塗った金属球の中心温度を測定。熱放射+対流の影響を受ける。 |
| WBGT(湿球黒球温度) | 屋内外の暑熱作業時の熱ストレス評価に使用。熱中症予防の指標。 |
| 有効温度(ET) | 気温・湿度・風速の3要素で構成。主観的な体感温度に近い。 |
| 修正有効温度(CET) | 有効温度に**修正(湿度補正)**を加えたもの。 |
| 新有効温度(ET*) | 上記3要素に放射熱を加えた4要素による体感温度指標。 |
| 標準新有効温度(SET) | ETに代謝量+着衣量を加えた6要素の統合指標。快適さの比較可能。 |
| 不快指数(DI) | **気温+湿度(または湿球温度)**で算出される不快さの指標。 |
| PMV(予測平均温冷感申告) | 気温・湿度・風速・放射熱・代謝量・着衣量の6要素を用いて温冷感を数値化。 |
■ WBGTの算出式(暑さ指数)
| 条件 | 式 | 説明 |
| 屋内/屋外(太陽照射なし) | WBGT = 0.7Tw + 0.3Tg | 湿球温度+黒球温度 |
| 屋外(太陽照射あり) | WBGT = 0.7Tw + 0.2Tg + 0.1Ta | 湿球温度+黒球温度+気温 |
■ 快適温度の基本と傾向
| 項目 | 内容・ポイント |
| 夏の快適温度 | 冬に比べて2~3℃低い |
| 快適感の特徴 | 核心温の影響を受ける |
| 冷房時の体調不良訴え | 暖房時より少ない |
| 冷暖房の室温差 | 大きすぎると健康リスク(例:脳卒中) |
| 男女の快適温度差 | 女性の方が1~2℃高めを好む |
| 床暖房の影響 | 上下の温度差が大きくなる |
■ 地下空間の特徴
| 特徴項目 | 内容・メリット/注意点 |
| 温度変化 | 年間通じて一定の温度が得られやすい |
| 湿度 | 比較的低く、結露やカビの発生が少ない |
| 音環境 | 外部騒音の影響が少なく、静かさを保てる |
| 地震時の揺れ | 地上階より大きくなる場合あり |
■ 高温度・低温度・湿度の影響
| 項目 | 状況・影響内容 |
| 高湿度 | ・静電気が発生しやすい・カビ・ダニが繁殖しやすい |
| 低湿度 | ・汗の蒸発が妨げられる・皮膚や喉の乾燥、粉塵の浮遊しやすさ |
| 高温度 | ・風邪など呼吸器疾患にかかりやすくなる |
| 低温度 | ・ほこりが舞いやすい |
| 湿度と喘息予防 | ・気管支喘息の憎悪予防には湿度を下げることが有効 |
| 高湿度と建材 | ・塗装の剥離が起こりやすい |
■ 日本産業衛生学会「許容濃度の勧告」
| 項目 | 内容・ポイント |
| 勧告の目的 | 労働者の化学物質による健康障害を予防するため |
| 許容濃度の定義 | 安全と危険の境界を示すもの |
| 根拠 | 動物・人の実験研究等による科学的知見に基づいて決定 |
| 健康影響との関係 | 許容濃度以下では健康障害が起きないとされている |
| 見直し | 新たな科学的根拠により見直されることがある |
| 労働強度への配慮 | 労働が激しい作業にも対応できる基準を含む |
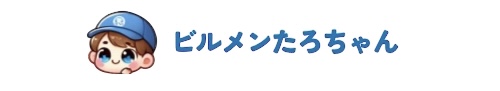

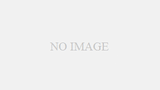
コメント