◎空気環境の調整:頻出・過去出題された単位(※は頻出)
| 用語 | 正しい単位 | 注意点・誤表記例 |
| ※熱伝導率 | W/(m・K) | W/(m²・K)と誤表記されることあり |
| ※音の強さ | W/m² | N/m²などと誤表記されることあり |
| ※輝度 | cd/m² | Im/m²(誤) |
| ※熱伝導抵抗 | m²・K/W | m・K/Wと混同注意 |
| ※音圧 | Pa | dBは音圧レベル |
| ※光度 | cd | カンデラ |
| 貫流熱流量 | W/m² | |
| ※吸音力 | m² | |
| ※色温度 | K(ケルビン) | |
| 熱貫流率 | W/(m²・K) | |
| 透過損失 | dB | |
| 光束(光東) | lm(ルーメン) | Im(誤) |
| 熱量 | J(ジュール) | |
| 照度 | lx(ルクス) | |
| ※比熱 | kJ/(kg・K) | K/(kg・K)と誤表記されることあり |
| ※振動加速度 | m/s² | m/s(誤) |
| 立体角 | sr(ステラジアン) | rad(誤) |
| ※比エンタルピー | kJ/kg(DA) | W/kg(DA)と誤表記あり |
| 振動加速度レベル | dB | |
| 水蒸気分圧 | kPa | |
| 比容積 | m³/kg(DA) | mi/kg(DA)(誤) |
◎用語
| 略語 | 正式名称 | 内容 |
| LCC | ライフサイクルコスト | 設備・建築物の生涯費用 |
| HID | 高輝度放電ランプ | ※発光ダイオード(LED)ではないので注意 |
| BRI | ビル関連病 | Sick Building Syndromeのこと |
| CFU | 集落形成単位 | 空気中の微生物数などの指標 |
| MRT | 平均放射温度 | 室内放射温度環境の快適性指標 |
◎熱放射
・熱放射とは:物体の表面間を電磁波によって伝わる熱移動のこと
・温度が0°Cの固体表面からも、熱放射は発生する(※誤:放射しない)
・放射熱流は、絶対温度(K)の4乗に比例
・常温物体の熱放射:波長10μm付近の赤外線(長波長)
・同温度物体では「放射率=吸収率」
・日射吸収率は物体の色に依存(白:低い、黒:高い)
・太陽放射:**0.38~0.78μm(可視光)**の電磁波成分が多い
【長波長放射率の代表比較表】
| 材料・表面 | 長波長放射率の特徴 |
| アルミ箔(光沢) | 約0.1(非常に低い) |
| 酸化した亜鉛鉄板 | 吸収率高い/放射率は低め |
| 白色ペイント | アルミ箔より放射率は大きい |
| アスファルト | 約0.9(高い) |
◎熱伝導・熱伝達・熱貫流
【用語と定義】
| 用語 | 単位 | 意味・補足 |
| 熱伝導率 | W/(m・K) | 材料自体がどれだけ熱を通すか |
| 熱伝達率 | W/(m²・K) | 固体と流体間での熱の伝わりやすさ |
| 熱貫流率 | W/(m²・K) | 複数層(材料+空気層)の総合的な熱の伝わりやすさ |
| 熱伝導抵抗 | m²・K/W | 材料厚さ ÷ 熱伝導率 |
【ポイントまとめ】
・熱伝導率が大きい=熱が伝わりやすい(アルミなど金属)
・同じ材料でも温度が高いほど、熱伝導率は大きくなる
・断熱材(グラスウール等)は空気の流れを阻害→熱伝導率が低い
・中空層の熱抵抗は2~5cmまでは厚さに比例、それ以上はほぼ一定
・熱伝達率は風速・表面粗さに比例(風が強い→伝わりやすい)
・外気側の熱伝達率 > 室内側
◎湿り空気・空気線図関連
・絶対湿度:乾燥空気1kg中に含まれる水蒸気の質量
・相対湿度:水蒸気分圧 / 飽和水蒸気圧 × 100(%)
・露点温度:空気が飽和して結露が始まる温度
・比エンタルピー:湿り空気1kg(乾燥空気あたり)がもつエネルギー
・比容積:1kg(乾燥空気あたり)の体積
・飽和度:実際の絶対湿度 / 飽和絶対湿度 × 100(%)
・顕熱比:全熱に対する顕熱の割合
・熱水分比:エンタルピー変化 / 絶対湿度変化
【覚えておきたい現象】
・加熱 → 相対湿度↓ /比エンタルピー↑ /比容積↑
・冷却 → 相対湿度↑ /露点に達すると凝結・結露
・絶対湿度一定で温度上昇 → 相対湿度は低下
・絶対湿度増加 → 露点温度上昇
◎結露
【表面結露】
| 条件 | 備考 |
| 絶対湿度が高い | 結露しやすい |
| 窓にカーテンを使用 | 空気の流動が妨げられ悪化 |
| 単板ガラス窓 | 結露しやすい |
| 複層ガラス(断熱性高) | 結露しにくい |
| 気密性が高く、換気が少ない | 結露しやすい(※問題文の逆に注意) |
| 家具の裏や収納の陰 | 温度が上がりにくく、結露しやすい |
| 冬季の外壁出隅(室内側) | 表面結露が発生しやすい |
【内部結露】
| 防止対策 | 解説 |
| 防湿層は断熱材の室内側に設ける | 暖房時に水蒸気分圧の高い側に防湿層を置く |
| 壁体の室外側に防湿層を置くとNG | 結露が発生しやすくなる |
| 内断熱構造にすると、内部結露しにくい | 外断熱より気密性確保しやすく、管理しやすい |
◎壁体内の温度分布図の読み方(断熱・熱伝導率)
| ポイント | 解説 |
| 傾きが急な直線 | 断熱材(熱伝導率が小さい) |
| 傾きが緩やか | 構造体など(熱伝導率が大きい) |
| 熱流量 | どの層でも同じ値 |
| 熱伝達率 | 屋外側>屋内側 |
| 防湿層の位置 | 断熱材の室内側 |
◎熱橋(ヒートブリッジ)と結露
・断熱材の途切れた部分(間柱、アルミサッシ)で熱橋が生じる
・熱橋部分は温度が低く、局所的に飽和水蒸気圧が低下 → 結露発生
・外気と接する部分の室内側で表面結露が発生しやすい
◎湿り空気に関する用語と関係性
| 用語 | 単位 | 定義・説明 |
| 絶対湿度 | kg/kg(DA) | 乾燥空気1kgに含まれる水蒸気の質量 |
| 相対湿度 | % | 水蒸気分圧 / 飽和水蒸気圧 × 100 |
| 水蒸気分圧 | Pa | 空気中の水蒸気の占める圧力 |
| 露点温度 | °C | 湿り空気を冷却したとき飽和に達する温度 |
| 比エンタルピー | kJ/kg(DA) | 乾燥空気+水蒸気のエネルギー量合計 |
| 比容積 | m³/kg(DA) | 湿り空気1kg(乾き空気)の体積 |
【よくある誤答注意ポイント】
・気密性が高い建物は結露しにくい → × 結露しやすい
・冬季は家具裏は温度が上がりやすい → × 上がりにくい → 結露しやすい
・防湿層は室外側がよい → × 室内側が正解
・カーテンは結露対策になる → × 空気の流れが阻害されて逆効果
◎加湿・除湿の状態点の動き(湿り空気線図)
【動きの基本パターン】
| 処理方法 | 状態変化 | 線図上の動き |
| 温水加湿 | 温度上昇 + 絶対湿度上昇 | 右上がりの矢印 |
| 気化加湿 | わずかに温度低下 + 絶対湿度上昇 | やや右下がりの矢印 |
| パン型加湿 | 水が蒸発して加湿 →気化加湿と類似 | やや右下がりの矢印 |
| 冷却除湿 | 温度低下 + 絶対湿度低下(露点以下で凝結) | 左下がりの矢印 |
| 吸収除湿 | 絶対湿度低下(温度ほぼ一定) | 水平方向に左 |
| 加熱(乾燥) | 温度上昇(湿度低下) | 右方向(絶対湿度は変わらない) |
ポイント
・湿り空気線図での矢印の向き=処理の方向性
・矢印の角度・方向を頭に入れておけば、状態変化問題は解ける!
◎空調の状態点の流れ(空気線図でのサイクル)
【状態点の記号】
| 記号 | 説明 | 備考 |
| a | 外気 | 冷房時:高温多湿、暖房時:低温低湿 |
| e | 室内 | 基準点 |
| b | 混合空気 | a(外気)とe(室内)の混合点 |
| c | 冷却・加熱後の空気 | 処理空気(加湿・除湿・加熱などの後) |
| d | 吹出口 | 室内に供給する空気 |
【空気線図上での流れ】
1. a + e の直線上に b(混合点)
2. b → c:冷却 or 加熱
3. c → d:加湿 or 除湿
4. d → e:送風後に室内へ戻る
◎エアロゾル粒子サイズと影響
【代表的な粒径比較表(単位:μm)】
| 粒子種別 | 粒径(μm)範囲 |
| ウイルス | 約0.003~0.1 |
| タバコ煙 | 約0.01~0.5 |
| バクテリア(細菌) | 約0.3~3 |
| 真菌・ダニアレルゲン | 約1~20 |
| 花粉・胞子 | 約10~100 |
| 霧雨・噴霧粒子 | 約20~500 |
【粒子の沈着と再飛散】
・小粒子ほど壁面に沈着しやすい(等濃度の場合)
・ストークス領域では、壁面に一度沈着した粒子は再飛散しにくい
・付着力は、ファンデルワールス力・静電気力・表面張力による
◎空気の圧力損失とベルヌーイの定理
【流体の圧力関係】
| 圧力名 | 内容 |
| 静圧(P) | 空気の圧縮による圧力、ダクト壁面にかかる力 |
| 動圧(½ρV²) | 空気の運動による圧力(流速に比例) |
| 全圧 | 静圧 + 動圧 |
【試験対策例】
・流速5.0m/s → 動圧 ≒ 10Pa
・全圧40Pa、動圧38Pa → 静圧は2Pa
・ダクトの圧力損失は風速や直径に比例
・ベルヌーイの式:
½ρv² + P + ρgh = 一定(高さや圧力、流速に関する保存則)
◎ベルヌーイの定理・連続の式
【ベルヌーイの定理】
エネルギー保存の法則を流体に適用:
12ρv2+P+ρgh=一定\frac{1}{2}ρv^2 + P + ρgh = 一定
| 項目 | 意味 |
| ρ | 流体の密度 |
| v | 流速 |
| P | 静圧(圧力) |
| g | 重力加速度 |
| h | 位置(高さ) |
→ 運動エネルギー + 圧力エネルギー + 位置エネルギー = 一定
【連続の式(質量保存の法則)】
ρAv=一定ρAv = 一定
| 項目 | 意味 |
| A | 流体が通る断面積 |
| v | 流速 |
| ρ | 流体の密度 |
| → | 同じ流路では「断面積×流速」は一定 |
◎ダクトと圧力損失の関係
| 内容 | 備考 |
| 圧力損失はダクトの長さに比例 | 長いダクトほど損失が大きい |
| 圧力損失はダクト直径に反比例 | 細いほど損失が大きい |
| 圧力損失は風速の2乗に比例 | 動圧と同じ |
| 形状変化による損失は形状抵抗係数に比例 | 曲がり・分岐など |
◎レイノルズ数(Re)と流れの種類
Re=ρvLμRe = \frac{ρvL}{μ}
または、慣性力 / 粘性力
| Reの値範囲 | 流れの種類 |
| Re ≦ 2000 | 層流 |
| 2000 < Re < 4000 | 遷移領域 |
| Re ≧ 4000 | 乱流 |
→ Reが大きい=流れが乱れやすい
◎自然換気と風・温度差
【A)風力による換気】
| 式 | 意味 |
| 換気力:P = ½ρv²(C1 − C2) | 風速²、密度、風圧係数の差に比例 |
| 換気量:Q = aA√(2/p × P) | 有効開口面積と圧力差の√に比例 |
【B)温度差による換気】
| 項目 | 内容 |
| 換気力 | 温度差・密度差・高さ差に比例 |
| 換気量 | 上記の換気力の平方根に比例 |
| 開口の配置 | 給気口:下/排気口:上が理想 |
◎自由噴流と気流制御(空気環境制御)
| 用語 | 説明・特徴 |
| 自由噴流 | 吹出口から離れると速度が距離の2乗に反比例 |
| 到達距離 | 中心軸速度が一定値まで低下する距離 |
| 天井面沿いの噴流 | 自由噴流より到達距離は長くなる |
| コールドドラフト | 冷たい壁面近くで下降する冷気流 |
| 吹出し影響 | 遠方まで影響 |
| 吸込影響 | 吹込口付近のみ |
| ドラフト | 不快な局所的気流(風速、温度変動の影響) |
◎自然換気と機械換気の違い
| 種別 | 特徴・使いどころ |
| 自然換気 | 天井が高い建物/風力・温度差を利用/安価 |
| 機械換気 | 安定した換気/病院や厨房など制御が必要な空間に適用 |
◎換気の目的・必要換気量
| 項目 | 内容 |
| 換気の目的 | ・室内空気と新鮮空気の入れ替え・汚染物質の除去 |
| 必要換気量 | ・ある汚染物質の室内濃度を基準値に保つために必要な量・CO₂を基準に計算することが多い |
| 換気量 | 単位時間あたりに取り込む外気(新鮮空気)の量 |
| 換気回数(回/h) | 換気量 ÷ 室容積(1時間あたりに室内空気が入れ替わる回数) |
| 空気交換効率 | 室内の空気がどれだけ効率よく新鮮空気と入れ替わるかの指標 |
◎必要換気に関する規定・基準
・住宅等では0.5回/h以上の換気回数(シックハウス対策)
・開放型燃焼器具の必要換気量:理論廃ガスの40倍
・理論廃ガス量:燃料が完全燃焼したときのガス量
・電気室では、温度管理のために必要換気量を算出
◎換気方式の種類と特徴
| 名称 | 給気方式 | 排気方式 | 室圧 | 主な適用例 |
| 第1種換気 | 機械給気 | 機械排気 | 正圧/負圧 | オフィス、大規模施設 |
| 第2種換気 | 機械給気 | 自然排気 | 正圧 | 手術室、クリーンルーム(外気流入防止) |
| 第3種換気 | 自然給気 | 機械排気 | 負圧 | トイレ、感染症病室など |
| ハイブリッド換気 | 自然+機械 | 自然+機械 | 中間的 | エコ住宅、環境配慮型建築物 |
◎その他の換気方式
| 種類 | 説明 |
| 置換換気 | 床面からやや低温の清浄空気を供給、上部から排気 |
| 局所換気 | 汚染物質の発生源付近のみを対象に換気する方法 |
| 混合換気 | 清浄空気と室内空気を混合・希釈しながら排気 |
| 一方向換気 | 空気をピストンのように一方向に流す方式 |
| ナイトパージ | 夏季夜間に冷気を取り入れ、熱を蓄えた建物を冷却 |
◎空気汚染物質と発生源
| 汚染物質 | 発生源例 |
| CO(一酸化炭素) | 燃焼器具、車の排気(駐車場) |
| CO₂(二酸化炭素) | 人の呼吸、燃焼器具 |
| SO₂(二酸化硫黄) | 石炭・重油などの燃焼排気(無色・無臭) |
| NOx(窒素酸化物) | 自動車排気、燃焼機器 |
◎浮遊粒子とその挙動
| 用語 | 内容 |
| 粒子の抵抗 | 相対速度²に比例、粒子体積に比例 |
| 抵抗係数 | レイノルズ数により変化、ストークス域では一定 |
| 電気移動度 | 粒子の移動速度 ÷ 電界強度 |
| 拡散係数(球形粒子) | 粒径に比例 |
| 終末沈降速度 | 粒径²に比例 |
◎試験対策ポイントまとめ
・「換気回数」は窓を開ける回数ではない!
・CO₂や水蒸気量、温熱条件、汚染物質から必要換気量を計算する
・燃焼器具のある部屋では、空気の流入・排出バランスに注意
・第2種換気は正圧(外から汚染空気を入れない)→手術室向け
・第3種換気は負圧(汚染空気を外へ出す)→トイレや感染病室向け
◎熱負荷の分類と種類
【1】負荷分類と熱種別
| 負荷名 | 顕熱 / 潜熱 |
| 外壁・屋根などの構造体負荷 | 顕熱 |
| 接地床・設置壁 | 顕熱 |
| ガラス面:貫流熱 | 顕熱 |
| ガラス面:透過日射 | 顕熱 |
| 室内発生(照明など) | 顕熱 |
| 人体負荷 | 顕熱+潜熱 |
| その他内部発熱 | 顕熱+潜熱 |
| 隙間風負荷 | 顕熱+潜熱 |
| 透湿熱 | 潜熱 |
| 外気負荷 | 顕熱+潜熱 |
| 再熱負荷・送風機負荷 | 顕熱 |
| ダクト・配管・ポンプ負荷 | 顕熱 |
| 蓄熱装置 | 顕熱 |
【2】試験で問われやすいポイント
| 知識ポイント | 覚えるべき内容 |
| 潜熱を含む負荷 | 人体、外気、隙間風、透湿熱、内部発熱 |
| 潜熱のみの負荷 | 透湿熱 |
| 冷房時に無視される負荷 | 接地床、蓄熱装置 |
| 暖房時に無視される負荷 | 送風機、ポンプ |
| 室内負荷に含まれないもの | 外気、送風機、ダクトなど |
| 空調機負荷に含まれないもの | ポンプ、配管、蓄熱装置 |
◎空気調和方式(方式名・特徴)
| 方式名 | 特徴・備考 |
| 一定風量単一ダクト方式 | 給気量一定/給気温度で負荷調整/シンプルで制御性◎ |
| 変風量単一ダクト方式 | 風量可変で省エネ/VAV制御 |
| 二重ダクト方式 | 冷暖空気を混合/エネルギーロス大/ゾーン対応可能 |
| マルチゾーンユニット方式 | 複数ゾーン対応/機械室スペース大 |
| ターミナルエアハンドリング方式 | 個別空間制御可能/室内機ごとの処理が可能 |
| ハイブリッド換気方式 | 自然換気+機械換気/省エネ性と安定性を両立 |
◎熱源方式の分類と特徴
| 方式 | 特徴・備考 |
| 電動冷凍機+ボイラ方式 | 夏冬の電力差大/電気代高め |
| 吸収冷凍機+蒸気ボイラ | 病院・ホテル向け/排熱利用しやすい |
| 直焚吸収冷温水発生機 | 冷水・温水を1台で生成 |
| 電動ヒートポンプ方式 | 夏冬の電力差小/省エネ・低GWP対応 |
| ガスエンジンヒートポンプ | 排熱再利用/寒冷地暖房向き |
| コージェネレーション方式 | 発電+排熱利用/高効率 |
| 地域冷暖房 | 集中熱源供給/熱供給事業法21GJ/h以上→登録必要 |
◎冷凍機の種類と特徴
【1】冷凍サイクルと形式比較
| 種別 | 冷媒 | 圧縮手段 | 特徴 |
| 蒸気圧縮式 | フロン等 | 圧縮機でガス圧縮 | 高効率・GWP対策必要 |
| 吸収式 | 水(冷媒) | 吸収・再生でループ | 真空運転/電気消費少・排熱対応 |
| 吸着式 | 水+固体吸着剤 | 吸着材:シリカゲル等 | 成績係数低/コンパクト性に劣る |
【2】圧縮機の種類
| 圧縮機の型式 | 特徴 |
| スクロール | 静音・小型/家庭用に多い |
| スクリュー | 中大容量/工場・施設向け |
| 遠心 | 高速・大容量対応/冷凍機の主力機種 |
| 往復動 | ピストン往復/古い機種や特殊用途で使用 |
◎冷却塔の種類と特徴
| 分類 | 特徴 |
| 開放型 | 蒸発冷却式/小型化可能だが水質管理必須 |
| 密閉型 | 間接冷却/清浄用途・冷却水が汚れにくい |
| 共通注意点 | レジオネラ菌対策必要/水処理・ブロー必須 |
◎ボイラの分類と注意点
| 名称 | 主な用途 | 備考 |
| 炉筒煙管式 | 病院・ホテル/中規模 | 横型構造/洗浄・整備しやすい |
| 水管ボイラ | 高圧・大容量用途 | スケール対策・分解整備難 |
| 真空式温水発生器 | 給湯・暖房(圧力低) | 資格不要/セクション式あり |
◎空気調和機の種類と構成要素
【1】エアハンドリングユニット(AHU)
| 構成機器 | 備考 |
| エアフィルタ | 空気中の粉塵を除去 |
| 冷却・加熱コイル | 冷温水や蒸気で空気を処理 |
| 加湿器 | 湿度調整(ドレンパン・エリミネータ併設) |
| 送風機 | 軸流型が多い |
| ドレンパン | 結露水回収 |
・熱源は内蔵しておらず、外部の冷温水や蒸気が必要
・大空間向けのオーダーメイド機種
・機械室設置が多いが、ターミナル型は天井内設置も可能
【2】ファンコイルユニット(FCU)
| 特徴 | 備考 |
| 冷温水+送風ファンで空気を処理 | コンパクト設置が可能(床置・天吊型) |
| ダクト併用方式で端末として利用可 | 各室で個別制御が可能 |
【3】パッケージ型空調機(PAC)
| 構成機器 | 備考 |
| 圧縮機・蒸発器・凝縮器・膨張弁 | 冷媒による直接冷暖房 |
| ヒートポンプ機能付き | 空気熱源/水熱源で分類可能 |
| セパレート型(室内外分離) | 多くはこのタイプ |
| ビル用マルチ(マルチエアコン) | 複数室内機を1台の室外機に接続/個別運転可 |
◎空気調和方式の比較
| 方式名 | 特徴・メリット | 注意点・弱点 |
| 定風量単一ダクト方式 | 給気量一定/構造が単純 | 室間負荷変動に非対応/外気導入が困難 |
| 変風量単一ダクト方式(VAV) | 給気温度一定/風量制御で省エネ対応 | 室ごとの風量変動で外気量確保に工夫が必要 |
| ターミナルAHU方式 | 小風量で各室制御/天井内設置可能 | 複数ゾーン制御で施工コスト高 |
| 置換空調方式 | 床面給気→上部排気で快適性向上 | 結露・低温風注意 |
| 放射冷暖房 | 天井パネル冷暖房/放射熱で快適性高 | 換気機能なし/冷房時の結露注意 |
◎ヒートポンプ方式の比較
| 分類 | 特徴・用途 |
| 空気熱源 | 成績係数高/コンパクト/普及多い |
| 水熱源 | 安定運転/熱交換効率良/設備大 |
| マルチユニット型 | 室内個別制御/加湿機能追加可能 |
◎低温冷風空調・床吹出・外調機併用方式
| 方式名 | 特徴 |
| 低温冷風方式 | 風量削減に有効/結露と室温低下に注意 |
| 床吹出し空調方式 | 二重床利用/下部から空気供給 |
| 外調機併用ターミナルAHU方式 | ゾーン単位の空調+外気処理機能付き |
◎冷暖房システム・設備構成の全体像
| 設備分類 | 主な構成機器・設備 |
| 熱源設備 | 冷凍機、ボイラ、冷却塔、蓄熱槽 |
| 熱搬送設備 | ポンプ、冷温水配管 |
| 空気調和機 | AHU、FCU、PAC |
| 自動制御設備 | センサ、調節器、操作器、中央監視装置 |
◎自動制御システムの構成
| 構成要素 | 役割 |
| 検出部 | 温度・湿度・風速などの検知 |
| 調節部 | 計算処理・比較判断 |
| 操作部 | 弁やモーターなどを制御 |
・電力デマンド制御:契約電力超過を避けるため、電力供給者側で制限制御を行う場合あり。
◎空気調和の自動制御と省エネポイント
| 項目 | 内容・ポイント |
| 自動制御方式の種類 | **電気式・空気式(気圧式)**の2種類 |
| サーモスタット | → 温度調整用(※湿度調節ではない → ×) |
| CO₂濃度制御 | 室内CO₂濃度により最小外気量を自動調整 → 省エネ |
| 予熱時の外気ダンパ制御 | 外気・排気ダンパ閉、還気ダンパ全開 → 熱ロス削減 |
| 冷水コイル流量制御 | 三方弁で還水調整 → 省エネルギー |
| 予冷・予熱時の外気導入 | 外気導入増で熱交換削減・省エネ |
◎ファンコイルユニット(FCU)のポイント整理
| 項目 | 内容・特徴 |
| 用途 | 小規模建物・インテリアゾーン中心 |
| 構成 | 送風機・冷温水コイル・エアフィルタ |
| 設置形式 | 床置き型・天吊り型(※床置き限定は×) |
| 配管方式 | 2管式 or 3管式 |
| 熱源との関係 | 冷温水で搬送/ヒートポンプではない |
| 加湿機能 | 一般にはなし → 加湿器は別装置 |
| 電源 | 三相200Vが多い |
| 点検性 | 分散設置 → 保守点検が繁雑になりやすい |
◎ダクト併用ファンコイル方式の特徴
| 特徴 | 備考 |
| 個別制御性 | 単一ダクト方式よりは劣る |
| 小型化 | AHUやダクトを小型化できる |
| 空気混合損失 | FCU吹出空気+ダクト吹出空気 → 混合損失発生あり |
| 分類 | 空気–冷媒方式 |
◎蓄熱システムの要点
| 項目 | 内容・ポイント |
| 基本機能 | 冷熱・温熱を貯めて使用/ピークカット対応 |
| 故障・停電時対応 | 熱源代替にはならない(×) |
| 運転効率 | 夜間の定格運転が可能 → 高効率 |
| 部分負荷対応 | 苦手(調整が難しい) |
| 耐久性 | 熱源のオン・オフ減少 → 機器寿命延長 |
| 蓄熱材 | 氷(顕熱蓄熱) |
| 水の利用 | 消火用水には使用不可(×) |
| 開放式蓄熱槽の特徴 | 搬送動力小/水質管理必要 |
◎冷却塔(クーリングタワー)の整理
【1】種類と構造
| 種類 | 特徴・ポイント |
| 開放型 | 空気と水が直接接触/水の蒸発による冷却/水質管理要 |
| 密閉型 | 散水系統と冷却水系統が分離/冷却水が汚れにくい |
| 水と空気の接触方向 | 水平型・垂直型の分類あり |
【2】管理と注意点
| 内容 | 説明 |
| 点検頻度(使用後) | 6ヶ月以内に1回以上 |
| 清掃(冷却塔・冷却水配管) | 1年以内に1回以上 |
| スライム・レジオネラ菌対策 | 薬剤投入(月1回)・強制ブロー・防食剤使用 |
| 水質管理 | 濃縮管理法(pH・導電率)で補給水量調整 |
| 補給水量 | 循環水量の約0.5% |
◎加湿装置の種類と特徴
| 種類 | 特徴・注意点 |
| 噴霧式(水頭圧・超音波) | 霧状にして放出/水中不純物が室内に放出されることがある |
| 回転式 | 加湿材を水に浸して回転・加湿 |
| 蒸気式(シーズヒータ) | 水を加熱→蒸気化して加湿 |
| 超音波式 | 振動で霧化/不純物注意 |
| 蒸気ノズル式 | 空気温度の低下なし |
| エアワッシャ式 | 気化加湿/空気温度が低下する |
| 直接蒸気スプレー式 | ノズル詰まり注意 |
| 電極式 | 保守必要 |
◎全熱交換器の特徴と分類
| 項目 | 内容 |
| 全熱交換器とは | 排気の顕熱+潜熱を回収し、外気負荷を軽減する熱交換器 |
| 主な用途 | 厨房/温水プール/省エネ重視施設 |
| 顕熱交換器との違い | 潜熱(湿度)まで回収できる(結露が生じやすい) |
| 注意点 | 中間期の運転は省エネ効果が小さく逆効果になることもある |
| 外気取入系統 | 別系統が必要(空気短絡を避けるため) |
【全熱交換器のタイプ比較】
| 種類 | 特徴 | 吸湿材 or 素材 |
| 静止型 | 給排気を透湿・伝熱性の仕切板で分離 | 吸湿性仕切材(紙系など) |
| 結露・目詰まりしやすい | ||
| 回転型 | 円筒エレメントを回転させ、交互に熱交換 | シリカゲル・イオン交換樹脂など |
| 給気に排気残留空気が混入する可能性あり(多少) | ||
| ヒートパイプ型 | 蒸発・凝縮サイクルで熱輸送/構造が単純 | 空気-空気用/熱輸送能力が高い |
◎熱交換器の種類と特徴
| 種類 | 用途・特徴 |
| U字管式 | 伝熱管がU字型でコンパクト |
| 全固定式 | 両端が固定/熱膨張に弱い |
| フローティングヘッド式 | 熱膨張に対応/清掃しやすい |
| プレート式 | 水-水熱交換用/分解・洗浄可能/汚れやすい流体は不向き |
| プレートフィン式 | 空気冷却/経済的でコンパクト |
| ブレージング型 | 一体型/寒冷地に強い/金属プレートで透湿性なし |
◎加湿装置の種類と分類(気化・蒸気・噴霧)
| 方式名 | 加湿方式 | 空気温度低下 | 不純物放出 | 特徴/注意点 |
| 気化方式 | 水を自然蒸発 | ○ | × | 結露しにくく、湿度安定 |
| 滴下式 | 加湿材に水を滴下 | ○ | × | 給水部に藻類や菌類が繁殖しやすい |
| 透湿膜式 | 膜を通して加湿 | ○ | × | 清潔・気密性高 |
| エアワッシャ式 | 水噴霧と気化 | ○ | × | 空気温度が下がる |
| 蒸気方式 | 水を蒸気化 | × | × | 高温無菌、空気温度下がらない |
| 電極式 | 電気で水を加熱 | × | × | 純水不可/保守必要 |
| パン型 | 水皿から蒸発 | ○ | × | 簡易的 |
| 超音波式 | 振動で水を霧化 | ○ | ○ | 不純物が室内に放出される恐れあり |
| 遠心式 | 遠心力で霧化 | ○ | ○ | 高湿度空間や温室に適用 |
| スプレーノズル式 | 水をノズル噴霧 | ○ | ○ | ノズル詰まり注意 |
| 蒸気ノズル式 | 蒸気で加湿 | × | × | 空気温度を下げずに加湿可能(◎) |
◎除湿(減湿)方式の分類
| 名称 | 方法・原理 |
| 冷却減湿法 | 冷却コイルで空気を露点以下に冷却し、結露させて水分除去 |
| 吸収減湿法 | **吸湿性水溶液(例:塩化カルシウム)**で水分を吸収 |
| 吸着減湿法(デシカント法) | シリカゲルやゼオライトなどの固体吸着材で除湿 |
| 圧縮減湿法 | 空気を圧縮 → 冷却 → 結露 → 乾燥空気を得る |
【覚えておきたい関連ポイント】
・回転型全熱交換器:処理風量大きいものもある(設問での混乱注意)
・エアワッシャ:加湿と冷却を同時に行う → 温度が下がる
・超音波式・噴霧式:不純物の室内放出あり → 水質要注意
・ヒートパイプ:空気–空気間の熱交換/構造が簡単で熱輸送力◎
◎吹出し口の種類と分類
【分類と特徴一覧】
| 分類 | 型名称 | 特徴・用途 |
| ふく流型 | アネモ型 | 誘引効果大/温度分布が均一 |
| パン型 | 簡易な一方向吹出し | |
| 軸流型 | 長距離送風向き/体育館など大空間 | |
| ノズル型 | 到達距離長い/誘引比小(=空気を巻き込みにくい) | |
| 線状型 | スロット型 | インテリアゾーン向き/均一温度分布が得やすい |
| ライン型 | 可動・固定あり/中央部設置多い | |
| 面状型 | 天井パネル型 | 放射冷暖房効果あり |
| 多孔パネル型 | 有孔天井全体から微風速で吹出し |
【吹出し口の補足ポイント】
・アネモスタット型はアネモ型の一種。ノズル状吹出で多層コーン構造
・アンチスマッジリング:天井汚れ防止用リング(ディフューザに装着)
・線状吹出口:誘引比大 → 良好な温度分布
・ノズル型は長距離に吹出せるが、誘引比小
◎吸込口とその性質
・吸込口は指向性なし(向きに意味なし)
・吸込みにも吹出しと同様に整流・処理が必要
・形状:グリル型が多い
◎空気浄化装置・フィルタの種類
【エアフィルタの種類と性能】
| 種類 | 特徴・注意点 |
| ろ過式 | 繊維で粉じんを捕集/最も一般的 |
| 静電式 | 荷電+吸着で微粒子も除去可/電源必要 |
| 活性炭フィルタ | ガス状汚染物質除去に有効 |
| 折込み形 | 表面積が広く、圧力損失が低減 |
| 自動更新型 | タイマーで自動巻取り可能 |
【HEPAフィルタ】
| 項目 | 内容 |
| 用途 | クリーンルーム・医療施設・空調機など |
| 特徴 | 高性能ろ過/プレフィルタ併用が一般的(単独使用×) |
| 圧力損失 | 一般フィルタより大きい(→ ×圧力損失小) |
◎室内空気質測定法
| 測定対象 | 測定法 |
| 一酸化炭素 | 検知管法 |
| 二酸化炭素 | 非分散型赤外線吸収法 |
| 浮遊真菌・微生物 | フィルタ法/培地法 |
| オゾン | 赤外線吸収法 |
| 窒素酸化物(NOx) | 化学発光法 |
| アスベスト | 紫外線吸収スペクトル法 |
| 臭気 | オルファクトメータ法 |
◎ダクト・継手・ダンパ
【ダクトの種類】
| 種類 | 特徴 |
| 亜鉛鉄板製 | 板厚0.5~1.2mm/最も一般的 |
| スパイラルダクト | はぜ構造で強度◎/円形/フレキ使用可 |
| グラスウール製 | 断熱・吸音性能あり |
| ステンレス製 | 耐食性必要な用途に使用 |
【継手の種類】
| 継手名 | 用途 |
| フレキシブル継手 | 吹出口・消音ボックスと接続/位置調整用 |
| たわみ継手 | 振動防止用/空調機とダクト間 |
| 差込継手 | 丸ダクト・スパイラルダクト |
| アングル/共板フランジ | 長方形ダクトの接続に使用 |
【ダンパの種類】
| ダンパ名 | 特徴・使用場所 |
| 風量調整ダンパ | バタフライ型・平行翼型/風量調整に使用 |
| 防火ダンパ | 防火区画貫通部に設置/ヒューズ温度:72℃~280℃ |
| 防煙ダンパ | 煙感知器連動で防煙区画に設置 |
◎送風機の種類と特性
| 分類 | 特徴・用途 |
| 遠心(多翼・後向き) | 大風量/中低圧対応/空調機用に多用 |
| プロペラ型 | 低圧/換気・冷却塔に使用 |
| 斜流型 | 軸方向+遠心力の中間タイプ/省スペースに有効 |
| 横流型 | 静音・コンパクト/エアカーテンなどに使用 |
【サージング】
・送風機が大流量で不安定運転になる現象
・対策:ダンパ開度を閉じる(抵抗を増やす)
■送風機の種類と特徴
| 種類 | 空気の流れ方向 | 特徴 |
| 遠心送風機 | 軸方向 → 径方向 | 高静圧に向く。シロッコファンなど。 |
| 軸流送風機 | 軸方向 → 軸方向 | 大風量・低静圧。プロペラファン。 |
| 斜流送風機 | 軸方向 → 斜め方向(遠心と軸流の中間) | コンパクトで中圧対応。 |
| 横流送風機 | 外周の一部 → 反対側の外周 | 薄型形状が可能。エアカーテン等に使用。 |
■送風機の分類(ファンとブロワ)
・ファン:吐出圧力が9.8 kPa以下(おおよそ)
・ブロワ:吐出圧力が9.8 kPa以上
■送風機の風量制御と特性曲線
| 制御方法 | 内容 |
| ダンパ操作 | 風量調整時に抵抗を変化。特性曲線は変わらない。 |
| インバータ操作 | モータ回転数を調整して風量制御。特性曲線も変化。 |
| 抵抗曲線 | L原点を通る二次曲線として表される。 |
■空気浄化装置(エアフィルタ)の分類と特徴
1. ろ過式フィルタ
| フィルタ種別 | 粒子径での規定 | 特徴 |
| 一般空調用フィルタ | – | パネル型、自動巻取型など |
| HEPAフィルタ | 0.3μm粒子に対する捕集率で規定 | 高性能。折込み形。圧力損失やや大きい。 |
| ULPAフィルタ | 0.15μm粒子に対する捕集率で規定 | 超高性能。圧力損失はさらに大きい。 |
・捕集原理:さえぎり、慣性衝突、拡散、静電気など
・性能指標:圧力損失、捕集率、粉じん保持容量(kg/m²)
2. 静電式フィルタ(電気集じん器)
・高圧電界で粉じんを荷電 → 集じん電極に吸着し除去
・主に排気系統にも設置されることがある
3. ガス除去用フィルタ
| 特徴 | 内容 |
| 捕集方法 | 活性炭、シリカゲル、イオン交換繊維などで吸着 |
| 圧力損失の変化 | ほとんど変化しない |
| ガス除去容量の表示 | 初期除去性能の85%に低下するまでに捕集した質量で表す |
■ポンプの種類と分類
| 分類 | ポンプ名 | 特徴・用途 |
| 容積型 | 往復ポンプ | ピストンの往復で送水 |
| 歯車ポンプ | 粘度の高い液体に用いる。流量はほぼ一定 | |
| ダイヤフラムポンプ | 弾性膜を動かして送水 | |
| ターボ型 | 渦巻きポンプ | 遠心力を利用。片吸込型・両吸込型がある |
| 斜流ポンプ | ターボ型と軸流型の中間 | |
| 渦流ポンプ | 渦流により揚水 | |
| 特殊型 | インラインポンプ | 配管途中に取り付け。省スペース |
| 多段型 | 多段渦巻きポンプ | 複数羽根車で高揚程対応 |
■ポンプ運転・設計に関する用語と注意点
・全揚程 = 実揚程 + 損失水頭
・キャビテーション防止:有効吸込みヘッド > 必要吸込みヘッド
・サージング:流量過小で不安定 → バルブを開ける
・グランドパッキン:漏水してはならない(注意)
・インバータ駆動:高調波で電動機の発熱に注意
・水撃作用対策:緩閉式逆止弁を使用
■空調配管の温度範囲と特徴
| 配管種別 | 使用温度 |
| 冷水配管 | 5~10°C |
| 冷却水配管 | 10~15°C または 20~40°C |
| 温水配管 | 40~80°C |
| 高温水配管 | 80~100°C または 100°C以上 |
| 氷蓄熱用不凍液配管 | -10~-5°C |
| 低圧蒸気配管 | 0.01~0.05MPa |
| 高圧蒸気配管 | 0.1~1MPa |
※蒸気配管には黒管使用。亜鉛メッキ管は不可
■冷温水配管方式の比較
| 方式 | 特徴 |
| ダイレクトリターン方式 | 配管が短く、水量のバランスを取りやすい |
| リバースリターン方式 | 各経路の抵抗が等しく、流量が均一 |
■測定・計測関連(温熱・湿度・風速)
| 測定機器・用語 | 内容・特徴 |
| グローブ温度計 | 気流が小さいと平均放射温度に近づく |
| サーミスタ温度計 | 金属の膨張率差で測定(実際は誤り、抵抗変化) |
| 管気抵抗式湿度計 | 感湿部の電気抵抗変化を利用 |
| アスマン通風乾湿計 | 通風のある場所向き。乾球>湿球温度 |
| アウグスト乾湿計 | 通風速度の影響を受けない |
| 熱式風速計 | 白金線などで熱損失を測定 |
| ピトー管 | 流速と圧力差を測定。ストークスの定理は誤り |
| 超音波風速計 | 超音波の到達時間の差で風速を測定 |
■浮遊粉じん・汚染物質の測定と単位
| 測定方法・対象 | 特徴・単位 |
| 光散乱式粉じん計 | 光の散乱を利用。校正係数・感度・BG値に注意 |
| ピエゾバランス粉じん計 | 圧電素子による静電沈着 |
| アスベスト | f/L(繊維数/リットル) |
| 微生物 | CFU(コロニー形成単位) |
| 臭気 | cpm(臭気強度) |
| ダニアレルゲン | ng/m³ |
| 浮遊粉じん | cpm |
| 放射能 | Bq(ベクレル) |
| NO₂(二酸化窒素) | ppb(10⁻⁹) |
| オゾン | μg/m³ |
■節電対策(空気調和設備)
・冷房設定温度を上げる
・冷水出口温度を上げる
・冷却水入口温度を上げる
・ヒートポンプに散水しても節電効果なし(×)
・熱交換器の洗浄は節電に有効
■温熱環境要素と測定機器
| 測定項目 | 測定機器・方法 | 特徴・注意点 |
| 温度 | バイメタル式温度計 | 2種金属の膨張率差を利用 |
| サーミスタ温度計 | 電気抵抗式。気流測定にも使用される | |
| 熱電対温度計 | 熱起電力を利用 | |
| 湿度 | アスマン通風乾湿計 | 通風型。乾球>湿球 |
| アウグスト乾湿計 | 通風速度に影響されない | |
| 毛髪湿度計 | 毛髪の伸縮を利用。振動に弱い | |
| 気流 | 熱線式風速計 | 白金線の熱損失量に基づく(定電圧式・定温度式) |
| 超音波風速計 | 超音波の到達時間差を利用 | |
| ピトー管 | ベルヌーイの式を使用 | |
| 放射 | グローブ温度計 | 黒球温度。15~20分かけて安定。気流が少ないとMRTに近づく |
■空気環境要素と測定法
| 測定対象 | 主な測定法 |
| 酸素 | ガルバニ電池方式、ポーラログラフ方式 |
| NOx(窒素酸化物) | ザルツマン法、化学発光法、吸光光度法、フィルタバッジ法 |
| SOx(硫黄酸化物) | 溶液導電率法、紫外線蛍光法 |
| オゾン | 紫外線吸収法、化学発光法、半導体法、検知管法 |
| 放射線 | シンチレーション検出器 |
| CO₂(二酸化炭素) | 非分散型赤外線吸収法、検知管法、ガス干渉計法 |
| CO(一酸化炭素) | 定電位電解法、検知管法 |
| 換気量 | トレーサガス減衰法 |
■汚染物質と単位(頻出)
| 汚染物質 | 単位 |
| 細菌・真菌 | CFU/m³ |
| アスベスト | f/L、f/cm³、本/L |
| ダニアレルゲン | ng/m³ |
| オゾン | ppm、μg/m³ |
| 浮遊粉じん | mg/m³、cpm |
| 臭気 | 単位なし(臭気強度) |
| 放射能 | Bq(ベクレル) |
| 放射線量 | Sv(シーベルト) |
| NO₂・SO₂など | ppb、ppm |
※1 ppm = 1000 ppb
■浮遊粉じんの測定法
| 分類 | 測定法・装置名 | 特徴・注意点 |
| 定量測定 | ローボリウムエアサンプラ法 | 重量濃度測定(mg/m³) |
| 光散乱法(デジタル粉じん計) | 光の散乱強度で測定 | |
| 圧電天秤法 | ピエゾバランス方式 | |
| フィルタ振動法 | フィルタ上の質量変化検出 | |
| 吸光光度法 | 光の吸収による測定 |
・対象:相対沈降径10μm以下の粒子(PM10)
・化学的組成は測定しない
・浮遊定法・捕集定法がある
■ホルムアルデヒドの測定法
| 測定法種別 | 方法 | 特徴 |
| 精密測定法 | アクティブ法(DNPHカートリッジ+HPLC) | 冷蔵保管必要。オゾンによる妨害あり |
| 簡易測定法 | バッシブ法(DNPH含浸チューブ等) | 長時間(8時間)必要。ポンプ吸引方式もある |
■VOC(揮発性有機化合物)測定法
| 測定法種別 | 方法 | 特徴 |
| アクティブ法 | 固相捕集+加熱脱着-GC/MS、GC/FIDなど | 精密測定。標準ガスで定期較正必要 |
| バッシブ法 | 拡散現象利用。吸引ポンプ不要 | 測定精度は劣るが簡易。定量には向かない場合もある |
| TVOC | ヘキサン~ヘキサデカン範囲のVOCの合計 | 市販モニターあり。感度はアクティブ法より劣る |
■音の基本用語と物理特性
| 用語 | 説明 |
| 波長 | 媒質が1回振動する間に音が進む距離 |
| 周波数×波長 | 音速になる(空気中:約340m/s) |
| 音速 | 気温が1℃上がると約0.6m/s増加 |
| 純音 | 1つの周波数だけの音(正弦波) |
| 拡散音場 | 音のエネルギーが空間全体に一様に分布し、あらゆる方向に伝搬 |
| 音の強さ | 単位面積・単位時間あたりの音のエネルギー(音圧の2乗に比例) |
| 音圧レベル | 音の強さをdB(デシベル)で表現。人間の感覚に合わせた対数尺度 |
■音響測定に関する用語
| 用語・概念 | 内容 |
| 暗騒音 | 対象音以外の背景音。測定時に10dB以上差がなければ影響除去が必要 |
| 吸音率 | 入射音に対して吸収される割合(0~1) |
| 透過損失 | 音の透過をどれだけ防げたか(dB)。大きいほど遮音性能が高い |
| 質量則 | 壁の質量が重いほど透過損失は大きくなる |
| コインシデンス効果 | 高音域で壁材が共鳴し透過損失が下がる現象 |
| 音源からの減衰特性 | 点音源:距離2倍で6dB減衰/線音源:3dB/面音源:ほぼ変化なし |
■遮音・衝撃音と対策
| 種別 | 特徴・対策 |
| 軽量床衝撃音 | 高周波成分が多い。床仕上げ材を柔らかくして対策 |
| 重量床衝撃音 | 低周波成分。床構造の質量・剛性増強で対応(カーペット等では効果薄) |
| Dr値(遮音等級) | 値が大きいほど遮音性能が高い |
| 等級値(衝撃音) | 値が小さいほど遮音性能が高い |
| 隔壁透過損失 | 受音室の吸音力が大きいほど性能向上 |
■空気伝搬音と固体伝搬音の違い
| 分類 | 例・説明 | 低減方法 |
| 空気伝搬音 | 空調機の隙間音、ダクト内音、窓からの道路騒音 | 壁・窓・床の遮音 |
| 固体伝搬音 | 機器振動、給排水管・ポンプ・設備からの音 | 防振装置・絶縁・振動源の制御 |
■騒音・振動の評価と単位
| 評価尺度 | 内容・特性 |
| A特性音圧レベル | 人間の聴覚感度に合わせた重み付け |
| 時間率レベル(Lx) | 観測時間内で「あるdB以上」の音が占める時間割合(例:L₆₀で60dB以上の占有時間) |
| 振動の時間変動 | 道路交通=不規則/空調=定常/建設=間欠的/風=長周期 |
| 振動周波数範囲 | 環境振動の鉛直方向は1~80Hzが対象 |
| 振動加速度実効値 | 正弦波振動では最大振幅から算出 |
■複数音源の合成・減衰例(デシベル加算)
・6台の78dB音源 → 約92dB
・83dB+89dBの合成 → 約92dB
(参考:10log₂=0.3010、10log₃=0.4771)
■音響性能の計算式(一例)
| 式 | 内容 |
| L₁ – L₂ = TL + 10log(S/A) | 音源室と受音室の音圧差。A=吸音面積、S=透過面積 |
■振動対策と効果的な設計要素
・防振溝は深く、振動源に近い方が有効
・乗り物の揺れ→水平振動の方が敏感
・振動規制(環境振動)は夜間がより厳しい
・低周波数の方が人は敏感に感じやすい
■音の基本用語と物理量
| 用語 | 意味・特徴 |
| 暗騒音 | 対象音以外の環境音の総称。測定時、対象音とのレベル差が10dB未満なら除去が必要 |
| 波長×周波数 | 音速。空気中では約340m/s(気温1℃上昇で約0.6m/s増加) |
| 吸音率 | 入射音に対する吸収音エネルギーの割合 |
| 透過率 | 入射音に対する吸収+透過エネルギーの割合 |
| 拡散音場 | 空間全体に音エネルギーが均一に分布し、あらゆる方向へ伝搬する状態 |
| 音の強さ | 単位面積・単位時間に通過する音エネルギー。音圧の2乗に比例 |
| 純音 | 単一周波数の音。瞬時音圧は正弦関数で表現 |
| 広帯域騒音 | 広い周波数領域に成分を含む騒音 |
■音の評価尺度・測定値
| 項目 | 内容 |
| 音圧レベル | 最小可聴値(2×10⁻⁵Pa)を基準とした対数尺度(dB) |
| 音響出力レベル | 音源の出力をdBで表す |
| A特性音圧レベル | 人間の感覚補正を加味した音圧レベル |
| 等価騒音レベル(Leq) | 時間的に変動する騒音の平均エネルギーレベル |
| C特性音圧レベル | 重低音成分を含む広範囲の騒音評価に使用 |
| 質量則 | 壁を重くすると遮音性能(透過損失)は大きくなる |
| オクターブ帯域 | 周波数が2倍になる幅。10倍幅ならデケード帯域 |
■衝撃音の分類と対策
| 分類 | 主成分・特徴 | 主な対策 |
| 軽量床衝撃音 | 高周波成分。硬い衝撃源が多い | カーペット・畳など柔らかい仕上げ材 |
| 重量床衝撃音 | 低周波成分。弾性影響が大きい | 床構造の質量・剛性の増加 |
■音の伝搬形式と防止策
| 分類 | 例 | 防止策 |
| 空気伝搬音 | 空調機からの音、外の騒音(窓・壁経由) | 遮音材・気密性確保 |
| 固体伝搬音 | ダクト・配管の振動音、機械振動の伝播 | 防振・絶縁・固定方法の改善 |
■音圧レベルの伝搬・合成の法則
| 条件 | 結果 |
| 点音源、距離2倍 | 約6dB減衰 |
| 線音源、距離2倍 | 約3dB減衰 |
| 面音源 | 距離に依存せず変化ほぼなし |
| 同一音源×6台稼働 | 78dB → 約92dB(10log₁₀6 ≈ 7.8dB) |
・複数音源の合成は単純加算不可(対数加算)
■音圧レベルの室間透過計算式
L₁ – L₂ = TL + 10log₁₀(S / A)
| 記号 | 意味 |
| L₁ | 音源室の音圧レベル[dB] |
| L₂ | 受音室の音圧レベル[dB] |
| TL | 透過損失[dB] |
| S | 透過面積[m²] |
| A | 受音室の等価吸音面積[m²] |
■その他試験対策用ポイント
・コインシデンス効果:壁が共鳴し高音域の透過損失が低下
・吸音力が大きい部屋ほど遮音性能は高くなる
・遮音等級Dr値:値が大きいほど性能高
・衝撃音等級:値が小さいほど性能高
・外部騒音が同じでも、録音スタジオ>コンサートホールの遮音性能が必要
■音の伝搬と分類
| 種類 | 例 | 対策 |
| 空気伝搬音 | ・空調機の音が壁・隙間を通って聞こえる音・ダクト内を通って排出口から出る音・道路交通・鉄道騒音 | 壁・窓・床などの遮音対策 |
| 固体伝搬音 | ・ダクト自体の振動音・ポンプなどの配管系の振動音・設備機器の振動が内装に伝わる | 防振装置・機器の固定・絶縁 |
■音の減衰特性(距離に伴う音圧レベルの変化)
| 音源の種類 | 距離が2倍になったときの減衰 | 距離が10倍になったときの減衰 |
| 点音源 | 約6dB | 約20dB |
| 線音源 | 約3dB | 約10dB |
| 面音源 | 減衰ほぼなし | 減衰ほぼなし |
■遮音・音響特性の要点
| 用語・現象 | 内容・試験対策ポイント |
| コインシデンス効果 | 壁が高音域で共鳴→透過損失が下がり遮音性能が低下 |
| 透過損失(TL) | 小さい音しか通らないほど大きくなる。大きいほど遮音性能が良い |
| 質量則 | 壁を重くすればするほど遮音性能が上がる |
| Dr値(遮音等級) | 数値が大きいほど遮音性能が高い |
| 衝撃音の音等級 | 数値が小さいほど遮音性能が高い |
| 吸音力の影響 | 受音室の吸音力が大きいほど、2室間の遮音性能は良くなる |
| 複層壁の特性 | 構成部材の透過損失を平均化して評価。共鳴で遮音性能が下がる場合がある |
| 建物用途と遮音性能 | 録音スタジオ>コンサートホール>一般室 |
■床衝撃音の種類と対策
| 分類 | イメージ例 | 主成分 | 有効な対策 |
| 軽量衝撃音 | フォークを床に落とす音 | 高周波成分 | カーペット・畳など柔らかい仕上げ材 |
| 重量衝撃音 | 人がベッドから飛び降りる音 | 低周波成分 | 床構造の質量や曲げ剛性の強化 |
| 注意点 | 重量衝撃音は仕上げ材だけでは不十分 |
■環境振動の時間特性と分類
| 振動の種類 | 特性・時間変動 |
| 道路交通振動 | 不規則で変動が大きい |
| 空調機などの設備振動 | 定常的で変動が小さい |
| 風による建物振動 | 長周期の正弦波 |
| 地盤振動 | 間欠的で非周期的 |
| 人の歩行による振動 | 間欠的・非周期的 |
| 建設振動・工場振動 | 間欠的で周期的・不規則 |
| 振動規制 | 夜間の方が基準が厳しい |
■振動の評価方法と試験ポイント
・時間率レベル(Lx):観測時間中、あるレベル以上に達した時間割合
例:L₆₀=60dB以上が全体の80%
・振動レベル評価は、最大加速度ではなく時間平均で行う
・振動規制法では、80%レンジ上端値で判定
■振動に関するその他重要事項
・防振溝は深いほど・振動源に近いほど効果的
・環境振動の対象周波数:鉛直方向 1~80Hz
・正弦波振動の場合:加速度の実効値=最大振幅から算出
・低周波数の振動の方が人は感じやすい
・乗り物の揺れは鉛直方向より水平方向に敏感
■光の基本用語と単位
| 用語 | 内容・定義 | 単位 |
| 照度 | 単位面積に入射する光束 | lx(ルクス) |
| 光度 | 単位立体角あたりの光束(点光源の強さ) | cd(カンデラ) |
| 輝度 | 観測方向から見た単位面積あたりの光度 | cd/m² |
| 昼光率 | 全天空照度に対する屋内の照度の比率 | % |
| 保守率 | 使用後の平均照度 ÷ 初期平均照度(器具・光源で決まる) | 無単位 |
| 設計光束維持率 | 光束減退を補正する係数 | 無単位 |
■照明設計・照度計算のポイント
・照度は距離の2乗に反比例(例:距離1/3 → 照度3²=9倍)
・照度均斉度 = 最低照度 / 最高照度
・必要照度計算式例:
灯数 = (必要照度 × 床面積) ÷ (1灯光束 × 照明率 × 保守率)
■光の性質と色温度
| 要素 | 内容・注意点 |
| 色温度 | 赤→黄→白→青(温度が高くなるほど青白くなる) |
| 色温度の例 | 白熱電球:約2800K/青空:10000K以上 |
| 演色評価数 | 100に近いほど自然光に近い(演色性が良い) |
| 光沢反射 | 平滑な面では正反射→光沢あり |
■昼光利用と昼光率
| 昼光項目 | 特徴・影響要素 |
| 昼光率 | 窓ガラスの透過率の影響を受ける |
| 直接昼光率 | 直射日光の影響。室内反射の影響は受けない |
| 間接昼光率 | 室内表面の反射率の影響を受ける |
| 天窓 vs 側窓 | 同面積なら天窓の方が昼光量が多い |
| 全天空照度 | 快晴よりも薄曇り時の方が高い |
| 照明器具と昼光 | 発光部の立体角が大きいほど、UGR値(不快グレア)は大きい |
■照明器具の種類と特徴
| 種別 | 例 | 備考 |
| 独立型 | ペンダント、スポット、フロアライト | 空間に独立して設置 |
| 建築化照明 | ダウンライト、光天井、コーニス照明 | 天井・壁等に埋め込み式 |
■人工光源の分類と特徴
| 種類 | 特徴・用途例 |
| 白熱電球 | 放電発光ではない。色温度約2800K。寿命短め |
| 蛍光ランプ | 発光効率:20~50lm/W。長寿命 |
| ハロゲンランプ | 白熱電球より高効率。蛍光より短寿命 |
| 高輝度放電ランプ(HID) | 水銀・ナトリウム・メタルハライドなど |
| LED | 指向性強い。熱・水に弱い。高効率で長寿命 |
| EL(エレクトロルミネセンス) | 面発光可能。表示や薄型照明に利用 |
■光源の設計・交換方式
| 項目 | 内容 |
| 設計光束維持率 | 経時劣化に伴う照度低下を補うための係数 |
| 個別交換方式 | 切れたランプを都度交換+一定期間で一斉交換(併用) |
| 集団交換方式 | 一定期間・灯数で交換時期を決める(オフィスで一般的) |
| 保守率 | 器具構造の影響大(例:露出形<密閉形)。室内粉じんは影響なし |
■水平面照度と太陽光
・水平面照度 = 法線照度 × sinH(H=太陽高度)
・大気透過率が高いほど照度も高い
・太陽高度が同じなら、大気透過率の差で地表照度が変化する
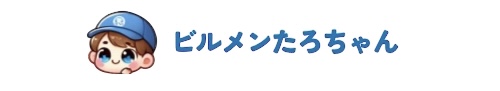

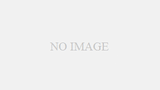
コメント