◎都市環境にまつわる重要用語
| 用語 | 意味・解説 |
| ヒートアイランド現象 | 都市化により、都市の中心部の気温が郊外より高くなる現象 |
| スプロール現象 | 乱開発などにより無秩序に市街地が拡大する現象 |
| ストリートキャニオン | 両側を高層建築で囲まれた道路空間。熱や汚染物質が滞留しやすい |
| ダウンドラフト | 煙突の煙が建物の背後の渦に巻き込まれて地上に降下・滞留する現象 |
| 熱帯夜 | 夜間(夕方~翌朝)の最低気温が25°C以上の日 |
| サスティナブルディベロップメント | SDGsの基本概念。持続可能な開発 |
| アルベド | 入射日射量に対する反射日射量の割合 |
| ファサード | 街路や広場に面する建築物の正面外観 |
◎都市環境に関するポイント
・ヒートアイランド現象:都市の舗装面・建築物・人工熱などが原因
・ストリートキャニオン:風が弱いと熱・汚染物質が拡散しにくい
・熱容量が大きい材料:温まりにくく、蓄熱しにくい(同じ熱量でも温度変化が小さい)
・パリ協定:2015年、COP21(フランス・パリ)で採択。温室効果ガス削減の国際枠組み
・温室効果:二酸化炭素などが太陽光を吸収→大気が温まり気温上昇
・都市部の風速:年平均では郊外より小さい。ただし高層建築周辺では局地的強風あり
・都市部の湿度:相対湿度は郊外より低い傾向
・雨水の保水能力:都市部では低く、洪水リスク増加
◎典型七公害
・大気汚染
・水質汚濁
・土壌汚染
・騒音
・振動
・地盤沈下
・悪臭
◎CASBEE(建築環境総合性能評価システム)の評価対象
| 評価分野 | 内容例 |
| エネルギー消費 | 断熱性、省エネ設備の導入など |
| 資源循環 | リサイクル率、廃棄物の抑制など |
| 地域環境 | 周辺との調和、ヒートアイランド対策など |
| 室内環境 | 温熱環境、音環境、空気質など |
◎日射量の大小関係(重要)
| 日にち | 大きい順に並べた日積算日射量 |
| 夏至 | 水平面 > 東・西向き鉛直壁面 > 南向き鉛直壁面 |
| 冬至 | 南向き鉛直壁面 > 水平面 > 東・西向き鉛直壁面 |
※逆順にして出題されること多し!
◎日射・太陽関連のポイント
・外付けブラインド > 内付けブラインド(日射遮蔽効果)
・日射反射率:白壁 > コンクリート > 緑葉
・熱容量が大きい材料:温まりにくく、蓄熱しやすい(例:アスファルト)
・ライトシェルフ:直射日光を反射し、部屋奥まで光を導く庇
・オーニング:窓の外に取り付ける日よけ
・天空日射:太陽光が大気中で散乱→地上に届く光(昼光利用時に活用)
・太陽定数:大気圏外で太陽に直面する1㎡あたりの放射エネルギー
◎設計図書に含まれる or 含まれない
| 設計図書に含まれる例 | 含まれない例(よく出題) |
| 配置図・平面図・立面図・断面図 | 施工図・原寸図・維持管理資料 |
| 仕様書(標準・特記) | 実施設計図と見積り図面 |
◎意匠図の種類とポイント
| 図面名 | 内容・用途の要点 |
| 配置図 | 建築物と敷地の関係、外構計画など(部屋の配置ではない) |
| 平面図 | 部屋配置を水平断面で示す(家具など描かれることもある) |
| 立面図 | 建築物の外観 |
| 断面図 | 建物の垂直断面 |
| 矩計図 | 建物主要部(基礎~屋根)の詳細断面 |
| 展開図 | 室内壁面を時計回りに表示 |
| 透視図 | 室内外の空間構成・雰囲気を立体的に描いた図(パース) |
◎その他重要知識
・日影図:建物が冬至に作る影を時間ごとに平面図上に記す
・日影曲線:棒の影の長さの時間変化(冬至によく出る)
・照り返し:日射の反射による。白壁や舗装面が主原因
・温室効果:赤外線が大気中のCO₂などに吸収→地球が冷えにくくなる
・紫外線・可視光線・赤外線:短波長の順に並ぶ
・遮熱塗料:近赤外線の反射率が高い
・レンタブル比:貸室面積 ÷ 基準階の全体面積 ×100(%)
◎地層と地盤の特徴
| 地層区分 | 特徴 | 地耐力 | 注意点 |
| 沖積層 | 新しい軟弱地盤(埋立地など) | 小 | 液状化しやすい |
| 洪積層 | 比較的古く締まった地盤 | 良好 | |
| 第3紀層 | 古く強固な地盤(例:土丹層) | 大 | 建物の安定性が高い |
| 洗堆層(誤) | ※沖積層よりもさらに軟弱な地盤とされるが、用語としては注意 | 非常に小 | 記述ミス注意(誤記出題あり) |
◎基礎の種類と特徴
| 基礎の種類 | 特徴・用途 |
| べた基礎 | 軟弱地盤向け、建物全体で荷重を分散 |
| 布基礎(連続フーチング基礎) | 木造・小規模建物向け |
| 独立フーチング基礎 | 正方形または長方形の基礎+地中梁で接続 |
| 杭基礎 | 深層の強固な地盤まで荷重を伝達(異種基礎の併用は原則禁止) |
・フーチング:基礎の広がり部(主に鉄筋コンクリート製)
・地業:基礎スラブの下に施工される割ぐり石や捨てコン(※上ではない)
・標準貫入試験:地盤の強度や沈下特性などを調べる試験
◎地盤と構造に関する要点
・液状化現象:砂質地盤や埋立地で起こりやすい(粘性土地盤は×)
・圧密沈下:粘土質地盤に重みがかかって沈下する現象
・地盤の許容地耐力:支持力と沈下量の両方で決まる
・短期許容応力度=長期の2倍
・砂質地盤の方が粘土質地盤より長期の応力度に強い
◎構造形式の比較
| 構造種別 | 特徴 |
| ラーメン構造 | 柱と梁が剛接合、応力は軸力+曲げ(※軸力のみは×) |
| トラス構造 | 三角形構成で応力は軸力、四角形ベースではない(※×) |
| 吊り構造 | 主部を吊って支える構造 |
| 空気膜構造 | 内外の気圧差による張力で成り立つ膜構造 |
| 壁式構造 | 壁で荷重を支える(RC造の中高層によく使われる) |
| スケルトン・インフィル | 躯体と内装・設備を分離した構造(※一体型ではない) |
◎鉄筋コンクリート構造(RC構造)
| 項目 | ポイント |
| コンクリートの特徴 | 圧縮に強い、引張に弱い、耐火性・耐久性が高い |
| 鉄筋との線膨張係数 | ほぼ同じ(異なるは×) |
| 帯筋(柱)、あばら筋(梁) | 引張力やせん断力に対する補強筋 |
| プレキャスト化 | 工期短縮・品質安定 |
| かぶり厚さ | 柱・梁は2cm以上(直接土に接しない場合) |
| 耐震壁の鉄筋配置 | 厚さ20cm以上→複筋 |
| コンクリート床厚 | 通常13~20cm程度 |
| 開口部の最大径 | 梁せいの1/2以下 |
| 捨てコンクリート | 基礎形状を整えるために最初に打つコンクリート。余りを流すものではない(×) |
◎木造・構造材に関するポイント
・**在来工法・プレハブ工法・枠組壁工法(2×4)**が木構造の代表
・集成材:繊維方向をそろえて接着し、大断面にした木材
・筋かい:耐震性を持たせるために壁内に配置する斜材
◎鉄骨構造の基礎知識
| 項目 | 内容・ポイント |
| 耐食性 | 鉄骨構造は耐食性に劣る(※「優れる」は誤り) |
| 高温時の強度 | 鋼材は温度上昇で強度低下し、1000℃ではほぼゼロ |
| 鋼材の炭素量 | 炭素量が増すとじん性は低下(※「高まる」は誤り) |
| 鋼材のJIS記号(例:SN400B) | 数字=引張強さ、B=じん性区分(A<B<C) |
| 接合方法 | ラーメン構造・トラス構造などに分けられる |
| 溶接継手の種類 | 重ね継手、突合せ継手、T継手 |
| 合成梁 | 鉄骨梁とコンクリート床を高力ボルト等で一体化したもの |
| 床材 | 鉄筋コンクリート床、デッキプレート等 |
| デッキプレート | ※広幅帯鋼ではなく、波形鋼板(誤選択肢で出やすい) |
| ボルト接合 | 高力ボルトが主流。摩擦力で伝達(曲げモーメントではない) |
| 降伏比 | 大きいほどじん性は低下 |
| H形鋼ウェブ | せん断力に抵抗(※曲げモーメントではない) |
◎積載荷重(用途別)と大小関係
| 用途 | 積載荷重(大きい順) |
| 床構造計算時 | 自動車車庫 > 劇場 > 店舗 > 教室 > 事務室 > 住宅(居室) |
| 地震力計算時 | 自動車車庫 > 劇場 > 店舗 > 事務室 > 教室 > 住宅(逆転注意) |
※教室と事務室の順番は、構造計算と地震力計算で逆になるので要注意!
◎荷重の種類と特徴
| 荷重種別 | 内容・注意点 |
| 固定荷重 | 建物本体(構造体、仕上材など)の自重 |
| 積載荷重 | 人・家具・物品の重さ(用途により異なる) |
| 積雪荷重 | 屋根形状や地域の積雪量により変動。1cmあたり20N/m²以上 |
| 風圧力 | 動的荷重。速度圧×風力係数で計算 |
| 地震力 | 慣性力によるもので、積載荷重を加味して算出される |
| 土圧・水圧 | 常時荷重として扱われる |
※垂直荷重に「風圧力」「地震力」は含まれない(それらは水平荷重)
◎構造力学のポイント整理
| 力の種類 | 定義・特徴 |
| せん断力 | 部材を切断しようとする力(例:梁の中間に作用) |
| 軸方向力 | 部材の軸方向に働く力(圧縮・引張) |
| 曲げモーメント | 部材を曲げようとする力のモーメント成分 |
◎支点形式と伝達される力
| 支点種別 | 伝達される力 |
| 固定端 | 曲げモーメント、せん断力、軸力の全て |
| ピン支点 | せん断力、軸力(曲げモーメントは伝えない) |
| ローラー支点 | せん断力のみ(水平・回転方向は自由) |
◎支点形式(名称と構成)
・ピン支持形式:2つのピン支点+中間にもう1つのピン節点
・特支持形式(片持ち):一端固定、他端ピン
・静定構造:力のつり合い条件だけで解ける構造
・不静定構造:つり合い条件だけでは解けず、変形条件が必要
◎構造形式ごとの特徴
| 構造形式 | 主な特徴 |
| トラス構造 | ・応力は軸方向力のみ(せん断・曲げは理論上発生しない)・接点はピン接合扱い |
| ラーメン構造 | ・部材に軸力・せん断力・曲げモーメントが生じる・柱と梁が剛接合 |
| 折板構造 | ・主に面内力で構成される(波形の板構造) |
| 空気膜構造 | ・内部と外部の気圧差による張力で構成 |
| プレストレストコンクリート | ・コンクリートにあらかじめ圧縮力を導入→ひび割れ防止 |
◎構造力学の基本用語
| 用語 | 定義・ポイント |
| せん断力 | 部材をずらすように働く力(例:梁の中間) |
| 曲げモーメント | 部材を曲げようとする力のモーメント |
| 軸方向力 | 部材の長さ方向に働く力(引張・圧縮) |
| 層間変形角 | 層間変位 ÷ 階の高さで計算 |
| 剛性率 | 柱・梁などの骨組の立面的バランスを示す指標 |
◎梁の種類と荷重の反応
| 梁の種類 | 支点構成 | 荷重による変形・応力の特徴 |
| 片持ち梁 | 一端固定、他端自由 | 先端に曲げモーメントは生じない根元が最大曲げ |
| 単純梁 | 両端ピン or ピン+ローラー | 中央が最大曲げ、端部はモーメント0 |
| 三ピン支持 | 2つの回転支点+中央ピン節点 | 静定構造として解析可能 |
◎配筋と負担する応力
| 部材・筋 | 負担する主な応力 |
| 主筋 | 曲げモーメント、軸方向力 |
| あばら筋 | せん断力(梁) |
| 帯筋 | せん断力(柱) |
◎コンクリートの性質・試験・用語
| 項目 | 内容・定義 |
| ワーカビリティ | 流動に対する抵抗性の程度(スランプ試験で確認) |
| スランプ値 | 大きいほど流動性が高い |
| ブリージング | 水が浮き上がり泥水層になる現象(品質に影響) |
| コールドジョイント | 打ち重ねが不十分で付着性が弱い部分 |
| レイタンス | 表面に微粒分が浮き上がり層になる(削り落とす必要) |
| コンシステンシー | 流動性に対する抵抗性(ほぼワーカビリティと同義) |
◎かぶり厚さ(コンクリートと鉄筋)
| 対象部位 | 最小かぶり厚さ |
| 直接土に接しない柱・梁等 | 3cm以上 |
| 直接土に接する基礎・壁等 | 4cm以上 |
| 基礎(捨てコン除く) | 6cm以上 |
| 耐力壁以外の壁・床 | 2cm以上 |
◎材料の密度(軽い順)
合板 < コンクリート < アルミニウム < 鋼材
◎コンクリートの構成と物理特性
| 材料構成 | 定義 |
| セメント+水 | セメントペースト |
| +砂 | モルタル |
| +砂利 | コンクリート |
・普通コンクリート密度:約2,300kg/m³
・軽量コンクリート密度:約1,700kg/m³
・圧縮強度:約18N/mm²
◎鋼材・鉄筋の基礎知識
| 項目 | 内容・注意点 |
| 鉄筋の種類 | 普通棒鋼、異形棒鋼 |
| SD295Aの数値 | 降伏点強度(295N/mm²) |
| 降伏比 | 引張強さに対する降伏強さの割合(小さいほどじん性に優れる) |
| 耐火被覆工法 | 吹付け・巻付け・成形板張りなど |
| 鋼材の炭素量 | 軟鋼:0.12~0.30% |
| 鋼材の応力ひずみ曲線 | 最大荷重時の応力度=引張強度 |
◎鉄骨構造と接合
| 接合形式 | 特徴 |
| 高力ボルト接合 | 摩擦力で伝達。余長はねじ山3以上 |
| 溶接(突合せ・すみ肉等) | 溶接方法により母材の配置が異なる |
| 合成梁 | 鉄骨梁とコンクリ床を高力ボルトで一体化 |
◎耐震・免震・制振構造
| 構造形式 | 概要・構成要素 |
| 耐震構造 | 壁・ブレース増設などで建物が揺れに耐える |
| 免震構造 | アイソレータ・オイルダンパーで地震力を遮断 |
| 制振構造 | ダンパー等で揺れ自体を減衰させる |
◎構造形式の特徴比較表
| 構造形式 | 主な特徴 | 応力の種類 |
| トラス構造 | ・部材は軸力(引張・圧縮)のみ負担・接点はピンで構成 | 曲げモーメントなしせん断力なし |
| ラーメン構造 | ・柱と梁を剛接合し、剛性を確保・変形に強い構造 | 曲げモーメントせん断力軸力 |
◎応力の種類と説明
| 応力名 | 内容・説明 |
| 軸方向力 | 部材の軸に沿って働く力(引張力・圧縮力) |
| せん断力 | 部材をずらすように働く力(例:ボルトのずれ) |
| 曲げモーメント | 部材を曲げようとするモーメント(例:梁のたわみ) |
◎梁の種類と支点構成・特徴
| 梁の種類 | 支点構成 | 特徴 |
| 片持ち梁 | 一端:固定他端:自由 | ・先端に曲げモーメントなし・根元に最大曲げ発生 |
| 単純梁 | 両端:回転端 or ローラー | ・中央に最大曲げモーメント・支点でモーメント0 |
| 三ピン支持 | 2つのピン+中間にピン節点 | ・静定構造として力学的に解析しやすい |
◎荷重の種類と区分(作用時間による)
| 区分 | 内容例 |
| 常時荷重(長期) | 建物の自重、仕上材、固定された設備など |
| 非常時荷重(短期) | 地震力、風圧、積雪荷重など |
◎荷重の種類と特徴まとめ
| 荷重種別 | 主な内容・特徴 |
| 固定荷重 | 建築物の構造体・仕上げ材などの自重 |
| 積載荷重 | 人・家具・物品など、用途に応じて変動 |
| 風圧力 | 動的荷重。速度圧×風力係数で計算 |
| 地震力 | 地震時の慣性力として建物に作用 |
| 積雪荷重 | 地域・屋根勾配により異なる(1cmあたり20N/m²以上) |
◎荷重と反応(片持ち梁 vs 単純梁)
| 項目 | 片持ち梁 | 単純梁 |
| 曲げモーメント | 根元が最大。先端は0 | 中央が最大、支点は0 |
| せん断力 | 全長一定 | 中央0、支点が最大 |
| 先端の反応 | 曲げなし・せん断一定 | 曲げ最大(中央)・せん断は変動 |
◎荷重の分類例(集中荷重・等分布荷重)
・集中荷重:1点にかかる荷重(例:梁の中央に重い物)
・等分布荷重:全体に均一にかかる荷重(例:天井仕上げ材)
◎建築材料の密度(軽い順)
| 材料名 | 密度の目安(軽い順) |
| 合板 | 最も軽い |
| コンクリート | 約2,300kg/m³(普通) |
| アルミニウム | 比重 約2.7(鉄の約1/3) |
| 鋼材(鉄) | 約7,850kg/m³ |
◎構造設計に関わる基礎知識
| 用語・数値 | 説明・注意点 |
| 層間変形角 | 層間変位 ÷ 階の高さ(出題で逆にされること多い) |
| 剛性率 | 各階の水平剛性のバランス(骨組の立面バランスを表す指標) |
| 耐震改修の定義 | 安全性向上のための増築・改築・修繕・模様替・除却・敷地整備 |
| 木造住宅の法定耐用年数 | 22年 |
| RC構造の店舗建築の法定耐用年数 | 39年 |
◎各種構造の特徴まとめ
| 構造形式 | 特徴・ポイント |
| 折板構造 | 波形の鋼板などで構成。面内力が主たる応力 |
| 空気膜構造 | 内部・外部の気圧差により膜面に張力を与えて構成される |
| プレストレストコンクリート構造 | あらかじめ圧縮力を導入。ひび割れ防止・クリープ抑制 |
| 木質構造 | 在来工法・プレハブ工法・枠組壁工法(ツーバイ方式)などがある |
| 壁式構造の組積造 | れんが造・補強コンクリートブロック造(補強が入る) |
| 混合構造 | RC構造とS構造など異種構造の良さを併用した構造 |
◎鉄筋コンクリート構造:配筋と応力
| 部位・配筋名 | 主に負担する応力 |
| 主筋(柱・梁) | 曲げモーメント、軸方向力 |
| 帯筋(柱) | せん断力(主筋の座屈防止も担う) |
| あばら筋(梁) | せん断力 |
◎かぶり厚さ(コンクリート表面から鉄筋までの距離)
| 対象部位 | 最小かぶり厚さ |
| 直接土に接しない柱・梁等 | 3cm以上 |
| 直接土に接する基礎・床等 | 4cm以上 |
| 基礎(捨てコンクリート除く) | 6cm以上 |
| 耐力壁以外の壁・床 | 2cm以上 |
◎RC構造:寸法・仕様に関する重要数値
| 項目 | 数値・内容 |
| 柱の小径 | 支点間距離の1/15以上 |
| 柱の主筋本数 | 4本以上 |
| 梁のせい(梁断面の高さ) | 下端から上端までの距離(※用語確認) |
| 梁のあばら筋の曲げ角度 | 135度以上で主筋に定着 |
| 柱の帯筋比 | 0.2%以上 |
| 梁に開ける通孔の直径 | 梁せいの1/3以下 |
| 通孔の中心間隔 | 直径の3倍以上 |
◎コンクリートの基本構成
| 材料名 | 内容 |
| セメントペースト | 水+セメント |
| モルタル | セメントペースト+砂 |
| コンクリート | モルタル+砂利(粗骨材) |
◎コンクリートの基本性質と用語
| 用語・数値 | 説明・注意点 |
| 普通コンクリート密度 | 約2,300kg/m³ |
| 軽量コンクリート密度 | 約1,700kg/m³(※2,500kg/m³は誤り) |
| 圧縮強度(普通) | 約18N/mm² |
| ワーカビリティー | 流動に対する抵抗性(フレッシュコンクリートの性質) |
| スランプ試験 | ワーカビリティの代表的な試験法 |
| ブリージング | 打設後、水や空気が浮上してできた泥状層 |
| コールドジョイント | 打ち重ねたコンクリートが一体化せずにできた継ぎ目 |
| レイタンス | 硬化時に浮き出たセメントや微粒子が層状になったもの |
| 捨てコンクリート(捨てコン) | 基礎の底面を平らに整えるために敷くコンクリート |
◎コンクリート関連の寸法
| 部位 | 厚さ・仕様 |
| 床スラブ | 約13~20cm |
| 壁 | 約10~15cm |
| 耐力壁 | 12cm以上が原則(20cmで複筋配置) |
◎鋼材・金属材料のポイント
| 材料・用語 | 説明・特徴 |
| アルミニウム | 比重は鉄の約1/3~1/5(非常に軽い) |
| トタン | 亜鉛メッキ鋼板 |
| ブリキ | すずメッキ鋼板 |
| ステンレス鋼 | 鉄にクロム・ニッケル等を添加→耐食・耐熱性が高い |
| 引張強度 | 鋼材の応力-ひずみ曲線において最大荷重時の応力度 |
◎ガラスの種類と性質
| ガラス名 | 特徴・構成 |
| 主原料 | 珪砂(SiO₂) |
| フロート板ガラス | 表面は平滑(※凸凹していない) |
| 熱線反射板ガラス | ミラー効果あり(鏡面反射) |
| 熱線吸収板ガラス | 無色透明 |
| 強化ガラス | 表面に引張応力を持たせたガラス |
| 合わせガラス | 中間膜や空気層を封入した複層ガラス |
| 日射取得係数 | 各種ガラスの日射熱取得量 ÷ 3mm厚透明フロートガラスの取得量 |
◎防水材料と関連事項
| 種類 | 特徴・用途 |
| アスファルト防水 | 陸屋根などで多用。施工しやすく耐久性も高い |
| モルタル防水 | セメント系の材料による古典的な防水 |
| シート防水 | 合成ゴム系・プラスチック系。接着施工が基本 |
| 塗膜防水 | 液体状の材料を塗布して膜を形成 |
| ステンレスシート | 接着剤施工→太陽熱に弱く、防水性が低下しやすい |
◎その他材料の基礎知識
| 材料・製品名 | 特徴・内容 |
| 木材 | 引火点は約300°C以上 |
| 合板 | 繊維方向を交差させた薄板を接着したもの |
| プラスタ | 石膏等の無機質粉末+水=塗壁材 |
| テラゾ | 大理石粉末などを混ぜた仕上げ床材(高級感がある) |
◎鋼材の耐火被覆工法
| 工法名 | 特徴・用途 |
| 吹付け工法 | 耐火被覆材を直接吹き付ける。施工性に優れる |
| 巻付け工法 | 耐火材(ボードなど)を鋼材に巻き付けて保護する |
| 成形板張り工法 | 成形された耐火板を張り付ける。仕上がりがきれい |
◎溶接の種類と特徴
| 溶接形式 | 概要 |
| 突合せ溶接 | 板同士を突き合わせて溶接。主に母材の延長上 |
| すみ肉溶接 | 板の角部を三角形状に溶接 |
| 部分溶込み溶接 | 完全には溶け込まないが十分な強度を確保 |
| T継手 | 材料がT字型に交わる部位の溶接 |
◎高力ボルト接合の基礎知識
| 項目 | 内容・注意点 |
| 接合方式 | 主に摩擦力で伝達(摩擦接合) |
| 締付け長さ | 接合される鋼板の板厚の合計 |
| 余長 | 締付け後、ねじ山3山以上確保 |
| 力の伝達 | 材間の面圧・摩擦力により力を伝達 |
◎耐震・免震・制振構造の違い
| 構造種別 | 概要・主な装置 |
| 耐震構造 | 柱・梁・壁・ブレースで建物を頑丈にして揺れに耐える |
| 免震構造 | 建物と地盤の間にアイソレータ+オイルダンパーを挿入 |
| 制振構造 | オイルダンパー・アクティブ制振装置などで揺れのエネルギーを吸収 |
◎まとめ:重要チェックポイント
・鉄筋とコンクリートの線膨張係数はほぼ等しい → 温度差での割れが起きにくい
・コンクリートの中性化・クリープ・収縮は、寿命や構造性能に関わる
・高力ボルト摩擦接合は、「せん断」ではなく「摩擦」による力の伝達がポイント
・溶接継手の種類は形状・用途によって明確に区別される
・鋼材の降伏比が小さい=じん性が高い(ひっかけに注意)
◎熱伝導率(小さい順)
| 材料 | 備考・ポイント |
| グラスウール | 空気の断熱性を利用。熱伝導率が最も低い |
| 硬質ウレタンフォーム | 優れた断熱材 |
| 木材 | 自然素材で断熱性あり |
| 板ガラス | 中程度の熱伝導率 |
| コンクリート | 比較的高い熱伝導率 |
| 鋼材 | 金属であり高い熱伝導率 |
| アルミニウム | 金属中で最も熱伝導率が高い(鋼材より上) |
※ひっかけ例:「グラスウールは熱伝導率が高い」→誤!
◎金属材料と表面処理
| 材料名 | 処理内容 |
| トタン | 鋼板に亜鉛めっき |
| ブリキ | 鋼板にすずめっき |
| ステンレス | 鉄にクロム・ニッケル等を加えて耐食・耐熱性を付加 |
◎木材の性質と管理
| 内容 | 数値・性質 |
| 含水率の式 | (含水量 ÷ 絶乾質量) × 100% |
| 気乾状態の含水率 | 約15% |
| 着火温度 | 約260°C |
| 自然発火温度 | 約450°C |
| 腐朽の4要素 | 養分・湿気・空気・温度 |
| 虫害対策 | 薬剤処理・表面被覆が基本 |
◎アルミニウムの特徴
・比重は鉄の約1/3 → 軽くて扱いやすい
・腐食しやすい:他の金属やコンクリートと接触すると腐食が進む
・カーテンウォールの材料として多用される(非耐力壁)
◎H形鋼・床構成に関する材料
| 名称 | 役割・用途 |
| スタッドボルト | 鉄骨梁とコンクリートスラブを緊結する部材 |
| 合成梁 | スタッドボルトで梁とスラブを一体化した構造 |
| デッキプレート | 波形の鋼板で床スラブの下地(鉄骨構造で使用) |
◎ガラスの種類と特徴
| 種類 | 特徴・ポイント |
| LOW-Eガラス | 表面に特殊金属膜。断熱・遮熱効果 |
| 合わせガラス | ガラス+中間フィルム → 安全性・防犯・紫外線カット効果 |
| 複層ガラス | 2枚のガラスを間隔保持して密封 → 断熱・結露対策 |
| 強化ガラス | 表面に圧縮応力 → 衝撃に強い、割れると粒状になる |
| 入(網入り)ガラス | 飛散防止効果あり(※火災時に特に効果を発揮) |
| 板ガラス | 不燃だが部分加熱で破損しやすい |
◎防水・仕上材・面材のポイント
| 材料種別 | 特徴・注意点 |
| シート防水 | 合成ゴム系・プラスチック系。接着施工が基本 |
| アスファルトルーフィング | 合成繊維の原紙にアスファルトを含浸させた材料 |
| 合成高分子材料 | 合成樹脂・ゴム・繊維の3種類に大別 |
◎面材・無機質材料の整理
| 材料名 | 主な特徴 |
| せっこうボード | 耐火性あり、湿気に弱い |
| プラスタ | 石膏など+水で練った塗り壁材 |
| しっくい | 消石灰+のり・すさ・水で構成された左官材 |
| 合板 | 繊維方向を交差させた薄板を接着 |
| CLT | 繊維方向が直交するよう積層された構造用木材 |
| 集成材 | 繊維方向を平行に揃えた板を接着 → 大断面構造材 |
◎木材の強度方向(強い順)
繊維方向(幹軸)>半径方向(放射軸)>年輪接線方向
◎建築生産の特徴と用語定義
| 用語 | 定義・内容 |
| 建築生産 | 注文生産・一品生産・現場生産が多い |
| 工事監理 | 設計図通りに施工されているかを設計者の責任で確認(建築士法に規定) |
| 施工管理 | 現場の工程・品質・安全などの管理全般(諸官庁への手続きも含む) |
| 設計図書 | 設計図・仕様書など。請負契約時に必要な書類 |
※よく出る誤り:「工事監理=施工者が行う」→ 正しくは設計者(または設計者に委託)
◎請負契約と入札制度
| 区分 | 内容・注意点 |
| 一般競争入札 | 条件を公示し、広く入札者を募集 |
| 指名競争入札 | 指定した業者のみが参加 |
| 随意契約 | 特定の業者と直接契約(緊急時・特殊工事など) |
| 二括下請負 | 原則禁止(発注者の書面承諾がなければ違反)公共工事では全面禁止 |
◎工事監理と施工管理の比較
| 項目 | 工事監理 | 施工管理 |
| 担当者 | 設計者(建築士) | 施工者(現場代理人・現場監督など) |
| 主な内容 | 設計図通りに工事が行われているかの確認 | 工程・品質・安全・原価などの現場運営 |
| 根拠法令 | 建築士法 | 建設業法・安全衛生法など |
| 委託の有無 | 建築主が設計者に委託することが多い | 施工者が自社管理として行う |
◎工事分類と内容(流れ順)
| 工種区分 | 内容例 |
| 仮設工事 | 工事用の電力・水道・足場など安全・作業環境の準備 |
| 土工・地業 | 土工事・山留工事・地業(割栗地業など)・基礎工事 |
| 躯体工事 | 型枠・鉄筋・コンクリート・鉄骨・木工事など建物の骨組みづくり |
| 仕上げ工事 | 屋根・防水・タイル・塗装・ガラス・建具など内外装を整える作業 |
| 設備工事 | 空調・電気・給排水・衛生など(建築工事とは別契約が多い) |
◎工法の種類
| 工法名 | 内容・特徴 |
| プレハブ工法 | 工場製作部材を現場で組み立てる → 工期短縮・品質安定 |
| 軸組構法 | 木材や鋼材で柱・梁を組み、面材で構造強化 |
◎よく出る誤選択肢の注意点
・工事監理を「施工者が行う」とする→ 誤り
・躯体工事に「防水工事」が含まれるとする→ 防水工事は仕上げ工事
・建築物は「施工者によって企画される」とする→ 企画は建築主や設計者
・二括下請負は「公共工事ならOK」とする→ 公共工事は全面禁止
◎ガスの種類と基本性質
| 分類 | 都市ガス(13A) | LPガス(プロパン・ブタン) |
| 主原料 | 天然ガス(メタンなど) | プロパン・ブタン |
| 空気との比重 | 軽い(上部に滞留) | 重い(下部に滞留) |
| 発熱量 | 小さい(例:約11,000kcal/m³) | 大きい(例:約24,000kcal/m³) |
| 理論空気量 | LPガスの方が少ない | 都市ガスは多く必要 |
| 状態 | 常温・常圧で気体 | 加圧・冷却で液化し、容器で供給 |
| 供給形態 | 地中のガス管経由 | ガスボンベ(鋼板製容器)にて供給 |
| 付臭剤 | どちらも無臭のため付臭義務あり | 同上 |
◎付臭剤と法令
・都市ガスもLPガスも無臭であるため、法令により付臭剤の添加が義務付けられている
・人間が1,000倍に希釈しても感知できるレベルの**臭い物質(チオール系など)**が使用される
◎発熱量と理論空気量
| 用語 | 内容・補足 |
| 低位発熱量 | 水蒸気の凝縮潜熱を含まない発熱量 |
| 理論空気量 | ガス1m³を完全燃焼させるために必要な空気量(※都市ガスの方が多い) |
| LPガスの発熱量 | 都市ガスより約2倍高い |
◎ガス設備と法令・安全対策
| 項目 | 内容・注意点 |
| LPガス容器 | 一般に鋼板製。直射日光を避け40℃以下の場所に設置 |
| LPガスの漏えい時 | 比重が空気より重いため、低部に滞留しやすい |
| 都市ガスの漏えい時 | 軽いため天井部に滞留 |
| ガス臭時の対処 | 換気扇はNG。まず窓や戸を手で開けて換気 |
| ガス管の引込時 | 腐食防止のため、絶縁継手の設置が必要 |
| マイコンメーター | ガス漏れ・地震時の自動遮断機能あり |
| 点検 | 所有者または使用者が責任を持つが、実際は業者が実施することが多い |
◎ガス供給圧力の分類(都市ガス)
| 圧力分類 | 圧力値の目安 | 説明 |
| 高圧供給 | 0.5MPa以上 | 一部工場・施設向け |
| 中圧供給 | 約0.1~0.5MPa程度 | 商業ビル・大型住宅団地など |
| 低圧供給 | 約2~3kPa(=20~30mbar) | 一般家庭向け |
◎よくある誤り選択肢と訂正
| 誤った記述例 | 正しい内容 |
| LPガスは空気より軽く、天井部に滞留する | → LPガスは重く、低部に滞留 |
| ガス臭時は換気扇を動かして排出する | → スイッチ操作はNG。まず戸や窓を開けて換気 |
| LPガス容器は密閉室内に設置するのが望ましい | → 屋外の風通しが良く、直射日光を避ける場所が望ましい |
| LPガスの臭気はプロパン・ブタン固有のもの | → どちらも無臭。付臭剤を添加している |
| 都市ガスの発熱量はLPガスより高い | → LPガスの方が発熱量は高い(倍近い差) |
◎エレベーターの種類と用途
| 種類 | 特徴・用途 |
| ロープ式 | ・中高層~超高層に多用・汎用性が高い |
| 油圧式 | ・低速・低層向け(例:共同住宅・中小規模建築)・高層には不向き |
◎機能・設備・法令関係
| 内容 | 正誤ポイント |
| 火災時は避難階に自動停止する管制運転装置 | 乗用エレベーターに必要(正) |
| 地震時は最寄階に自動停止 | 安全確保のための基本機能(正) |
| 非常用エレベーターは建築基準法で義務化 | 高さ31m超の建築物に必要(正) |
| 非常用エレベータの設置義務→「電気事業法」 | × → 建築基準法(誤) |
| 火災時、非常用エレベータは消防隊優先使用 | 正 |
| 非常用エレベーターは戸を開けたまま使用可能 | 正 |
◎非常用進入口の規定
| 内容 | ポイント |
| 進入口は3階以上に設置義務あり | 非常用エレベータがある場合は免除可 |
| 外部から開放または破壊できる構造 | 救助活動を前提とした構造(建築基準法) |
◎エレベーター設備の仕様・性能
| 項目 | 内容・数値例 |
| 規格型エレベータ | 最近は機械室なしが標準(※過去は屋上に設置が標準) |
| JIS規格:積載900kg | 最大定員13人 |
| 巻上電動機 | 現在は交流式が主流 |
| 小荷物専用昇降機 | かごの床面積・天井高さに上限あり(リフト的用途) |
◎エスカレーター・動く歩道の仕様(定格速度)
| 勾配・用途 | 定格速度の上限 |
| 動く歩道(勾配8°以下) | 50m/min 以下 |
| 勾配 8°超~30°以下 | 45m/min 以下 |
| 勾配 30°超~35°以下 | 30m/min 以下 |
◎エスカレーターの安全装置
| 内容 | ポイント |
| 防火シャッター閉鎖時に連動して停止する装置 | 法令で定められた制動装置 |
| 公称輸送能力は、定格速度 × 踏段幅で決まる | JISや技術指針に準拠 |
◎誤選択肢の注意点(過去問対策)
| 誤った記述 | 正しい内容 |
| 油圧式エレベーターは高層ビルに多用される | → × ロープ式が中高層~超高層向け |
| エレベーターに機械室があるのが標準仕様 | → × 最近は機械室なしが主流 |
| 非常用エレベータの設置義務は電気事業法による | → × 建築基準法により義務化 |
| LPガスは軽く、天井に滞留する | → × LPガスは重く、床部に滞留する |
◎受変電設備・供給方式の基礎
| 用語・設備名 | 説明・ポイント |
| 受変電設備 | 電力会社から送られる電力を受電し、所定の電圧に変換する設備 |
| 高圧受電 | 契約電力30kW以上の建築物では、6.6kVで受電し、構内で変圧する |
| 変圧器容量の算出 | 電気設備の負荷合計 × 利用率 により決定 |
| 配線の許容電流値 | 配線用遮断器(ブレーカー)より大きく設定(誤って小さくしない) |
◎電圧の区分(交流・直流)
| 区分 | 交流(AC) | 直流(DC) |
| 低圧 | 600V 以下 | 750V 以下 |
| 高圧 | 600V 超~7000V 以下 | 750V 超~7000V 以下 |
| 特別高圧 | 7000V 超 | 7000V 超 |
※高圧・特別高圧の区分は、建築設備・法令問題で頻出
◎交流と直流の違い・関連知識
| 項目 | 内容・数値等 |
| 実効値100Vの交流電圧 | ピーク電圧:約140V(=100V×√2) |
| 電力 | 電圧 × 電流に比例 |
| 磁束密度 | 電流の強さ × コイルの巻き数に比例 |
| 同一電力の比較 | 同じ電力値なら、交流のピーク電圧は直流より大きい |
| 長距離配線時の注意 | 電圧降下が起こるため、電線太さ・補償が必要 |
◎電動機・制御方式・安全
| 内容 | ポイント |
| 交流電動機 | 空調ファン・ポンプ等に広く使用される |
| スターデルタ起動方式 | 起動時の過電流を防ぐ制御法 |
| インバータ制御 | 回転数・トルク調整が効率的に可能 |
| 地域マイクログリッド | 自然エネルギーを組み合わせた分散型電力システム |
◎非常設備・設置義務など
| 設備名 | 設置義務・ポイント |
| 非常コンセント設備 | 地階除く11階以上の階に設置義務(消防法) |
| 非常用照明装置 | 建築基準法により定められている |
◎誤り選択肢対策(よく出るパターン)
| 誤った記述例 | 正しい内容 |
| ケーブルの許容電流値は、遮断器より小さく設定する | → 大きくするのが正しい(過負荷対策) |
| 非常コンセントの設置は建築基準法に定められている | → 消防法による義務 |
| 実効値100Vの交流電圧のピーク値は100Vである | → 約140V(=100×√2) |
| 電力は電圧と電流の差に比例する | → × 積(電圧×電流)に比例 |
◎消防用設備の主な種類と用途
| 設備名 | 特徴・用途・設置場所例 |
| 屋内消火栓設備(1号) | 2人以上で操作、消火能力が高い(例:事務所・劇場等) |
| 屋内消火栓設備(2号) | 1人でも操作可能、消火能力は低い(例:小規模店舗等) |
| 屋外消火栓設備 | 敷地外周等に設置される消防隊用の設備 |
| スプリンクラー設備 | 水道連結型が福祉施設で使用される(高齢者向け施設など) |
| 泡消火設備 | 窒息+冷却作用、油火災対応(例:ガソリンスタンド、駐車場) |
| 粉末消火設備 | 負触媒作用により火を消す(例:変電所、危険物施設など) |
| ハロゲン化物消火設備 | 電算室・図書館等で使用、オゾン層破壊の懸念から現在は非推奨 |
| 不活性ガス消火設備 | 希釈作用による消火。水損を避けたい電気室・ボイラ室等で使用 |
◎感知器の種類と作動原理
| 感知器名 | 作動原理・特徴 | 設置例 |
| 差動式熱感知器 | 温度の上昇速度が一定以上になると作動 | 一般的な空間 |
| 定温式熱感知器 | 一定温度以上になると作動 | 厨房・ボイラ室 |
| 煙感知器 | 空気中の煙の濃度が一定以上で作動 | 居室・通路など早期検知が必要な所 |
| 炎感知器 | 紫外線・赤外線の強度で感知(マイクロ波は×) | アトリウム、大型ドーム空間など |
※ひっかけ例:「炎感知器はマイクロ波で感知する」→ 誤り
◎消防法による分類(どの法令に基づくか)
| 設備名 | 分類 | 根拠法令 |
| 自動火災報知設備 | 警報設備 | 消防法 |
| 非常コンセント設備 | 消火活動上必要な施設 | 消防法 |
| 排煙設備 | 消火活動上必要な施設(※避難設備ではない) | 消防法 |
| 非常用照明装置 | 避難設備 | 建築基準法 |
◎自動火災報知設備の構成要素
| 機器名 | 役割 |
| 感知器 | 火災の発生を検知(熱・煙・炎) |
| 受信機 | 感知器からの信号を集め、表示・警報を出す |
| 中継器 | 電気信号の中継(大規模施設等) |
| 発信機 | 人が押して警報を発する(手動式) |
| ベル・表示灯 | 音と光で警報を知らせる装置 |
◎誤選択肢に注意!(正誤チェック)
| 誤り例 | 正しい内容 |
| 熱感知器は煙感知器より早期感知に適している | → × 煙感知器の方が早期感知に優れる |
| 炎感知器はマイクロ波の強度で感知する | → × 紫外線・赤外線(熱線)の強度で感知 |
| 排煙設備は「消防の用に供する設備」に該当しない | → × 消防法で定める消防の用に供する設備に含まれる |
| 自動火災報知設備は「避難設備」に分類される | → × 警報設備に分類される(避難設備ではない) |
◎構造耐力上主要な部分と主要構造部の違い
| 区分 | 含まれる部材 | 備考 |
| 構造耐力上主要な部分 | 壁・柱・床・梁・屋根・階段 | 建築基準法で定義される。構造上重要な部分 |
| 主要構造部 | 壁・柱・小屋組・土台・斜材・床版・屋根版・横架材 | 構造区分により耐火性能などで規制あり |
| ※含まれない部材 | 基礎・基礎ぐい・屋外階段 | → 主要構造部ではない! |
◎特殊建築物の分類
| 特殊建築物(例) |
| 学校・病院・劇場・百貨店・旅館・共同住宅・寄宿舎・工場・倉庫・自動車車庫など |
| 特殊建築物に該当しないもの(例) |
| 一戸建住宅、事務所、警察署、消防署など |
◎建築設備と非対象設備の分類
| 建築設備に含まれるもの |
| 電気・ガス・給排水・換気・冷暖房・消火・排煙・汚物処理・煙突・昇降機・避雷針(20m超) |
| 建築設備に含まれないもの |
| テレビ共聴設備・共同アンテナ・防犯設備 |
◎定期検査・建築士・申請関連
| 項目 | 内容 |
| 特殊建築物の定期調査者 | 一級建築士 or 二級建築士 |
| 報告先 | 特定行政庁(国土交通大臣ではない!) |
| 一級建築士免許 | 国土交通大臣 |
| 二級建築士免許 | 都道府県知事 |
| 建築確認の確認済証交付者 | 建築主事(指定確認検査機関ではない) |
| 建築基準法の目的 | 建築物の敷地・構造・設備・用途等に関する最低基準の確保 |
| 集団規定 | 安全・防火・避難・衛生等に関する技術的基準の総称 |
◎避雷針・非常用照明など
| 項目 | 内容・法令根拠 |
| 避雷針設置義務 | 高さ15m超の建築物に原則必要(建築基準法) |
| 非常用照明 | 床面照度21ルクス以上の蛍光灯が必要 |
| 病院の病室 | 非常用照明の免除対象ではない → 誤選択肢注意! |
◎誤選択肢パターンと正誤ポイント
| 誤った記述例 | 正しい内容 |
| 特殊建築物の定期検査の報告先は国土交通大臣である | → 特定行政庁 |
| 基礎・基礎ぐいは主要構造部である | → × 構造耐力上主要な部分には含まれない |
| 非常用照明は病室では免除される | → × 病室でも非常用照明は原則必要 |
| 建築確認済証を交付できるのは指定確認検査機関である | → × 建築主事のみが交付可能 |
| 自動火災報知設備は避難設備に分類される | → × 警報設備に分類される(消防法) |
◎建築基準法における基本用語の定義
| 用語 | 定義・ポイント |
| 建築物 | 土地に定着し、屋根および柱または壁を有する工作物 |
| 建築 | 新築・増築・改築・移転をいう(→「修繕・模様替」は含まれない) |
| 新築 | 建物が存在しない土地に建築物をつくること |
| 増築 | 既存建築物の床面積を増加させること |
| 改築 | 一部除却して、用途・規模・構造が大きく変わらない建物に建て替える |
| 移転 | 同一敷地内で建物を移動する(別敷地は誤り) |
| 居室 | 居住・執務など継続的に使用する室(※廊下・階段は含まれない) |
| 基礎ぐい | 構造耐力上主要な部分ではない(※主要構造部にも該当しない) |
| 屋外階段 | 主要構造部に含まれない(試験での誤選択肢に注意) |
◎床面積・容積率など建築関連指標
| 用語 | 定義 |
| 床面積 | 各階またはその一部で、壁などの中心線で囲まれた水平投影面積 |
| 延床面積 | 地階や屋階を含めた全階の床面積の合計 |
| 容積率 | 延床面積 ÷ 敷地面積 × 100%(建ぺい率と混同しないこと) |
| 敷地 | 一の建築物または用途上不可分の複数建物のある一団の土地 |
| 耐火性能 | 通常の火災中、倒壊や延焼を防止するための建物の性能 |
| 防火性能 | 周囲からの火災による延焼抑制を目的とした外壁・軒裏等の性能 |
| 延焼のおそれ | 1階→道路中心線から3m以内2階以上→外壁間が5m以内の部分 |
◎建築設備に関する用語と事業モデル
| 用語 | 説明・内容 |
| 建築設備 | 電気・ガス・給排水・換気・冷暖房・排煙・消火・昇降機・避雷針など |
| 建築設備外 | 共同アンテナ、防犯設備、TV共聴設備は含まれない |
| BEMS | ビルエネルギー管理システム(中央監視+省エネ) |
| CASBEE | 建築環境総合性能評価システム(エネ消費・資源循環・室内環境等) |
| ESCO事業 | 省エネの成果から報酬を得るサービス事業者 |
| シェアードセービング | 顧客が投資→ESCOが省エネ効果を保証 |
| コージェネレーション | 発電と同時に排熱も活用できるエネルギーの高効率利用方式 |
◎防災・避難・震災対策関連用語
| 用語 | 内容・ポイント |
| 防災管理者 | 地震等の被害軽減のため選任される責任者 |
| 誘導灯 | 点灯継続時間60分が必要 |
| 非常用照明装置 | 蛍光灯やLEDで床面2ルクス以上を確保 |
| 非常照明免除対象 | 病室・寄宿舎の寝室・学校などは免除可 |
| 火災荷重 | 建物内の可燃物量を木材換算した床面積あたりの重量(→単位容積ではない!) |
| 加圧防煙方式 | 長時間の安全確保が必要なエリアに使う(例:制御室など) |
| サンクンガーデン | 雨水対策・一時貯留空間(都市の水害対応策) |
◎誤選択肢に注意する重要ポイント
| 誤った記述例 | 正しい内容 |
| 移転は他の敷地への建物移動を指す | → × 移転は同一敷地内での移動のみ |
| 火災荷重は単位容積あたりの可燃物量をいう | → × 単位面積あたりの重量が正しい |
| 主要構造部に基礎や屋外階段が含まれる | → × 含まれない |
| 居室には廊下や階段も含まれる | → × 継続使用する居住・執務室のみが居室 |
| マグニチュードが1上がるとエネルギーは約10倍になる | → × 約32倍になる |
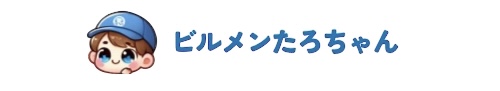

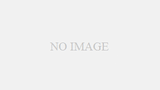
コメント