単位一覧
| 項目 | 単位 | 備考 |
| 水の比熱 | J/(g·°C) | 「1/°C」は誤り。J/(g·°C)などが正確。 |
| 水の比体積 | m³/kg | 「kg/m引」は誤り。逆数のm³/kgが正しい。 |
| 浮遊物質量 | mg/L | 水1L中の浮遊物質の質量 |
| BOD負荷量 | g/人・日 | 一人あたり1日あたりのBOD量 |
| 線膨張係数 | 1/°C | 温度1°Cあたりの長さの変化割合 |
| 水槽内照度率 | cd | 「cd」は光度の単位 |
| 腐食速度 | mm/年 | 年あたりの腐食深さ |
| 揚水ポンプの揚程 | m | 「m³/h」は流量の単位。揚程の単位は「m」 |
用語解説(箇条書き)
・絶対圧力:大気圧を基準とした圧力。真空を基準にした圧力ともいう。
・ウォータハンマ:急激なバルブ開閉などにより管内の水流が急停止し、圧力波が発生する現象。
・逆サイホン作用:給水管内の正圧により、吐水された水が給水管内に逆流する現象。
・逆サイホン作用の防止:基本的には吐水口空間(エアギャップ)を設けることで対策する。
・バキュームブレーカ:給水管の負圧状態を解消し、空気を導入して逆流を防止する装置。
・逆止弁:一方向にのみ流体を流すバルブ。逆流を防止する。
・ボールタップ:受水槽や便器などの水位調節に用いるフロート付きの止水装置。
・ダイレクトリターン方式:循環配管において、全ての経路で往復配管長がほぼ等しい方式。
・インバータ制御:モーターの回転数を制御し、必要な出力に応じて省エネを図る制御方式。
・着色障害:主に配管の腐食生成物が水に溶け込み、色がつく水質障害。
・トリハロメタン:消毒用塩素と有機物が反応してできる発がん性が懸念される物質。
・金属の不動態化:金属表面に酸化被膜が形成され、腐食しにくくなる現象。
・バルキング:汚泥が膨張し、沈降性が低下する現象。処理性能が悪化する。
・バイオフィルム:微生物が表面に形成する薄膜。管内に付着してスライム化することも。
・富栄養化:窒素やリンなどが過剰に供給されることで藻類などが異常繁殖し、水質が悪化する現象。
・クロスコネクション:飲料水系統と非飲料系統が直接接続され、汚染の危険がある状態。
水道の分類(法的定義と基準)
| 区分 | 内容・定義 | 主な基準 |
| 水道事業 | 一般の需要に応じて水道によって水を供給する事業 | 計画給水人口 101人以上 |
| 上水道事業 | 水道事業のうち、規模が大きいもの | 計画給水人口 5,001人以上 |
| 簡易水道事業 | 水道事業のうち、比較的小規模なもの | 計画給水人口 101人以上5,000人以下 |
| 水道用水供給事業 | 水道水を供給するが、実際の配水は他の事業者が行う | 他事業者に用水を供給 |
| 専用水道 | 自家用水道等で一定以上の居住者や給水量に対応 | ・100人超の居住用・最大給水量 20m³/日超(※条件いずれか) |
| 簡易専用水道 | 水道事業の水のみを水源とし、一定以上の水槽を有する施設 | 有効容量合計が10m³超の水槽 |
| 貯水槽水道 | 上記以外の水道水を一時的に貯水して供給する設備 | 水槽容量10m³以下が目安 |
用語と補足(箇条書き)
・計画給水人口:水道計画上、サービス対象として見積もる人口。
・専用水道の基準はかつて「50人超」「10m³/日超」だったが、現在は「100人超」「20m³/日超」が最新基準(2020年改正)。
・簡易専用水道は、水道事業の水を水源としており、水槽容量が10m³を超えるかどうかで区別される。
・貯水槽水道との違いは、水槽容量と届け出義務の有無。簡易専用水道は管理基準対象。
【塩素消毒に関するポイント】
| 項目 | 内容 |
| 塩素の作用物質 | 次亜塩素酸(HOCl)・次亜塩素酸イオン(OCl⁻)が主成分 |
| 消毒効果が高い条件 | 弱酸性(pHが低い側)ほど効果が高く、温度が高いほど反応速度が速い |
| CT値 | 塩素濃度(C)×接触時間(T)の積(消毒効果の指標) |
| 残留塩素の測定 | DPD試薬を用い、反応により色が変化(※セミキノン中間体は誤記) |
| 発色の順序(DPD法) | 遊離残留塩素 → 結合残留塩素の順に発色する(記述に誤りあり) |
| 効果が低下する要因 | 懸濁物質の存在、窒素化合物との反応、原虫シストには効果が弱い |
| その他特徴 | ・異臭味の原因になる・残留確認や濃度測定がしやすい・災害時に有用 |
【建築物環境衛生管理基準における塩素基準】
| 項目 | 基準値・頻度 |
| 遊離残留塩素濃度(末端) | 0.2mg/L以上 |
| 検査頻度 | 1ヶ月以内ごとに1回 |
【水質基準(代表例)】
| 項目 | 基準値 |
| 大腸菌 | 1mLあたり不検出(集落形成数 0) |
| 鉛及びその化合物 | 0.01mg/L以下(※0.1ではない) |
| 総トリハロメタン | 0.1mg/L以下 |
| 銅及びその化合物 | 1.0mg/L以下(※0.1ではない) |
| 濁度 | 5度以下(0ではない) |
| 硬度(Ca・Mg) | 10mg/L以上~100mg/L程度が望ましい(明確な法基準なし) |
| 塩化物イオン | 200mg/L以下 |
| ホルムアルデヒド | 0.08mg/L以下 |
| pH値 | 5.8以上~8.6以下 |
| 色度 | 5度以下 |
補足事項(正誤ポイント)
・DPD法では「遊離残留塩素」が先に発色 → 記述の「結合型が先」は誤り
・鉛の基準値は0.01mg/L以下 → 記述の「0.1」は誤り
・銅の基準値は1.0mg/L以下 → 記述の「0.1」は誤り
・濁度は0ではなく、5度以下 → 「0であること」は誤り
【水道施設の流れと主な役割】
| 区分 | 施設名 | 主な役割・ポイント |
| 1. 取水 | 取水施設 | ・水源から水を取り入れる施設・水量・水質の変動が少ない伏流水や地下水が好ましい |
| 2. 導水 | 導水施設 | ・取水施設と浄水施設を結ぶ施設 |
| 3. 浄水 | 浄水施設 | ・一般的に「沈殿 → ろ過 → 消毒」の処理・清澄な地下水は消毒のみで供給もある |
| 4. 送水 | 送水施設 | ・浄水施設から配水施設へ浄水を送る(※導水施設と混同注意) |
| 5. 配水 | 配水施設 | ・浄水を配るための中継施設(配水池など)・必要容量は「12時間分」が正解! |
| 6. 給水 | 給水装置 | ・配水管から需要者の建物内へ水を引き込む装置・給水管と直結する給水用具も含む |
【試験で出るひっかけポイント】
| 正しい記述 | よくある誤記・引っかけ |
| 配水池の必要容量:12時間分 | × 8時間分とされる場合が多い(過去問に多い) |
| 最小動水圧:150kPa以上 | × 「150kPa以下」などの引っかけに注意 |
| 浄水処理:一般に沈殿 → ろ過(急速4~5m/日) | |
| 地表水は水量・水質の変動が大きい | 伏流水や深層地下水と比較されることが多い |
| 深層地下水:汚染受けにくく、水質は安定している | ※「腐食もない」は誤り。腐食することがある |
【給水装置の定義(法的視点)】
| 法的定義 | 内容 |
| 給水装置(水道法) | ・水道事業者の配水管から分岐し設けられた給水管・末端の給水栓までを含む |
| 給水装置(実務表現・簡易版) | ・配水管から分岐して設けられた給水管及び直結する給水用具を含む |
【補足:ろ過の種類】
・急速ろ過法:一般的な浄水処理で使われる。4~5m/日の速度。
・緩速ろ過法:処理速度が遅く(0.1~0.2m/日)、自然浄化に近いが、大面積が必要。
【飲料水の水質基準(代表項目)】
| 項目 | 基準値・条件 |
| 遊離残留塩素 | 0.1mg/L以上(汚染のおそれがある場合は0.2mg/L以上) |
| 結合残留塩素 | 0.4mg/L以上(汚染のおそれがある場合は1.5mg/L以上) |
| 一般細菌 | 1mL中の集落形成数100以下 |
| 大腸菌 | 検出されないこと |
| pH値 | 5.8以上8.6以下 |
| 臭気・味 | 異常でないこと |
| 色度 | 5度以下 |
| 濁度 | 2度以下 |
| 有機物(TOC) | 3.0mg/L以下 |
| 銅 | 1.0mg/L以下 |
| 鉄 | 0.3mg/L以下 |
| 総トリハロメタン | 0.1mg/L以下 |
| 鉛・ヒ素 | 各0.01mg/L以下 |
| 硬度(Ca・Mg) | 300mg/L以下(カルシウム・マグネシウムの合算) |
| 塩化物イオン | 200mg/L以下 |
【水質検査・測定頻度】
| 検査内容 | 頻度 |
| 遊離残留塩素の検査(給水栓末端) | 7日以内ごとに1回 |
| 建築物衛生法に基づく16項目の水質検査 | 6か月ごとに1回 |
| 直結給水方式(特定建築物)の定期検査 | 不要(水道水を直結給水する場合) |
【設計給水量の目安】
| 利用施設 | 給水量(1日あたり) |
| 事務所 | 60~100L/人(節水器具あり:40~60L) |
| ホテル | 350~450L/床 |
| 戸建住宅 | 300~400L/人 |
| 総合病院 | 1500~3500L/床 |
| 小学校 | 70~100L/人(A:児童数) |
| デパート | 15~30L/m² |
| 社員食堂 | 25~50L/食 |
【給水圧・給水装置関連】
| 項目 | 数値 |
| ゾーニング時の上限給水圧力(住宅) | 0.3MPa以下 |
| ゾーニング時の上限給水圧力(商業) | 0.5MPa以下 |
| 最低必要水圧(小便器・大便器) | 70kPa |
| 一般水栓 | 30kPa |
| ガス湯沸器(4~5号) | 40kPa |
| ガス湯沸器(7~10号) | 50kPa |
| ガス湯沸器(22~30号) | 80kPa |
| 配管内流速 | 0.9~1.2m/s以上、2.0m/s以下 |
【洗浄水量(節水基準)】
| 器具 | I型(旧) | I型(新) |
| 大便器 | 8.5L以下 | 6.5L以下 |
| 小便器 | 4.0L以下 | 2.0L以下 |
【ひっかけ注意ポイント】
・残留塩素の基準値は“最低値”に注意(特に病原生物汚染時)
・濁度は2度以下(「0であること」などに引っかからない)
・硬度の上限は300mg/L以下(軟水~中程度が望ましい)
・給水栓末端での測定が原則である点を問われやすい
【受水槽の構造・設置に関する基準】
| 項目 | 内容・基準 |
| 貯水槽の設置位置 | ・底以外の五面点検可能にする・壁面・床面と60cm以上の空間を確保 |
| 屋内設置の注意点 | ・構造体との兼用不可(底以外)・上部スラブと天板の間も60cm以上 |
| マンホールの蓋 | 防水・密閉・施錠可能であること |
| 通気管の設置 | 有効容量2m³以上の貯水槽には必要 |
| 水抜き管 | 保守点検を容易にするため設置が必要 |
| オーバーフロー管との接続 | 水抜き管と接続してはならない |
| 流入・流出口の位置 | 離すのが望ましい(※「近い方が良い」は誤り) |
| 配管上の制限 | 機械室等では、飲料水・空調配管以外の設置不可 |
| ボールタップの波立ち対策 | 流入管は波立ち防止策を講じること |
| ポンプ接続部 | 受水槽とポンプの間には伸縮継手を使用 |
| 揚水ポンプ電極 | 揚水制御のため電極棒を設置 |
| 少量用水制御 | 使用量が少ない場合水位切替制御付き電極棒を使用 |
【貯水槽清掃・消毒・水質検査】
| 項目 | 内容・基準 |
| 消毒方法 | 次亜塩素酸ナトリウム(5~10mg/L)を使用し2回以上消毒 |
| 消毒後の水張り | 15分以上経過してから実施 |
| 高置水槽と受水槽の清掃順 | 別日に実施。受水槽 → 高置水槽の順で行う |
| 水質基準(残留塩素) | 給水栓で0.1mg/L(=100ppm)以上の遊離残留塩素を確認 |
| 測定法 | DPD法を使用 |
| 水質基準(濁度) | 5度以下 |
| 清掃作業員の健康診断 | おおむね1年ごとに健康診断を受けること |
【覚えておきたいひっかけ注意ポイント】
| 正しい知識 | よくある誤り・注意事項 |
| 水抜き管とオーバーフロー管は接続不可 | × 接続可とする記述は誤り |
| 流入口と流出口は離すべき | ×「近い方が良い」とする記述は誤り |
| 清掃消毒には塩素濃度5~10mg/Lを使用 | × 1mg/L や 0.5mg/L では不十分 |
| 清掃後の水質確認は残留塩素と濁度 | × どちらか一方だけでは不十分 |
【給水設備に関する用語・現象一覧】
| 用語 | 内容・現象の概要 | 原因・防止策など |
| ウォータハンマ | 急閉弁操作により生じる圧力波(衝撃) | 【原因】シングルレバー混合水栓の急閉など【防止】吸収式逆止弁設置 |
| クロスコネクション | 飲料水系と他系統(冷却水・雑用水など)を直接接続 | 汚染リスクが高いため、構造上の分離が重要 |
| 逆サイホン作用 | 給水管内の負圧により、水が逆流する現象 | 【防止】吐水口空間(空間の垂直距離)を設ける |
| クリープ変形 | 合成樹脂管に長時間熱応力がかかると、変形が進行する現象 | 時間とともに形状が変わるため、適切な支持と耐熱設計が必要 |
| 青水(銅イオンの浸出) | 銅管内部から銅イオンが溶出し、水が青く見える現象 | 長時間滞留、pHなどに注意 |
| 白濁水(亜鉛の溶出) | 亜鉛メッキ鋼管などから亜鉛が溶出し水が白く濁る | 換水や材質選定が重要 |
| 孔食(ピンホール腐食) | 銅管やステンレス管内壁に**小さな穴(腐食孔)**ができる | 【防止】内部清掃の徹底、設計時に異物混入を防ぐ |
| トリハロメタン | 有機物と塩素(消毒剤)が反応して生成される有害物質 | 消毒副生成物。水質管理が重要 |
| さや管ヘッダー工法 | 各器具に独立した給水配管を設ける集合住宅向けの分岐方式 | 保守が容易、リフォームにも適応しやすい |
| 大気圧式バキュームブレーカ | 圧力がかからない/一時的にかかる配管用(主に大便器) | 負圧時に空気を吸い込み逆流を防止 |
| 圧力式バキュームブレーカ | 常時圧力がかかるが、逆圧はかからない配管用 | 常時加圧部でも使用可能 |
| 専用洗浄弁式 | タンクのないタンクレストイレに使用される洗浄方式 | 水圧で直接洗浄 |
| 吐水口空間 | 吐水口と洗面器あふれ縁との垂直距離。逆流防止のため空間を設ける | 逆サイホン作用防止の基本構造 |
| 可とう継手 | 配管の揺れ、地盤沈下、振動吸収などに対応するための継手 | 伸縮継手、ショックアブソーバなどが該当 |
| ショックアブソーバ | ウォータハンマ対策として設置する減衝装置 | 急激な水圧変動を吸収 |
【覚えておきたい試験対策ポイント】
・吐水口空間:洗面器のあふれ縁との垂直距離。数字ではなく構造に注目される。
・ウォータハンマ防止:吸収式逆止弁やショックアブソーバで対策。
・バキュームブレーカの種類:圧力条件により大気圧式/圧力式を使い分け。
・クロスコネクションの例:消防水系や冷却水との直結配管は原則NG。
・可とう継手は「不同沈下」などの吸収にも使う:伸縮対応と混同しないよう注意。
【給水方式の分類と特徴】
| 給水方式 | 概要・特徴 | 注意点・適用例 |
| 直結直圧方式 | 配水管の水圧で直接給水。受水槽なし | 経済的ではないが水質汚染のリスクが最も低い |
| 直結増圧方式 | 増圧ポンプユニットで水圧を高めて中層建築物などにも対応可能 | 引込管径に制限あり、受水槽は不要 |
| 高置水槽方式 | 受水槽→ポンプ→高置水槽→自然流下で給水。安定した圧力・量が得られる | 水質汚染のリスクが比較的高い、配管勾配と横引き長さに注意 |
| 圧力水槽方式 | ポンプで水と空気を加圧する圧力水槽を使い、そこから給水 | 空気圧利用、貯水と加圧を兼ねる |
| ポンプ直送方式 | 受水槽からポンプで直接給水。ポンプ停止時に負圧の危険あり | インバータ制御などで圧力変動対策 |
【給水設備に関する数値まとめ】
| 項目 | 数値・基準 |
| シャワー・水栓・便器の必要水圧 | 30kPa(一般)、ガス湯沸器は20kPa |
| 給水管内流速 | 0.9~1.2m/s(最大:2.0m/s以下) |
| 受水槽容量 | 1日最大使用水量の1/5程度 |
| 高置水槽容量 | 1日最大使用水量の1/10 |
| ゾーニング時の上限給水圧力 | ホテル・住宅:0.3MPa以下事務所:0.5MPa以下 |
【設計給水量の目安】
| 建築物・用途 | 給水量の目安 |
| ホテル | 350~450L/床 |
| 事務所 | 30~50L/人(40~60Lという記述もある) |
| デパート | 15~30L/m² |
【配管材料・接合方法まとめ】
| 材料・部材 | 接合方法・特徴 |
| SGP管(炭素鋼管) | 使用不可(腐食あり)※亜鉛メッキ付きなら使用可 |
| 合成樹脂ライニング鋼管 | 管端防食継手でねじ接合 |
| 銅管 | 一般に差込ろう接合※銅イオン溶出→赤水の可能性 |
| ステンレス鋼管 | メカニカル継手またはTIG溶接 |
| 硬質ポリ塩化ビニル管(VP) | 一般に融着接合 |
| ポリブテン管・架橋ポリエチレン管 | 接着接合 |
【腐食・水質トラブル】
・異種金属の接続:電位差が小さいほど腐食電流が大きくなり、腐食速度が上がる
・銅管:銅イオンが溶出→青水や赤水の原因
・空気混入:白濁水の原因になる
・クリープ劣化:合成樹脂管に熱応力がかかり、時間と共に変形進行
【弁類の機能と特徴】
| 弁の種類 | 主な機能・特徴 | 注意点・補足 |
| 仕切弁 | 開閉動作のみ。流量調整には不向き | →「流量調整が可能」は誤り |
| 玉形弁 | 流量調整に適する(S字状流路、途中開閉OK) | 弁体を中間開度で使用可 |
| 電磁弁 | 遠隔操作が可能。ウォータハンマが発生しやすい | →「発生しにくい」は誤り |
| バタフライ弁 | 円板型弁体を回転して開閉する | 大口径配管に使用される |
| 減圧弁 | ダイヤフラムとバネで下流圧力を一定に保つ | 圧力調整機能あり |
| 定水位弁 | 副弁と主弁が連動し、水槽の水位制御 | 給水ポンプと連動するケースも |
| ボール弁 | 球状の弁体で開閉。流路全開・全閉が基本 | 小型・シンプルで水栓などに多用 |
| 逆止弁 | 一方向のみ流体を通し逆流を防止 | 分岐点・ポンプ吐出側に設置 |
| 空気抜き弁 | 配管内の空気の排出 | 配管頂部や凸部に設置 |
| 吸排気弁 | 空気の出入り両方に対応。負圧時の逆流防止にも有効 | 特に長大配管に使用 |
| ウォータハンマ防止器 | 急閉止弁から十分離れた位置に設置が必要 | 近すぎると器具が破損する恐れあり |
【止水弁に関する注意事項】
・フランジ型:取外しが必要な機器の前後に設置
・点検口:天井内に止水弁を設ける場合、近傍に点検口を設けること
・名称札:止水弁には系統名の表示を設ける
・設置場所:主管からの分岐部、各階の起点、機器接続部など
【貯水槽の材質と特徴】
| 材質 | 特徴・注意点 |
| 木製貯水槽 | 正方形限定、断熱性能が低く結露しやすい |
| ステンレス鋼板製 | 気相部(空気に触れる部分)の腐食対策が必要 |
| FRP製 | 紫外線に強いが、耐震補強は必要(→不要は誤り) |
| FRP複合板パネル | 断熱性に優れるが、結露しやすい |
| 鋼板製 | 毎年の防錆処理被膜の点検が必要 |
【配管に関する注意点・構造】
・先上り配管:上向き配管方式
・先下り配管:下向き配管方式
・分岐方法:上方は上取出し、下方は下取出し
・埋設時:給水管は排水管の上に埋設する
・ポンプ配管:荷重がかからないよう支持を設ける
・機器接続部:フランジ接合などで容易に取り外しできる構造に
・識別:飲料水系統は他の配管と明確に識別する
【配管材料・接合方法】
| 材料 | 主な接合方法 |
| 合成樹脂ライニング鋼管 | ねじ接合(管端防食継手)、フランジ接合 |
| 銅管 | 差込ろう接合 |
| ステンレス鋼管 | TIG溶接、メカニカル接合、フランジ接合 |
| 架橋ポリエチレン管・ポリブテン管 | メカニカル接合、融着接合、接着接合 |
| 硬質ポリ塩化ビニル管(VP) | 接着接合 |
【ポンプの種類と保守点検】
| ポンプ種別 | 使用場所/方式 |
| 揚水ポンプ | 高置水槽方式 |
| 給水ポンプ | 圧力水槽方式 |
| 加圧ポンプ | ポンプ直送方式 |
| 増圧ポンプ | 直結増圧方式 |
【保守点検頻度】
| 項目 | 頻度 | 内容 |
| 毎日点検 | 毎日 | 圧力、流量、電圧、振動・水滴・音など |
| 月1点検 | 月1回 | 温度、絶縁抵抗の測定 |
| 半年点検 | 6か月に1回 | 芯ずれ、基礎のゆがみ確認 |
| 分解点検 | 3~5年に1回 | 内部の分解・消耗部品の点検 |
【貯水槽の材質と特徴】
| 材質 | 特徴・注意点 |
| 木製貯水槽 | ×「断熱性に優れる」は誤り。断熱性が低く、結露対策が必要円形・楕円形限定。搬入・組立は容易 |
| ステンレス鋼板製 | 塩素イオンに弱く、気相部の腐食対策が必要強度・軽量・耐食性に優れる |
| FRP製貯水槽 | 軽量・耐食・断熱性に優れるが、紫外線や衝撃に弱く、耐震補強が必要照度100lx以上で藻類繁殖 |
| 鋼板製貯水槽 | FRPより強度が高いが、防錆処理が必須。防錆塗装の剥離に注意 |
【貯水槽の設置位置・構造基準】
| 項目 | 基準・ポイント |
| 六面点検 | 飲料用貯水槽は六面点検可能にする |
| 点検スペース | 下・周囲60cm以上、上部100cm以上確保 |
| 防護策 | 屋外・独立室:施錠・フェンスを設ける |
| 他設備設置 | 貯水槽の上部に他設備や配管の設置不可 |
| 流入口吐水口 | 吐水口空間を設ける(×水没させる → 誤り!) |
| 流入口・出口 | 対角線配置で滞留防止 |
| 水抜き管 | 最も低い位置から単独で設置。防虫網は× |
| オーバーフロー管 | 防虫網設置可、開口面積は管断面積以上 |
| 通気管 | 容量2m³以上で水密性ある取付部に通気管設置 |
【貯水槽 清掃・水質管理】
| 内容 | 頻度・基準 |
| 清掃 | 1年に1回定期実施 |
| 清掃作業者の健康診断 | 6か月ごとに実施 |
| 消毒(塩素) | 有効塩素濃度50~100mg/L、2回以上消毒 |
| 水張り・水洗い | 消毒後、30分経過してから実施 |
| 清掃順 | 原則同日実施:受水槽 → 高置水槽 → 圧力水槽の順 |
| 清掃後の残留塩素基準 | 遊離:0.2mg/L以上結合:1.5mg/L以上 |
| 臭気・味・色度・濁度 | 異常なし、色度5度以下、濁度2度以下 |
【圧力水槽の検査周期】
| 区分 | 定期自主検査 | 性能検査 |
| 第一種圧力容器 | 1か月以内ごとに1回 | 1年以内ごとに1回 |
| 第二種圧力容器 | 1年以内ごとに1回 | 不要 |
【水質・薬剤管理】
・DPD法:遊離残留塩素の一般的な測定方法
・残留塩素の検査:7日以内ごとに1回
・防錆剤の濃度検査:定常時に2か月以内ごとに1回
・防錆剤の管理者:建築物衛生法に基づく登録者が管理
・水質基準超過時:給水停止措置を直ちに行うこと
【給湯設備:設計湯量の目安】
| 用途 | 設計湯量(1日あたり) |
| 事務所 | 7~10L/人 |
| ホテル宿泊部 | 150~250L/人 |
| 集合住宅 | 150~300L/戸 |
| 総合病院 | 150~200L/人 または 100~200L/床 |
| 飲食店 | 30~70L/m² または 16L/食 |
【電気温水器・給湯設備の種類と特徴】
| 項目 | 内容・ポイント |
| 電気温水器 | ・容量:60~480L程度・貯湯能力はあるが加熱能力は低い(小) |
| CEC/HW(エネルギー消費係数) | 年間給湯消費エネルギー量 ÷ 年間仮想給湯負荷 |
| ガスマルチ式給湯機 | 小型ガス瞬間湯沸器を複数台連結したユニット方式 |
| ヒートポンプ給湯機 | 一体型の熱源機と貯湯槽で構成。自然循環で加温 |
| 自然冷媒ヒートポンプ給湯機 | 最高沸き上げ温度:約90℃以下(多くは70~90℃) |
| 潜熱回収型給湯器 | 排気の潜熱で給水を予熱して効率向上 |
| ガス瞬間湯沸器の「1号」 | 1L/minの水を15℃上昇させる能力 |
| 貯蔵湯沸器 | 90℃以上の高温湯が得られる |
【給湯方式の分類と用途】
| 方式 | 特徴・用途 |
| 中央式給湯方式 | 一括で加熱・供給。給湯箇所が少ない事務所建築に適用 |
| 間接加熱方式 | 蒸気・高温水を熱交換器(加熱コイル)で給湯用水を加熱 |
| 局所給湯方式 | 各箇所に個別設置。単管式配管が基本 |
【給湯配管・材料に関するポイント】
| 材料・継手 | 特徴・注意点 |
| 金属材料の曲げ加工 | 応力腐食の原因になる |
| 給湯設備の腐食速度 | 給水より遅い(加熱でガス成分が抜け、酸素が減少) |
| 銅管(返湯管) | 流速を速く設定できる |
| ステンレス鋼管 | 線膨張係数が大きく、すき間腐食やもらいさびが起きる |
| 架橋ポリエチレン管 | 線膨張係数は銅管より大きい、温度上昇で許容圧力は低下 |
| 耐熱性硬質塩ビ管 | 使用温度は95℃以下 |
| スリーブ形伸縮継手 | ベローズ形に比べて伸縮吸収量が小さい |
| ベローズ形伸縮継手 | 疲労破壊による漏水のリスクあり |
| 単式伸縮継手の設置間隔 | 約50mごと |
| ポリプテン管 | 線膨張係数は銅管より大きい |
| 長い直線配管 | 可とう継手を設置して変位吸収 |
【給湯設計湯量の目安】
| 建築用途 | 設計湯量(1日あたり) |
| 総合病院 | 50~100L/床・日(記述の「50~1001」は誤字) |
| 集合住宅 | 300L/戸・日 |
| 事務所 | 7~10L/人 |
| ホテル宿泊部 | 150~250L/人 |
| 飲食店 | 30~70L/m² または 16L/食 |
【空気抜き・腐食関連】
・自動空気抜き弁は、圧力の高い位置に設置して溶存空気を排出
・塩素による劣化は、高温時の樹脂管に生じやすい
・線膨張係数(大きい順):ポリ管 > ステンレス管 > 銅管
・銅管の腐食:アノード=電流が水中に流れ込む側、カソード=逆
【湯の循環方式】
| 項目 | 内容・ポイント |
| 自然循環方式 | 熱の自然対流を利用(※配管形状が複雑な中央式には不向き→誤り注意) |
| 強制循環方式 | 循環ポンプを用いる。放熱量から循環水量を計算する |
| 循環ポンプの選定 | ・背圧に耐えることが必要・揚程は最も小さい摩擦損失から決定する |
| 設置位置 | 循環ポンプは給湯管に設置し、返湯管の圧力低下に応じて運転 |
| 流量の安定化 | 返湯管に定流量弁を設けて循環を均等化する |
| リバースリターン方式 | 湯を均等に循環させるための配管方式(配管長を揃える) |
| 厨房などの連続使用箇所 | 枝管に返湯管を設けないことが多い |
| 給湯配管の勾配 | 下向き配管の場合、1/100以上の下り勾配とする |
| 返湯管の材質と流速 | 銅管の場合、流速1.2m/s以下が望ましい |
| 単式配管の銅管腐食 | 循環なしの単式給湯配管の方が腐食リスクが高い |
| 気体の溶解度 | 水温上昇で溶解度は減少する(→「増加する」は誤り) |
【逃し弁・逃し管の取り扱い】
| 項目 | 内容・ポイント |
| 逃し管 | 緊急時用で、弁は設けない(常時開放) |
| 逃し弁 | 温度上昇時に作動。加熱時の膨張水を排水する排水管を設ける |
| 逃し管の取付位置 | 高置水槽の水面よりも低い位置から立ち上げる |
| 逃し弁は逃し管の代用可 | ○ 設備内容により適切に使い分ける |
【貯湯槽の構造・管理】
| 項目 | 内容・ポイント |
| 材質(SUS444) | 腐食対策として電気防食を施す |
| 温度基準 | ・常時60℃以上・ピーク時でも50℃以上を確保 |
| 容量設計 | ピーク時の必要湯量の0.5時間分を目安に加熱能力と調整 |
| 容量が小さい場合の影響 | 加熱装置の発停回数が多くなり、機器負荷が増大 |
| 第一種圧力容器(大容量) | 1年以内ごとに性能検査(労働安全衛生法) |
| 小型圧力容器 | 2年以内ごとに1回の定期自主検査を行う |
【ひっかけ注意ポイント】
| 誤記されやすい内容 | 正しい内容 |
| 自然循環方式は中央式に適している | × 不適。→強制循環方式が適している |
| 気体の溶解度は温度上昇で増加 | × 減少する(※炭酸や酸素は抜ける) |
| 逃し管に弁を設ける | × 設けない(常時開放が基本) |
| 循環ポンプの揚程は高く設定する | × 最も小さくなる摩擦損失から設定する |
【保守管理・定期点検】
| 対象 | 点検・管理内容 |
| 逃し弁 | 6か月ごとに手動レバー操作で作動確認 |
| 給湯循環ポンプ | 1年に1回分解・清掃し、作動確認 |
| 貯湯槽(休止後) | 再使用時には点検・清掃後、設定温度まで加熱して使用 |
| 真空式温水発生機 | 労働安全衛生法に基づく検査対象 |
| ワッシャ | 天然ゴムを使用(耐熱性に注意) |
【湯温・レジオネラ属菌対策】
| 項目 | 設定温度・対策内容 |
| 壁掛けシャワー | 42℃程度 |
| 厨房食器洗浄(すすぎ) | 70~90℃ |
| 中央式給湯の貯湯温度(常時) | 60℃以上 |
| ピーク時でも確保すべき湯温 | 55℃以上 |
| レジオネラ属菌対策 | ・中央式を推奨・高濃度塩素で一時消毒・50℃加熱循環処理も有効 |
【給湯設備の配管勾配】
| 配管方式 | 勾配基準 |
| 上向き配管方式 | 給湯横主管:1/200以上の上り勾配 |
| 下向き配管方式 | 給湯横主管:1/200以上の下り勾配 |
【循環ポンプ関連】
| 項目 | 内容・注意点 |
| 循環ポンプの設置位置 | 返湯管に設置(「給湯管に設置」は誤り) |
| 作動方式 | 返湯温度が低下したときに起動(連続運転はしない) |
| 揚程の設定基準 | 最も大きくなる摩擦損失から設定 |
| 流量の決定方法 | 加熱器の温度差に反比例/配管放熱量に比例 |
| 騒音対策(サイレンサ) | ポンプの吐出側に設置 |
| 配管方式 | リバースリターン方式は均等循環に不利 |
| 均等循環対策 | 返湯管に定流量弁を設置 |
| 返湯管の管径 | 給湯管の約1/2程度 |
【配管材料・使用温度・伸縮継手】
| 材料 | 使用温度上限 |
| 銅管・ステンレス鋼管 | ~90℃ |
| 耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管 | ~95℃ |
| 架橋ポリエチレン管 | ~95℃ |
| ポリブテン管 | ~95℃ |
| 耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管 | ~85℃ |
【線膨張係数:大きい順】
架橋ポリエチレン管 > ポリブテン管 > 硬質塩化ビニル管 > ステンレス鋼管 ≒ 銅管
【伸縮継手・設置間隔】
| 配管材・継手 | 設置間隔 | 備考 |
| ライニング鋼管(単式) | 30m程度 | |
| 銅管・ステンレス管 | 20m程度 | |
| ベローズ形伸縮継手 | 伸縮吸収量は少ない | |
| スリーブ形伸縮継手 | 伸縮吸収量は大きい |
【加熱装置の種類と特徴】
| 種類 | 特徴・備考 |
| ガス瞬間湯沸器 | ・1号=1.74kW(1L/minを25℃上昇)・セントラルヒーティング兼用型あり |
| 貯蔵式湯沸器 | ・開放式貯湯槽で90℃以上の高温湯が得られる・飲用可能 |
| 電気温水器 | ・加熱ヒーター、温度制御、密閉貯湯、逃し弁、減圧弁で構成 |
| 真空式温水発生器 | ・大気圧以下の缶体内で蒸気→湯を生成・労働安全衛生法の対象外 |
| 無圧式温水発生器 | ・開放容器構造、大気圧を超えない・大規模シャワーには不適 |
| 加熱コイル付き貯湯槽 | ・蒸気等の外熱源→加熱コイルで加温・第一種圧力容器に該当 |
| 太陽熱利用温水器 | ・集熱器と貯湯槽一体型。自然循環で加熱・排水熱利用は間接加熱に限る |
【直接加熱/間接加熱方式の違い】
| 分類 | 内容 |
| 直接加熱 | 水が直接熱源と接触(例:ガス瞬間湯沸器、電気温水器) |
| 間接加熱 | 加熱コイルなどを介して湯を加熱(例:加熱コイル付き貯湯槽) |
【圧力容器と検査周期】
| 種類 | 定期自主検査 | 性能検査 |
| 第一種圧力容器 | 1か月以内ごとに1回 | 1年以内ごとに1回 |
| 第二種圧力容器 | 1年以内ごとに1回 | なし |
| 小型圧力容器 | 1年以内ごとに1回 | なし |
【各種保守・清掃基準】
| 項目 | 内容・頻度 |
| 逃し弁の作動確認 | 1か月以内ごとに1回 |
| 循環ポンプの分解清掃 | 1年に1回以上 |
| 給湯配管の洗浄 | 1年に1回以上 |
| シャワーヘッドの点検 | 6か月ごとに1回 |
| シャワーヘッドの分解清掃 | 1年に1回以上 |
【その他の注意事項】
・SUS444製の貯湯槽 → 電気防食は施さない(NG)
・ワッシャ類 → 合成樹脂製が使用される(×天然ゴム)
・残留塩素検査は水温が常時55℃以上確保できれば省略可
・一般細菌基準超過時は、70℃以上の湯を循環させ加熱処理する
【電気防食の種類】
| 種類 | 特徴 |
| 流電陽極式 | 特性陽極あり(取替必要/外部電源不要) |
| 外部電源式 | 陽極の取替不要/外部電源が必要 |
【雑用水システムの種類】
| 種類 | 特徴・説明 |
| 個別循環方式 | 単一建築物内で雑用水を回収・処理して使用。下水道負荷軽減に有効 |
| 地区循環方式 | 複数の建築物で排水再利用設備を共同利用し、処理水を再配水 |
| 広域循環方式 | 公共下水処理場の処理水を再利用する。→下水道負荷の軽減効果はない |
【雑用水の用途ごとの使用条件】
| 用途 | 使用可能な原水 | 水質基準あり | 補足 |
| 水洗便所用水 | し尿を含む水も使用可 | pH・臭気・外観・大腸菌など | 濁度や温度基準なし |
| 散水・修景・清掃用水 | し尿含む水は使用不可 | pH・臭気・外観・大腸菌・濁度 | 濁度2度以下、透明で浮遊物なし |
※両方の用途で、一般細菌数の規定はなし。
【雑用水の水質基準(散水・修景等の場合)】
| 項目 | 基準値 | 検査頻度 |
| 遊離残留塩素 | 0.1mg/L以上(汚染おそれあり→0.2mg/L以上) | 7日以内ごとに1回 |
| 結合残留塩素 | 0.4mg/L以上(汚染おそれあり→1.5mg/L以上) | 7日以内ごとに1回 |
| pH値 | 5.8以上8.6以下 | |
| 臭気・外観 | 異常なし、ほぼ無色透明 | |
| 大腸菌 | 検出されないこと | |
| 濁度(※散水等用途) | 2度以下 | 2か月以内ごとに1回 |
【設備・配管上の注意点】
・雑用水は洗面器・手洗器に接続しないこと
・配管は飲料水系統と異なる色で塗装し、並列配列は変更不可
・雑用水使用水栓には**「飲用不可」等の表示が必要**
・竣工時に着色水で通水試験を行い、上水器具への混入がないか確認
・スライム発生時は残留塩素を高めて洗浄する
・活性炭処理法は臭気・色度の除去に適する
・**浮遊物質を含まないこと(外観基準)**が明示されている
【雑用水槽の設置・管理】
| 項目 | 内容 |
| 雑用水槽の防水処理 | コンクリート槽は合成樹脂防水モルタルなどで処理 |
| 飲料水補給時の措置 | 吐水口空間を設けて補給 |
| 雑用水受水槽の点検性 | 六面点検可能な設置が望ましい |
| 飲料水と雑用水の接続禁止 | 高置水槽同士をバイパス管で接続するのはNG |
| 清掃 | 容量・材質・水源に応じて定期的に実施 |
【塩素消毒の効果に影響する要因】
| 効果に影響する要因 | 備考 |
| 接触時間 | 長いほど有効 |
| 水温 | 高いほど反応が速い |
| 有機物量 | 多いと塩素が消費され効果が減少 |
| 藻類の繁殖 | 塩素が分解される場合がある |
| ※× 溶存酸素 | 塩素効果とは無関係(→誤り注意) |
【雨水利用率と上水代替率】
| 用語 | 定義 |
| 雨水利用率 | 雨水集水量に対する雨水利用量の割合= 雨水利用量 ÷ 雨水集水量 × 100% |
| 上水代替率 | 使用水量に対する雨水利用量の割合= 雨水利用量 ÷ 使用水量 × 100% |
※用語の「分母」に注意!(入れ替えて出題されがち)
【雨水利用設備の処理フロー】
集水 → スクリーン → (沈砂槽) → (沈殿槽) → 雨水貯留槽 → ろ過装置 or マイクロストレーナ → 消毒槽 → 利用
※ばっ気・生物処理・活性炭吸着装置は不要(×)
【単位装置の役割・点検】
| 装置 | 役割・点検ポイント |
| スクリーン | ごみ除去、スクリーン目詰まり確認 |
| 沈砂槽・沈殿槽 | 固形物・砂の沈殿、汚れ・蚊の発生状況の点検 |
| マイクロストレーナ | 細かい粒子除去、網の破損や洗浄装置の点検 |
| 雨水貯留槽 | 雨水を貯める、沈殿物の除去、汚れ・閉塞の確認 |
【雨水排水の設計ポイント】
| 項目 | 設計・基準 |
| 雨水ますの流出管 | 流入管より管底を20mm程度下げて設置 |
| 雨水ますの泥だめ | 150mm程度が標準 |
| ルーフドレンのストレーナ開口面積 | 接続する雨水管の2倍程度 |
| 雨水排水系統 | 単独系統として屋外へ排出(※排水立て管と兼用しない) |
| 雨水横主管の合流接続 | 排水立て管から3m以上離す |
【雨水浸透方式】
・透水性舗装や浸透枡を利用
・地下水涵養が目的
・× 下水道負荷軽減はしない(→ひっかけ注意)
【排水の水質・指標】
| 指標 | 意味・用途 |
| 透視度 | 水の透明度。浮遊物質と相関がある |
| BOD(生物化学的酸素要求量) | 有機物分解に必要な酸素量(※微生物による) |
| COD(化学的酸素要求量) | 酸化剤で有機物を分解するのに必要な酸素量(※BODより大きい) |
| BOD/COD 比 | 高い → 生物処理が有効低い → 物理化学処理が適する |
| ノルマルヘキサン抽出物質 | 油脂類(悪臭・処理機能低下の原因) |
| MISS | 活性汚泥中の浮遊物質 |
| 全窒素 | 有機性窒素・アンモニア性窒素の総和。富栄養化の原因 |
【排水再利用設備の処理フロー(雑用水用)】
集水 → スクリーン → (流量調整)→ 生物処理(活性汚泥/生物膜)→ 沈殿槽 → (ろ過)→ 消毒 → 雑用水槽 → 給水
※膜分離装置を使う場合:
膜分離活性汚泥処理(浸漬型MF膜)→ 活性炭 or オゾン処理 → 消毒
・膜は処理水と活性汚泥の分離用 ・ばっ気は酸素供給+膜表面洗浄の役割 ・膜の透過量低下防止には定期的洗浄が必要
【BOD・COD・水質指標】
| 指標 | 定義・特徴 |
| BOD | 生物化学的酸素要求量。有機物を好気性微生物が分解する際に消費される酸素量。 |
| COD | 化学的酸素要求量。酸化剤で有機物を分解する際に消費される酸素量。 |
| MLSS | 活性汚泥混合液浮遊物質。ばっ気槽内の微生物量の指標。 |
| DO | 溶存酸素。生物処理・放流水質評価に使用。 |
| 全窒素 | 有機・アンモニア性窒素の合計。富栄養化の原因物質。 |
| リン化合物 | 富栄養化の原因物質。 |
| 透視度 | 水の透明度。浮遊物と相関がある。 |
| ヘキサン抽出物質 | 油脂類(揮発しにくい)→悪臭・機能低下の原因。 |
| 汚泥容量指数(SVI) | 活性汚泥の沈降性の指標。バルキング現象の判定にも利用。 |
【排水設備用語・障害】
| 用語 | 内容 |
| スカム | 浄化槽・排水槽表面に浮いた固形物の集合体 |
| バルキング | 活性汚泥が沈降しにくくなる現象 |
| スライム障害 | 配管・装置内部に形成されたバイオフィルムで消毒効果が減少 |
| 不動態化 | 金属表面にできる酸化皮膜による腐食抑制 |
| スケール障害 | 硬度成分が析出して配管内閉塞や腐食を引き起こす |
| 誘導サイホン作用 | 管内圧力変動による封水の吸引・破封 |
【排水トラップ関連】
| 項目 | 内容・ポイント |
| 封水強度 | トラップが正圧・負圧にどれだけ耐えられるかの能力 |
| 独断面積比(出/入) | 大きいほど封水強度が高い |
| 共振現象 | トラップ内の水が圧力変動と共振して破封しやすくなる |
| 補給水装置 | 封水の蒸発による破封を防ぐため、使用頻度の少ない器具に設置 |
| 自作用 | 流下水流でトラップ内の異物を洗い流す作用 |
| 糸くず・毛髪の毛細管現象 | ウェア部で水が吸い上げられて封水が減少する原因 |
【排水勾配の基準(横管)】
| 管径 | 最小勾配 |
| 65mm以下 | 1/50 |
| 75~100mm | 1/100 |
| 125mm | 1/150 |
| 150~300mm | 1/200 |
※自然流下式では流速0.6~1.5m/sを目安に勾配設計。
【敷地内排水・下水道の分類】
| 種類 | 内容 |
| 敷地内排水 | 合流式(汚水+雑排水)/分流式(汚水・雑排水別) |
| 下水道 | 下水(汚水+雑排水+雨水)/汚水/雨水 |
| 流域下水道 | 都道府県が事業主体 |
| 公共下水道/都市下水路 | 市町村が管理 |
【間接排水の排水口空間】
| 間接排水管の管径 | 最小排水口空間 |
| 25mm以下 | 50mm以上 |
| 30~50mm | 100mm以上 |
| 65mm以上 | 150mm以上 |
| 飲料用貯水槽 | 150mm以上 |
・排水口空間=逆サイホン作用を防ぐために必須
・洗濯機は**簡易間接排水(開放式)**でも可
・人が触れる水受け容器では排水口開放NG
【間接排水の補足ポイント】
・間接排水管の配管長が1,500mmを超える場合、装置の近くにトラップを設置
・間接排水の目的は、飲料水汚染の防止(逆流防止)
【通気方式の比較】
| 通気方式 | 特徴・ポイント |
| 各個通気方式 | 各器具に個別通気管。トラップの2倍以上離して接続。 |
| ループ通気方式 | 器具排水管最上流のすぐ下流から通気立て管へ接続。 |
| 伸頂通気方式 | 排水立て管の最上部を通気管に接続。満流のおそれがある場合NG |
| 結合通気方式 | ブランチ間隔10以上の高層建築で、10以内ごとに設置。 |
・通気管の大気開口部 → 窓・換気口の600mm以上上方に開放
・通気口の開口面積比 → 100%以上(=通気率100%以上)
【掃除口の設置基準】
| 項目 | 基準 |
| 口径(100mm以下) | 配管と同径 |
| 口径(100mm超) | 最低でも100mm |
| 設置間隔(100mm以下) | 15m以内 |
| 設置間隔(100mm超) | 30m以内 |
| 保守用空間(65mm以下) | 300mm以上 |
| 保守用空間(75mm以上) | 450mm以上 |
| 床下掃除口 | 砲金製プラグを使用 |
| 曲がり角(45°超) | 掃除口の設置が必要 |
【排水ます・排水槽】
| 項目 | 基準・ポイント |
| 排水ますの設置間隔 | 管内径の120倍以内 |
| 排水槽の底部勾配 | 吸込みピットに向かって1/15以上1/10以下 |
| 排水槽マンホール | 内径600mm以上 |
| 排水ポンプの設置位置 | フート弁の直上 |
| 排水槽の悪臭防止 | タイマ制御で1~2時間以内に強制排水 |
| 清掃時のガス測定 | 酸素18%以上、硫化水素10ppm以下を確認 |
| 排水槽の清掃頻度 | 6か月以内に1回以上(建築物環境衛生管理基準) |
【ポンプの点検・管理】
| 点検項目 | 頻度 |
| 吸込側・吐出側の圧力 | 1カ月に1回 |
| 電動機の絶縁抵抗 | 1カ月に1回(1MΩ以上) |
| ポンプ各部の温度測定 | 1カ月に1回 |
| 軸受部の水滴の滴下状態 | 毎日 |
| 電流値 | 1週間に1回 |
| 芯狂いの点検 | 2年に1回程度 |
| 分解点検(給水ポンプ) | 3~5年に1回 |
【排水ポンプの種類と最小口径】
| 種類 | 用途 | 最小口径 |
| 汚水ポンプ | 固形物なし(雨水・湧水など) | 40mm |
| 雑排水ポンプ | 小さな固形物(厨房以外) | 50mm |
| 汚物ポンプ | 大きな固形物(トイレ・厨房) | 80mm |
・設置位置:吸込みピット壁面から200mm離す
【阻集器の種類と清掃基準】
| 種類 | 用途/清掃・点検内容 |
| グリース阻集器 | 厨房。7~10日に1回の油除去。底部は月1回高圧洗浄。2カ月ごとに清掃 |
| オイル阻集器 | ガソリンスタンドなど。屋内設置時は換気が必要 |
| 砂阻集器 | 泥だめ深さ150mm以上 |
| 繊維くず阻集器 | 金網目13mm程度のバスケットストレーナ使用 |
| プラスタ阻集器 | 歯科技工室での石膏・貴金属分離 |
| 毛髪阻集器 | 理髪店・浴場 |
【排水管の洗浄法】
| 方法名 | 特徴 |
| 高圧洗浄法 | 5~30MPaの高圧水で洗浄 |
| ロッド法 | 1~1.8mのロッドをつないで手動洗浄(最大30m) |
| スネークワイヤ法 | ワイヤを排水管に挿入し、回転させて洗浄 |
| ウォータラム法 | 圧縮空気の衝撃で閉塞物を除去 |
| 化学的洗浄法 | 有機物→アルカリ洗剤/小便器の石→酸性洗剤 |
【排水トラップ・封水】
| 用語 | 内容・補足 |
| 封水深(一般) | 100~200mmが一般的 |
| 封水強度 | トラップが蒸発・吸引などにどれだけ耐えられるかの能力 |
| 脚断面積比(出/入) | 比が大きいほど封水強度が小さくなる |
| ドラムトラップ | 実験用など。サイホン式で封水切れやすい |
| 排水トラップの深さ | ディップからウェアまでの垂直距離 |
【排水管・敷地内排水設備】
| 項目・用語 | ポイント・規定内容 |
| 分流式排水方式 | 汚水と雑排水を別々の系統で排除する |
| 自然流下方式の排水横管勾配 | 管内流速 0.6~1.5m/s となるように設ける |
| オフセット部制限 | オフセット上下 800mm以内に排水横枝管はNG(600mmと混同注意) |
| 管径100mm横管の最小勾配 | 1/150 |
| 掃除口の口径 | 排水管径100mm以下→同一径 |
| 掃除口の設置間隔 | 管径100mm以下→15m以内 |
| 45°超の方向転換部 | 掃除口を設置する |
| 凍結対策 | 寒冷地では凍結深度より深く埋設する(浅くではない) |
| 合流式でのトラップます | 一般にトラップますを設ける |
| 排水ますの設置基準 | 管径の120倍以内 |
| 特殊継手排水システム | 接続器具が少ない系統(ビル客室・集合住宅)向け |
【排水槽・汚水槽】
| 項目・用語 | ポイント・規定内容 |
| マンホール内寸 | 直径45cm以上の円が内接できること(≒有効内径600mm) |
| マンホールの位置 | 排水ポンプ or フート弁の直上に設置 |
| 排水槽底部の勾配 | 吸込みピットに向けて 1/150~1/100 |
| 階段の設置 | 点検歩行用に設けてもよい |
| 排水ポンプの設置距離 | 壁面から200mm以上離す |
| ポンプの台数 | 原則2台(常用+予備) |
| 自動運転用水位センサ | 汚水槽:フロートスイッチ使用 |
| 厨房排水槽の水位制御 | 電極棒が適当 |
| 湧水槽の用途 | 湧水のみを流入させる(他はNG) |
| 雑排水ポンプ | 厨房排水を含まない(汚物ポンプが対応) |
| ばっ気と空気管理 | ばっ気により正圧になるため排気が必要 |
■ 通気管の要点
・各個通気方式:自己サイホン防止に有効(排水横枝管に接続された衛生器具)
・伸頂通気方式:排水横主管以降が満流となる場合は使用不可
・四伸頂通気方式:排水立て管には原則オフセット禁止
・伸頂通気管:排水立て管の頂部より細い管径で大気開口
・ループ通気方式:最上流器具の下流から立ち上げる
・結合通気管:高層建築物でブランチ間隔10以内ごとに設ける
・通気立て管上部:最高位器具のあふれ縁から75mm以上高い位置
・通気立て管下部:最低部の排水横枝管より高い位置
・通気管末端:窓・換気口等の上端から600mm以上立ち上げて大気開口
・ループ通気方式:大便器8個以上 → 逃し通気管必要
・伸頂通気方式:排水横主管の水平曲がりは1m以内に設けてはならない
・通気管取り出し角度:排水管断面の水平中心線から30°以内
■ 通気方式に関する表
| 通気方式 | 特徴・制限事項 |
| 各個通気方式 | 自己サイホン作用の防止に有効 |
| 伸頂通気方式 | 排水横主管以降が満流になる場合は使用不可 |
| 四伸頂通気方式 | オフセットを原則設けない |
| ループ通気方式 | 器具排水管の直下流から通気管を立ち上げる |
| 結合通気管 | 高層建築物でブランチ間隔10以内ごとに設ける |
■ 排水通気設備の保守管理
・排水ポンプ:毎年オーバーホール
・水中ポンプのメカニカルシール:1~2年に1回交換
・水ポンプ:毎月 絶縁抵抗測定(2MΩ以上)
・修理後:絶縁抵抗測定・アース線接続確認後に運転
・排水槽清掃:2年以内ごとに1回(建築物環境衛生管理基準)
・排水槽:硫化水素による劣化あり
・清掃前確認:酸素10%以上・硫化水素20ppm以下
・清掃後:水張りで防水性能確認
・悪臭対策:12時間以内排水・タイマーによる強制排水
・掃除口:ネジ部にグリース塗布禁止
・排水管の有機性付着物除去:酸性洗浄剤
・通気管:2年に1回定期点検
・ロッド法:最大30mまで接続可能
・スネークワイヤ法:40mまでの排水横管清掃に使用
・空圧式清掃(ウォータラム):圧縮空気で閉塞物除去
・グリース集器廃棄物:一般廃棄物として処理
・グリース除去:7~10日に1回
・高圧洗浄:0.5~3MPaの水圧で洗浄
・排水管内確認:内視鏡で詰まりや腐食を確認
■ 衛生器具設備
・衛生器具の分類:
→ 給水器具、水受け容器、排水器具、付属品の4種
・ユニット例:
→ 浴室、便所、洗面器、複合ユニット等
・小便器の型:
→ 壁掛け形、ストール形、壁掛けストール形
・ストール型:乾燥面狭く、臭気の発散少ない
・手動式小便器洗浄弁:人為操作で洗浄、公衆用に適
・集合感知洗浄方式:センサで同時洗浄制御
・温水洗浄便座:給水に雑用水を用いる
・ハンドシャワー:バキュームブレーカ or 逆流防止機構必須
■ 衛生器具の基本・構造・材質
・洗面器のあふれ縁:水があふれ出る最下端の部分
・衛生器具の材質:平滑で吸水性・吸湿性がなく衛生的
・陶器製:熱湯を注いでも割れない
・ほうろう鉄器製:金属たわしでこすらない(NG)
・トラップは付属品に分類され、着脱式が望ましい(一体型NG)
・小便器リップ高さ:床面からあふれ縁までの垂直距離
・鏡に水分放置:汚れが付きやすくなる
■ 給水配管・設備工事
・上向き配管方式:最下階から枝管を上向きに配管
・ポンプ直送方式:最上階から枝管を下向きに配管
・高置水槽方式:場水管は下り勾配で配管
・給水管の流速:最大4m/s以下
・給水管の下方分岐:上取り出しとする
・揚水管の水柱分離部:ウォータハンマ発生リスク
・さや管ヘッダ工法:住戸内でヘッダから器具へ単独配管
・クロスコネクション防止:逆止弁の設置が必要
・給水・排水管の埋設:水平距離30cm以上
・給水設備の保守:ポールタップの手動操作点検・管内色度等の検査
■ 給水管径と洗浄弁接続
| 接続対象 | 給水管径 |
| 大便器洗浄弁 | 25mm |
| 小便器洗浄弁 | 13mm |
■ 洗浄水量区分(衛生器具)
| 器具 | 区分 | 洗浄水量(以下) |
| 大便器 | I型 | 8.5L |
| II型 | 6.5L | |
| 小便器 | I型 | 4.0L |
| II型 | 2.0L |
■ 洗浄弁と故障・安全装置
・節水型大便器:8.5L以下
・節水型洗浄弁:押し続けても吐出量が増えない(定量)
・大便器洗浄弁:圧力式バキュームブレーカを設置する
・吐水トラブル:
→ ストレーナ詰まり・パッキン破損・補助水管外れ
■ 小便器の洗浄方式
| 洗浄方式 | 特徴 |
| 洗浄水栓式 | 単純な構造 |
| 洗浄弁方式 | 圧力水での即時洗浄 |
| 自動洗浄式 | センサ検知、自動で洗浄 |
| 公衆トイレ向け | 自動洗浄が望ましい |
■ 衛生器具の定期点検
| 点検内容 | 点検頻度 |
| 洗面器の取付状態 | 2ヶ月に1回 |
| 便器・排水状態等の確認 | 6ヶ月に1回 |
| 小便器の排水状態 | 1年に1回 |
| わんトラップ確認(流し) | 清掃後、毎回 |
■ 衛生設備・水槽・保守
・受水槽:1年以内ごとに1回の清掃(簡易専用水道)
・残留塩素保持不可:塩素剤注入装置を設置・管理
・管更生工法:合成樹脂ライニング工法などがある
・防錆剤を使えば、布設替え不要のケースもある
・水洗い再開前:色度・濁度・臭気・味を検査
■ 給湯の設計基準
| 使用場所 | 設計給湯使用量(人・日) |
| 事務所 | 7~10L |
| ホテル宿泊部 | 約50L |
・厨房皿洗い機:すすぎ温度 80°C程度
・水は温度上昇で比体積が小さくなる
■ 浄化槽の処理フロー(簡易・大型別)
● 処理人数が少ない場合のフロー
流入管渠・インバート升
→ 嫌気ろ床槽 or 沈殿分離槽
→ 生物反応槽(ばっ気槽)
→ 沈殿槽
→ 消毒槽
→ 放流
↓
汚泥(再循環・濃縮・処理)
● 処理人数が多い場合のフロー
流入管渠・インバート升
→ 粗目スクリーン
→ 微細目スクリーン
→ 流量調整槽
→ 生物反応槽
→ 沈殿槽
→ 消毒槽
→ 放流
↓
汚泥(汚泥濃縮貯留槽へ)
■ 単位装置と点検項目
| 装置名 | 主な点検項目 |
| ばっ気槽 | MLSS濃度、DO(溶存酸素)、スカムの生成、汚泥沈降性 |
| 接触ばっ気槽 | 生物膜の形成状況、異物付着、スカム生成 |
| 沈殿槽 | 沈殿物の状況、透視度、堆積汚泥のpH、スカム |
| 消毒槽 | 残留塩素濃度、薬注装置の動作 |
| ポンプ類 | 起動・停止水位、作動音、異常振動 |
■ 浄化槽の基本知識
・放流水BOD基準:20mg/L以下(技術上の基準)
・活性汚泥:好気性微生物(細菌・原生動物)による代謝処理
・浄化槽法の定義:下水道以外に放流するし尿+雑排水の処理設備
・保守点検記録:作業内容を記録し、2年間保存義務
・指定機関の水質検査:2年に1回必須
・保守点検は登録業者**に委託可(許可制ではない)
■ 高度処理対象物質と除去法
| 対象物質 | 主な除去法 |
| 浮遊性有機物質 | 急速砂ろ過法、凝集沈殿法、活性汚泥法 |
| 溶解性有機物質 | 活性炭吸着法、生物膜法、オゾン酸化法 |
| アンモニア・窒素化合物 | 生物脱窒法、イオン交換法、散水ろ床法 |
| リン化合物 | 凝集沈殿法 |
■ 浄化槽に関する重要ポイント
・型式認定申請:国土交通大臣
・浮上分離法:汚泥発生量・ランニングコスト共に高い(近年不採用傾向)
・最初の保守点検:使用開始直前に実施
・浄化槽製造業:登録制ではない
・浄化槽管理者と浄化設備士は無関係
■ 計算問題(例)
● 汚泥発生量
汚泥発生量(m³/日)
= 流入BOD量 × 汚泥転換率 ÷(100 – 含水率)
● 処理対象人員の算出(複合用途ビル)
| 用途 | 人数算定式 |
| 一般店舗 | n = 0.07A |
| 飲食店 | n = 0.7A |
| 事務所(厨房無) | n = 0.06A |
例:延床3,000m²(店舗2,000、飲食500、事務所500)→ 360人
■ 特殊設備と保守管理
・浴槽循環水消毒:消毒剤投入口はろ過器直前に設置
・オーバーフロー方式:床洗浄水が入らない構造とする
・浴槽水供給:底部付近から供給する
・打たせ湯に循環水を使うのはNG
・水景施設:吐水口空間(空間を設けて間接給水)
・プール水:オゾンや紫外線と塩素を併用
・吸い込み事故防止:取水口に安全対策必須
■ 厨房設備・HACCP
・厨房機器材質:吸水性なし、耐水・耐食性あり
・食品接触部:衛生的・洗浄殺菌しやすい構造
・HACCP:各段階でリスク分析し、重要管理点を連続監視する方式
■ 浄化槽の処理フロー(処理人数別)
● 少人数処理用フロー(合併処理浄化槽)
流入管渠・インバート升
→ 嫌気ろ床槽 or 脱窒ろ床槽 or 沈殿分離槽
→ 生物反応槽(ばっ気槽)
→ 沈殿槽
→ 消毒槽
→ 放流
↓
汚泥(適宜戻し・濃縮処理)
● 大人数処理用フロー(施設用浄化槽)
流入管渠・インバート升
→ 粗目スクリーン
→ 微細目スクリーン
■ 消防用設備の法定点検内容
| 点検種別 | 内容 | 実施頻度(特定防火対象物) |
| 外観点検 | 設備の損傷・異常の有無などを目視確認 | 6ヶ月に1回 |
| 作動点検 | 実際に操作して機能確認(例:ポンプ作動) | 6ヶ月に1回 |
| 機能点検 | センサーやアラーム等の動作確認 | 6ヶ月に1回 |
| 総合点検 | 総合的に一連の動作を確認 | 1年に1回(非特定は3年に1回) |
・点検者:一定規模以上の特定防火対象物 → 消防設備士または消防設備点検資格者
・結果報告:1年に1回(非特定は3年に1回)
・点検で不備があれば、是正措置の報告義務あり
■ 消防用設備の種類と特徴
| 設備名 | 特徴・ポイント |
| 消火器 | 初期火災対応、公設消防隊用ではない |
| 屋内消火栓設備 | 自衛消防隊や関係者が使用、1号消火栓は一人操作可能 |
| 屋外消火栓設備 | 箱型・スタンド型・地下ピット型がある |
| スプリンクラー設備 | 火災時に自動散水、閉鎖型(混式・乾式・予作動式)と開放型あり |
| 放水型スプリンクラー | アトリウムや大空間用、固定式・可動式がある |
| 泡消火設備 | 空気遮断・冷却・油火災対応 |
| 粉末消火設備 | 炭酸水素ナトリウム等の粉末で消火 |
| 不活性ガス消火設備 | 酸素濃度低下で消火、警報→起動スイッチの手動起動 |
| 連結送水管 | 公設消防隊専用、建物内部の放水栓へ接続するための装置 |
| 連結散水設備 | 地下街等で使用、受水槽と連結された散水ヘッドから放水 |
■ その他重要知識(ガス・設置関連)
・ヒューズガス:火災時に温度感知で自動的にガス遮断
・引込管ガス遮断装置:地上から緊急操作でガス遮断可能
・ガス管の建物引き込み部:土切り部の露出箇所に伸縮継手設置
■ 注意すべき誤記・引っかけ
| 記述 | 正誤 | 解説 |
| 不活性ガス消火:冷却作用が主 | × | 酸素濃度の低下による消火が主 |
| 開放型スプリンクラー:感熱部が分解 | × | 感熱部がない(常時開放) |
| 連結送水管:従業員用 | × | 消防隊専用 |
| 放水型スプリンクラー:閉鎖型予作動式 | × | 開放型または固定式で大空間用 |
| 消火器:中期段階用 | × | 初期火災対応用 |
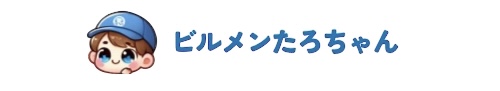

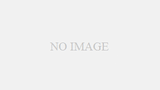
コメント