■ 清掃・点検のルールとポイント
・帳簿書類には、清掃・点検・整備の年月日や内容を記録する
・清掃用器具は共通使用(効率重視、区域別の使い分けなし)
・保管庫は1年以内ごとに1回点検
・大掃除は1年以内ごとに1回実施(日常清掃が及ばない箇所を除じん・洗浄)
・廃棄物処理設備(収集・運搬・貯留)は6カ月以内ごとに1回点検
・建築物清掃管理仕様書:基本方針・作業範囲・作業環境・作業時間などを記載した総括的なもの
・清掃者は廃棄物の分別環境を整備し、利用者に分別を促す
■ 清掃の分類と特徴
| 区分 | 内容 | 頻度・備考 |
| 日常清掃 | 頻繁に行う基本清掃 | 原則1日1回 |
| 定期清掃 | 汚れやすい場所や除じん・洗浄を計画的に実施 | 週1・月1・半年に1回など |
| 臨時清掃 | 必要が生じたとき | その都度 |
| 大掃除 | 汚れの蓄積部分を対象に計画的清掃 | 1年以内ごとに1回 |
■ 各場所・設備の清掃分類(頻度の例含む)
| 清掃対象 | 清掃種別 | 備考 |
| 共用区域 | 日常清掃 | 最も頻繁に使われる場所 |
| 専用区域 | 日常清掃 | 毎日1回以上の清掃が必要 |
| 繊維床の除じん | 定期清掃 | |
| エスカレータのランディングプレート | 定期清掃 | |
| エスカレータのパネル洗剤拭き | 日常清掃 | |
| エレベータかご内部の除じん | 定期清掃 | ※例外注意! |
| 廊下壁面のスイッチ回りの洗剤拭き | 日常清掃 | |
| 床面の洗浄と床維持剤塗布 | 定期清掃 | |
| フロアマットの洗浄 | 日常清掃 | |
| トイレ・洗面所の換気口の除じん | 定期清掃 | |
| 事務室窓台の除じん | 日常清掃 | |
| ドアノブなどの金属類の除じん | 日常清掃 | |
| 建築物内駐車場の除じん | 日常清掃 | |
| トイレ清掃時 | ― | 全面的に使用禁止 |
■ 点検・作業管理の頻度一覧
| 内容 | 頻度 |
| 清掃用資材の保管庫 | 1年以内ごとに1回点検 |
| 大掃除 | 1年以内ごとに1回 |
| 廃棄物処理設備(収集・運搬設備、貯留設備等) | 6カ月以内ごとに1回点検 |
| 清掃作業の計画・手順書及び実施状況の確認 | 3カ月以内ごとに1回点検 |
■ 試験に出やすいポイント整理
・「洗浄・洗剤拭き」→ 定期清掃のイメージ
・「除じん」→ 日常清掃が基本
・ただし、エレベータかご内部の除じんなど例外あり(定期清掃)
・記録の保存=責任の明確化につながる
・清掃は作業計画に基づき周期・頻度を明確に設定して行う
■ 建築物清掃の品質評価のポイント
・品質評価の目的:要求品質と実際の品質のギャップ修正
・組織品質は、事業所管理品質と作業品質の2つから構成
・組織品質の良否は、作業品質の良否に影響を及ぼす
・清掃者本人ではなく、管理者・評価者が評価を行う
・評価の頻度:
・管理者など→年1回
・現場責任者→月1回
・品質評価→3か月に1回
■ 品質評価の実施方法・流れ
| 評価要素 | 内容・備考 |
| 評価実施者 | 清掃者以外の管理者・評価者 |
| 評価の立場 | 利用者の視点で行う |
| 評価範囲 | すべての清掃箇所が対象、特に汚染度の高い箇所に重点を置く |
| 評価方法 | 基本は目視(※科学性に乏しいため、場合によって光沢度計などを併用) |
| 点検計画 | 品質評価実施計画に基づき実施 |
| 改善指示と再点検 | 評価者が改善指示 → 清掃責任者が対応 → 改善後の再点検を実施 |
■ ほこり・汚れの種類と対応法(表)
| 汚れ・ほこりの種類・部位 | 特徴・洗浄方法など |
| 水溶性のかさ高固着物 | 水洗いで除去可能(物理的力がなくてもOK) |
| 疎水性の汚れ | 湿ったタオルで軽くこすり、タオルに付着することで判別 |
| アルミニウム建材の汚れ | 弱アルカリ性洗剤を使用 |
| 洗剤成分の残留 | 汚れの予防効果がある |
| 階段の壁面 | 他の場所よりほこりの付着度が低い |
| 保護膜(汚れ予防) | 剥離しにくいものが望ましい |
■ 清掃作業法の特徴・使い分け(表)
| 方法名 | 使用素材 | 特徴・効果 | 注意点 |
| ダストコントロール法 | 不乾性鉱油(粘度高) | ほこりの除去に有効。油分を含む | 閉鎖空間向け |
| ダストクロス法 | 油不使用のクロス | 繊維の隙間で土砂等を回収 | 油による床面弊害がない |
| バキュームクリーニング | ― | カーペットの織り目に入った汚れは除去不可 | 限界がある |
| 研磨洗浄 | ― | 凹凸のある床は、研磨粒子パッド使用不可 | 研磨ブラシを使用する |
■ ほこりの予防・建物構造と対策
| 予防・対策方法 | 効果・注意点 |
| シール剤や床維持剤の塗布 | 汚れ・ほこりの予防効果がある |
| 出入口に前室を設置 | ほこりの侵入防止に有効 |
| 防じんマット(6~8歩分) | ほとんど効果なし |
| 自動開閉式・回転式扉 | ほこりが侵入しやすい |
| エアカーテン | ほこりの発生・侵入防止に有効 |
| プラスチック製品上のほこり | 単に載っている状態なので容易に除去可能 |
| おがくず清掃 | ほこりの付着性が高く、有効な除去方法 |
| 現代の高気密建築 | 隙間や窓が重要な侵入路 |
■ 試験対策の要注意ポイントまとめ
・評価は清掃者本人が行ってはダメ。第三者的立場から実施
・作業品質と組織品質の違いを理解すること
・評価頻度(年1、月1、3ヶ月に1)を覚える!
・「油を使うか使わないか」で、ダストコントロール法とクロス法を区別
・凹凸床=研磨粒子パッドはダメ。研磨ブラシを使う!
■ 清掃用機械の分類と特徴(表)
| 名称 | 特徴・用途 | 対応床・素材 | よく出るポイント |
| ポリシャー(床磨き機) | 低速回転で床洗浄・ワックス剥離などに使用 | 凹凸のある床面、ビニル床、石床など | ブラシ径20~50cmが主流 |
| 高速バフ機 | 毎分150~300回転、光沢出し | ワックス塗布後の床など | 回転数を覚える |
| 超高速バフ機 | 毎分1,000~3,000回転 | より高い光沢仕上げ | 「超」高速と数値の違いに注意 |
| 自動床洗浄機 | 洗剤供給式+吸水式の一体型。ドライ式ではない! | ビニルタイル・石床 | よく出るNGワード:ドライ式ではない |
| 洗剤供給式床磨き機 | 洗剤+回転ブラシ+泡+真空吸引の組合せ | 化繊タフテッドカーペット | カーペットシャンプーに使用 |
| ローラブラシ方式機械 | 泡を内部で生成し、縦回転ブラシで洗浄(ドライフォーム方式) | ウールのウィルトンカーペット | 柔らかい当たりでパイル傷みにくい |
| 噴射吸引式機(エクストラクタ) | 洗剤液を噴射→直後に吸引。泡ではない。 | 水に強いカーペット | シャンプー後のすすぎにも使用可能 |
| スチーム洗浄機 | 高温蒸気で汚れ分解。水分少なめで柔らか仕上げ | シミ取りや軽度の洗浄 | しみ取り使用例を押さえる |
■ 床用パッドの色と用途(粗→細)
| 色 | 種別 | 用途 |
| 黒 | 最も粗い | 樹脂皮膜の剥離 |
| 茶 | 粗い | 剥離作業補助など |
| 緑 | 中間 | 一般洗浄用 |
| 赤 | 細かい | スプレーバフ用 |
| 白 | 最も細かい | 光沢出し(仕上げ) |
■ 掃除機・その他清掃器具の特徴
| 名称 | 特徴・用途 |
| 真空掃除機(一般) | 電動ファンで機内に低圧域を作り、ホースから吸引 |
| アップライト型掃除機 | カーペットのバイル内部のほこり除去に適する |
| カーペットスイーパ | 表面の除じんに使用 |
| 三つ手ちり取り | 頑丈(全民製)で多量のごみ処理に適する |
| 改良ちり取り | 置くと蓋が開く→移動時にゴミがこぼれにくい |
| 自在ほうき | 馬毛製でほこりが舞い上がりにくい |
■ 出題されやすいポイントまとめ
・自動床洗浄機はドライ式ではない!(水と吸引の併用型)
・ポリシャー・バフ機の回転数を暗記(高速:150~300、超高速:1,000~3,000)
・洗剤供給式床磨き機=泡を生成・回収する構造、タフテッドカーペット向き
・ローラブラシ方式=泡で洗浄、パイルへの負荷少なくウィルトンカーペット向き
・噴射吸引式(エクストラクタ)=泡ではない!
・スチーム洗浄機=高温水蒸気でしみ取りや軽洗浄に使用
■ 試験で間違えやすい比較ポイント(表)
| 比較対象 | 覚えるべき違い |
| 自動床洗浄機 vs ドライ式 | 自動床洗浄機はドライ式ではない!(水使用) |
| 洗剤供給式 vs 噴射吸引式 | 泡の使用有無:供給式→泡/吸引式→泡ではない |
| ダストクロス vs ダストコントロール | クロス=油なし/コントロール=油使用 |
| ウィルトン vs タフテッド | ウィルトン→ローラブラシ式/タフテッド→供給式機械 |
■ 床維持剤の種類と特徴(表)
| 種類 | 特徴・用途 |
| フロアフィニッシュ | 着色剤を含まない |
| フロアポリッシュ | 容易に除去できる 水性ポリマー |
| 水性ワックス | 乳化性、水で落とせる |
| 油性ワックス | 耐久性が高く安価だが除去しにくい |
| フロアシーラ | 容易に除去できない/下地止め剤 |
| フロアオイル | 表面加工なしの木質系床材の保護に使用 |
■ 床材の特徴とメンテナンス注意点(表)
| 材質 | 優れた点 | 欠点・注意点 |
| リノリウム | 抗菌性、天然素材 | 耐アルカリ性に欠ける |
| 弾性アスファルトタイル | 耐水性 | 耐アルカリ・耐溶剤性に欠ける |
| ゴムタイル/ゴムシート | 耐摩耗性 | 剥離剤で黄変しやすい |
| 塩ビタイル/塩ビシート | 酸・アルカリに強い(耐薬品性) | 可塑剤が密着不良や変質を招く |
| 花崗岩 | 耐酸・耐アルカリ・耐溶剤性 | 耐熱性に欠ける |
| セラミックタイル | 耐酸・耐アルカリ・耐摩耗性 | 硬く割れやすい |
| コンクリート | 安価で強度あり | 耐酸・耐アルカリに弱い |
| 大理石/生テラゾ | 美観に優れる | 耐酸性に欠け、酸で劣化 |
■ 洗剤・助剤・汚れ別対応
| 種類 | 特徴・用途 |
| 酸性洗剤 | 尿石・水垢の除去に有効(便器など) |
| 中性洗剤 | 木質系床材に使用(素材を傷めない) |
| 強アルカリ性洗剤 | 油脂分汚れ向け(厨房床など)/※ゴム系タイルNG |
| ビルダー(助剤) | 表面張力低下→再付着防止 |
■ 木質系・繊維系床材の特徴
・木質床材
・シールあり → 水性ポリッシュOK
・シールなし → 油性ワックスを使用(耐水性なし)
・木の硬さ:広葉樹 > 針葉樹
・洗剤は中性を選択
・繊維床材(カーペットなど)
・60%以上が親水性の汚れ(しみ)
・しみ取りは日常清掃で実施
・バイル表面 → カーペットスイーパ
・バイル内部 → アップライト型掃除機
■ 清掃方法の種類(表)
| 方法名 | 特徴・目的 | 機械・備考 |
| ドライバフ法 | 研磨剤なしのパッドで光沢回復 | 超高速回転(毎分1,000回転以上) |
| スプレーバフ法 | スプレー液を使ってつや出し | バフ機で光沢向上 |
| スプレークリーニング法 | フロアポリッシュ皮膜ごと削り、汚れ除去 → 再塗布 | 毎分200回転程度の床磨き機を使用 |
■ 清掃作業に関わる安全衛生
| 内容 | ポイント |
| 防災対策 | 自然災害だけでなく人為的災害にも対応 |
| 洗剤使用 | 説明書+保護具(手袋・マスク等)を必ず使用 |
| ノロウイルス対策 | 嘔吐物→拭き取り→クレゾール石けん液で消毒 |
| 事故防止 | 転倒防止は清掃者・第三者両方を守る |
| 事故の主因 | 激突・感電が最多 |
| ゴンドラ作業 | 特別教育が必要 |
| ローリングタワー(移動式足場) | 手すり付きでもヘルメット着用は必要 |
| 吸殻の処理 | 防火対策として重要 |
■ その他の重要ポイント
・清掃従事者の控室や倉庫の面積・設備基準は「建築物衛生法」で規定あり
・床洗浄の作業範囲を確保するためにローリングタワーを使用
・ドライメンテナンス法:滑りにくく、安全性が高く、工程が少ないのが特長
■ 床以外の清掃作業のポイント
・EV(エレベーター)インジケータや扉の汚れは油溶性
・階段壁面のほうが廊下壁面よりほこりが多い(→逆にしない)
・トイレ清掃は全面閉鎖せず、工程を工夫
・手垢が付きやすいのは夏期(汗・皮脂の影響)
・照明器具の清掃:年1~2回
・スポットクリーニング(繊維):月1回程度
・金属板のクリアラッカは半年後に剥離洗浄
■ 外装清掃・立地別清掃頻度(表)
| 清掃対象 | 清掃頻度目安 |
| 石材・磁器タイルの壁面 | 3~5年に1回 |
| 海岸地帯の金属製の外壁 | 年3~4回 |
| 臨海工業地帯の金属外壁 | 年4~6回 |
| 臨海工業地帯の窓ガラス | 月1回(6ヶ月~1年に1回) |
| 外壁の美観維持 | 1~2ヶ月に1回が望ましい |
■ 窓ガラス清掃のポイント
・スクイジー法:水+スクイジーで汚れ除去。研磨剤は使わない
・自動窓拭き設備:原理は同じ。スチーム洗浄機は付いていない
・人の作業の方が仕上がりが良い
・飛散防止フィルムは剥がさないよう注意
・光触媒コーティング(酸化チタン)は洗浄効果増強ではなく、清掃回数削減目的
■ 清掃資機材倉庫の設備基準
・施錠できない構造(頻繁に搬出入があるため)
・照明・換気・給排水設備を設置する
・床・壁材は不浸透性建材とする(濡れモップなどの収納に備える)
・資機材は建物規模に関わらず1か所に集約
■ 建材別の性質と洗剤使用の注意(表)
| 建材 | 優れた点 | 注意点・苦手なもの |
| リノリウム | 天然素材・抗菌性 | 耐アルカリ性に乏しい |
| コンクリート | 強度あり | 耐酸性に乏しい |
| 大理石 | 高級感、美観 | 酸に弱い |
| セラミックタイル | 耐酸性・耐アルカリ性に優れる | 表面が硬く割れやすい |
| 花崗岩 | 耐薬品性あり | 耐熱性に欠ける |
| 塩ビタイル | 耐薬品性・耐水性あり | 可塑剤の影響で密着不良が起きる |
| ゴムタイル | 耐摩耗性・耐溶剤性あり | 剥離剤で黄変する恐れ |
| テラゾ | 人工大理石で酸に強い | ― |
■ 洗剤・助剤・清掃剤に関する知識
・一般用洗剤:弱酸性/泡立ちが多く作業性向上
・合成洗剤:硬水・冷水でもよく溶ける
・助剤(ビルダー):表面張力を下げ再付着防止
・陰イオン系/陽イオン系:界面活性剤の分類
・石けんは硬水では洗浄力が低下する
・アルカリ性洗剤:尿石・水垢除去にも有効
・カーペット用洗剤:速乾性・粉末化が特長
・剥離剤:界面活性剤+低級アミン含有/ゴム系床材には注意(ひび割れ)
■ 清掃用機械・器具のポイント
・アップライト型掃除機:カーペットのバイル内部の除じん
・真空掃除機:機内に低圧域を作り吸引(床移動型はバッテリー式が多い)
・高性能フィルタ付き掃除機は清浄度要求が高い場所に使用
・スクラバ方式の洗浄力はローラブラシ方式より劣る
・ドライメンテナンス用高速床磨き機:超高速回転(1000rpm超)
・タンク式スクラバマシン:カーペットシャンプー可、高速回転タイプ
・エクストラクタ:洗剤液を噴射→直後に吸引、泡ではない
・ドライフォーム方式:泡を供給し縦回転ブラシで洗浄
・スチーム洗浄機:しみ取りにも使えるが水分残留が多い
・パウダークリーニング:汚れが深く入ったときの全体洗浄に使用
■ ドライ vs ウェット メンテナンス法(比較)
| 比較項目 | ドライメンテナンス | ウェットメンテナンス |
| 安全性 | 劣る | 優れる |
| 資機材の量 | 多い | 少ない |
| 部分補修 | しにくい | しやすい |
| 作業工程 | 少ない(効率重視) | 多いが丁寧 |
■ ごみ・廃棄物の基本
・ごみの単位容積質量:単位は kg/m³
・分別:発生・排出元であらかじめ区分
・最終処分:埋立て処理を指す(焼却は中間処理)
・ごみの3成分表示法:水分・灰分・可燃分(%表示)
■ 中間処理とリサイクル
| 処理法 | 内容 |
| 可燃ごみ | 焼却・脱水 |
| 不燃ごみ | 破砕・圧縮 |
| 焼却の効果 | 容積:5~10%に減容化重量:30%まで減量化 |
| 再利用 | リデュース・リユース・リサイクルの3R |
| サーマルリサイクル | 熱回収(例:ごみ焼却の余熱発電) |
| マテリアルリサイクル | 物質を原料として再生(例:ペットボトル→服) |
■ リサイクル関連法
| 法律名 | 対象とポイント |
| グリーン購入法 | 環境負荷の少ない物品の調達を推進 |
| 家電リサイクル法 | エアコン・TV・冷蔵庫・洗濯機等/小売業者が引取 |
| 小型家電リサイクル法 | 携帯・デジカメ等から金属資源を再利用 |
■ 一般廃棄物と産業廃棄物の違い(表)
| 分類 | 主な排出元例 | 管轄 |
| 一般廃棄物 | 家庭・商店・事務所等(産廃以外) | 市町村・市町村長 |
| 産業廃棄物 | 建設業・飲食店・クリニック等 | 排出事業者責任・都道府県知事 |
・排出量構成:家庭系70%、事業系30%
・最も多い産廃の種類:汚泥
・再生利用率(産廃):約50%
・処理委託先:登録だけでなく許可業者に委託必要
■ マニフェスト制度(産業廃棄物管理票制度)
・処理の流れと責任を排出事業者が把握
・帳簿の保管:5年間
・電子マニフェストでの最終返却タイミング:
・B2・D票→90日以内、E票→180日以内
・返却なければ問い合わせ義務あり
■ ごみの処理・廃棄物処理法のキーワード
・焼却処理温度:800°C以上
・**焼却施設の30%**で発電(サーマルリサイクル)
・容積質量値:家庭<事務所(事務所の方が重い)
・厨芥の容積質量値は可燃ごみの2~3倍
・ビルピットの雑排水汚泥:一般廃棄物
・浄化槽の汚泥:産業廃棄物
・空きビンなど再利用目的の廃棄物:処理業許可不要
・し尿・ふん尿・動物死体なども廃棄物に含まれる
■ 保管・中間処理・減容化
・保管施設:床に集水勾配・側溝設置、室内を負圧に
・圧縮率(建物用装置):1/4~1/3
・溶融固化:熱で溶かして固める
・中間処理方法:切断・圧縮・脱水・乾燥・発酵・冷蔵など
■ 試験で注意すべき項目(ひっかけ注意)
| 問題例 | 正誤・注意点 |
| ごみの焼却=最終処分 | 誤り(焼却は中間処理) |
| 放射性廃棄物=廃棄物処理法の対象 | 誤り(対象外) |
| マテリアルリサイクル=熱回収 | 誤り(熱回収はサーマル) |
| トイレ清掃=使用を全面禁止 | 原則誤り(工程工夫で使用可) |
| アルミ建材は耐アルカリ性に乏しい | 誤り(耐アルカリ性あり) |
■ 特別管理廃棄物・分類と特徴
| 分類 | 主な対象・特徴 |
| 特別管理産業廃棄物 | 廃油・廃酸・廃アルカリ・感染性廃棄物・廃PCB・廃石綿等 |
| 特別管理一般廃棄物 | 家庭からの感染性廃棄物等 |
| 共通点 | 毒性・感染性・引火性・腐食性がある廃棄物 |
| 管理責任 | 所有者・管理者・事業者が適切に処理しなければならない |
■ マニフェスト制度(続き)
・産業廃棄物管理票にはA~E票(紙の場合)
→ 最終処分までの経路を把握できるようになっている
| 票の種類 | 内容 | 電子・紙どちらでも記録必要 |
| A票 | 排出事業者の控え | 発行時に保存 |
■ ごみ・廃棄物の定義と単位
・ごみの単位容積質量の単位:kg/m³
・ごみの3成分表示法:水分、灰分、可燃分(%表示)
・最終処分とは?:最終処分場に埋立てること
・焼却は中間処理の一手段(最終ではない)
■ リサイクルと法制度
| 区分 | 内容・対象 |
| 3Rの定義 | リデュース(発生抑制)・リユース(再使用)・リサイクル(再生利用) |
| サーマルリサイクル | 熱回収(焼却熱を発電等に利用) |
| マテリアルリサイクル | 物→物の再利用(例:ペット→衣料) |
| グリーン購入法 | 環境負荷の少ない製品の購入推進 |
| 家電リサイクル法 | エアコン、テレビ、冷蔵庫、洗濯機等/小売業者が回収 |
| 小型家電リサイクル法 | 携帯・ゲーム機など/金属資源を再利用 |
■ 一般廃棄物と産業廃棄物(比較表)
| 項目 | 一般廃棄物 | 産業廃棄物 |
| 排出者例 | 家庭、商店、事務所など | 建設業、飲食店、医療クリニックなど |
| 管理者 | 市町村 | 排出事業者(自己処理 or 許可業者に委託) |
| 処理業者の許可 | 市町村長(運搬)・都道府県知事(施設) | 都道府県知事(運搬・施設とも) |
| 再生利用率 | 約20~30% | 約50% |
| 最も多い種類 | ― | 汚泥が最多 |
■ マニフェスト制度(産廃の追跡管理)
・紙の場合の票の流れ(記号と順序):
| 票の種類 | 処理の流れ | 備考 |
| B1票 | 排出→運搬→処分→運搬 | 返却不要 |
| B2票 | 排出→運搬→処分→運搬→排出 | 90日以内に返却必要 |
| C1票 | 排出→運搬→処分 | |
| C2票 | 排出→運搬→処分→運搬 | |
| D票 | 排出→運搬→処分→排出 | 90日以内に返却必要 |
| E票 | 排出→運搬→処分→排出 | 180日以内に返却必要 |
・帳簿の保存:5年間
・電子マニフェストでも期限は同様
・運搬業者と処分業者は別々に契約が必要
■ 中間処理の具体例と処理方法
| 処理対象 | 主な中間処理 |
| 可燃ごみ | 焼却・脱水 |
| 不燃ごみ | 破砕・圧縮 |
| 厨芥(生ごみ) | 脱水・発酵 |
| 発泡スチロール | 圧縮(梱包・切断は不要) |
| OA紙、雑誌等 | 再資源化 |
| 圧縮率(建物用機器) | 1/4~1/3 |
| 容積質量 | 家庭<事務所(事務所の方が重い) |
■ 特別管理廃棄物
| 種別 | 例 |
| 特別管理産業廃棄物 | 廃油・廃酸・廃アルカリ・感染性廃棄物・廃PCB・石綿 |
| 特別管理一般廃棄物 | 家庭から出る感染性廃棄物等 |
・クリニックがテナントにある場合=ビル所有者が責任者を選任
・感染性廃棄物は長期保管を考慮した保管場所が必要
■ その他試験で狙われるポイント
・廃棄物処理の責任:事業者は自らの責任で適正処理が原則
・事業系一般廃棄物も市町村長の許可を受けた業者に委託が必要
・専ら再生利用目的の廃棄物(古紙・空きビン等)→許可不要
・ごみの焼却処理は総処理量の約20%
・焼却で容積は5~10%、重量は30%に減容
・焼却施設の約70%で余熱利用発電あり
・一般廃棄物の一人当たり排出量:約2,000g/日
■ 建築物内廃棄物の貯留・排出方式(比較表)
| 方式 | 適用規模 | メリット | デメリット・備考 |
| 容器方式 | 小規模建築物 | 初期コストが安い、作業性に優れる | 広いスペースが必要、人力搬出(ポリバケツ等) |
| 貯留・排出機方式 | 中規模 | ランニングコストが優れる | 真空収集方式より防災性が劣る |
| コンパクタ・コンテナ方式 | 大規模建築物 | 圧縮機で減容、トラックへの自動積替え可能 | 初期コスト高い |
| 真空収集方式 | 広域・大規模開発 | 空気搬送で所要人数が少ない、防災性に優れる | 初期コストが非常に高い |
■ 建築物内廃棄物の搬送方式(比較表)
| 搬送方式 | 適用建築物の高さ | 特徴・メリット |
| エレベータ方式 | 低層~高層 | 初期コストが安い |
| ダストシュート方式 | 低層~中層 | ランニングコストが優れる |
| 自動搬送方式 | 中層~超高層 | 衛生性に優れる |
| 小口径管空気方式 | 大規模 | 所要人数が少なく、設置スペースも小さい |
■ 保管場所の構造と注意点
・出入り口は自動ドア
・種類ごとに分別できる構造とする
・排水拡散防止のため、通路に段差を設ける
・床は水平(傾斜はNG)
・室内は負圧(正圧は×)
・給水栓にはバキュームブレーカ付き(大気圧式)
・保管場所の他用途との兼用は不可
・冷蔵庫:厨芥類の保管用
・容器:キャンバス製コレクタなどを使用
■ 処理設備と用途(機器別)
| 機器名 | 主な用途 |
| 圧縮装置 | 缶・可燃ごみなどの**減容(1/4~1/3)**に使用 |
| シュレッダ | 新聞紙の切断など |
| 溶融固化装置 | 厨芥類の処理 |
| 滅菌装置 | 注射針の滅菌・処理 |
| 梱包機 | ダンボールなどの圧縮・減容 |
| 破砕機 | 新聞紙の減容など |
■ 試験でよく狙われるポイント(〇×対策)
| 記述例 | 判定・補足 |
| 真空収集方式は、空気搬送である | 〇 |
| 貯留・排出機方式は真空収集方式より防災性に優れる | ×(逆) |
| コンパクタ・コンテナ方式は中規模建築物に適する | ×(大規模が正解) |
| 保管場所の床は傾斜をつけるべき | ×(水平が正解) |
| 保管室は正圧であるべき | ×(負圧が正解) |
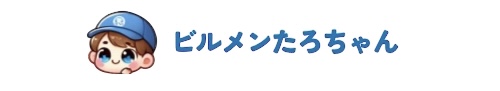

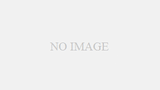
コメント